 |
まずコルクの穴を広げます。今回はコルク全体にコーティングが施してあるものを使っているので接着面のコーティングをサンドペーパーであらかじめ削り取っておきます。そうしないとグリップに白いコーティングの線が浮き出てしまいます。見かけを良くして商品価値を上げようというもくろみのコーティングなのでしょうが、一手間増えていい迷惑です。 |
||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
|
ブランクにコルクを通します。両端はなるべく質の良いものを選び、クランプのU字の溝の跡がつくのが嫌なのでワッシャーを両端に通しておきます。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
|
コルククランプで圧着します。ロッドを作ろうとする人ならこんなクランプの自作はたやすい事でしょう。 |
|||||||||||||||||||
|
旋盤の自動送りでがんがん削ります。目標の5mmくらい手前で止めておいた方が無難です。このあと金やすり、サンドペーパーで仕上げます。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
|
これで出来上がりです。せっかくですのでリールシートを装着する部分もこの機会に丸く仕上げておきます。 |
|||||||||||||||||||
|
何やらとんでもない装置になっていますが、Tools 自作編に紹介した揺れ止めを旋盤にも流用しています。向きを変えて主軸を貫通させると3爪チャックでスウェルバットのテーパー部分をくわえなければいけないのでこの方法になりました。 |
|||||||||||||||||||
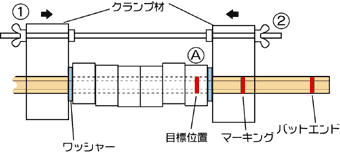 |
|||
|
グリップ取り付けで一番やっかいなのがクランプでコルクを圧着する際に圧力でグリップ全体が動いてしまう事でした。やはりグリップはバットエンドからリールシート分を差し引いた位置から始まってくれないと全体のバランスが狂います。対処法としてよく言われているのは(A)の位置のコルクをまず接着しておいてからその上に残りのコルクを積み重ねていく方法です。 |
|||
|
ですがこの方法でも(2)のクランプを締めていくと(A)のコルクはわずかですが動いてしまいます。(A)が動かないように(1)のクランプばかりを締めていきますとなかなかバット側のコルクにまで圧力が伝わらずいくら締めてもティップ側のコルクがつぶされるばかりで、そのまま続けると最後にはコルクが割れてしまう事もあります。やはり両方からクランプを締めつつ(A)を目標位置に固定したいわけです。 私の場合まず(A)が動いても良い範囲を5mmと決めます。目標位置にマークしたらその位置+ワッシャー+クランプ材の幅の位置にもマークキングします。次に目標位置の5mmバット側にコルク(A)を接着します。(A)が固定できたら残りのコルクを接着しクランプで圧力をかけていきます。まずは(1)側のクランプを締めます。なおも圧力をかけていくとやはりティップ側のコルクがつぶれてきます。頃合いを見計らって(2)を締めていきます。5mm分締めれば良いわけですがたかが5mmと言っても(1)側からすでにかなりの圧力がかかっていますので5mm分押し返すには相当な力を必要とします。また(A)側からも力を加えた事によってつぶれ方が均等になっていきます。マーキングがクランプ材の端まできたら完了です。(A)は目標位置に収まっているはずです。 簡単な事なのですが億劫がってマーキングをしないと(A)を目標位置に固定するのは雲をつかむような話です。 |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
