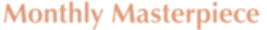 - March 2000 -
- March 2000 -| 105円x15枚の合計1,575円で、90年代のロックを振り返る | ||
■ 80年代から90年代へ 90年代と比較して80年代はダメだったとおっしゃる方々が多いけれども、その境目を多感な時期に生きた自分にとって、両者を比較して優劣を付けるのは甚だ難しい。感受性も異なれば、周りの環境も微妙に違ったし、音楽と触れるスタイル・方法もラジオ、テレビ、カセットテープ、レコード、ビデオ、CD、衛星放送、カーステ、インターネットとその季節季節で変遷があり、なおかつその時代の音のみを常に追いかけてきたというわけでもないので、正直そんな客観的な判断は致しかねる。 簡単に言ってしまえば今になって「つまらない」と吐き捨てられている時代においても、ただ単に自分が心地よいと思った音、興味を持った音、というのを聴いてきただけであって、時代性がどうの、なんていうことはその当時、これっぽっちも考えたことはなかった。 そしてそれは今も変わらない。 | ||
| でも今になって例えばファイン・ヤング・カニバルズなどという、当時かなりのヒット曲を連発していたバンドのアルバムを聴いてみるとちょっと恥ずかしくなってきてしまうのが80年代に出たバンドの音の悲しいところか? このバンドが活躍していた頃、つまり80年代から90年代への移り目の時期に、自分はその当時のトレンドを追うことはパッタリと止めていて、60、70年代の古い音を真面目に勉強していた。そしてなんとなくロックミュージックの大局的な流れのようなものも併せてこの時に掴んだような気がしている。 そんな自分の中のトレンドと合致するかのように、当時のトレンドのひとつとして、「レトロロック」というものがあって(・・・いや、ほんとにそんな言葉あったっけ?)、例えばレニー・クラヴィッツが特に日本で「第2のジミヘン、黒いジョン・レノン」などといったように今となっては恥ずかしいコピーとともに爆発的な人気を博したり、同じ黒人でもテレンス・トレント・ダービーのように60年代のR&Bの匂いを濃く映し出したアーティストも武道館レベルのマスなライヴを成功させたりしていた。リヴィング・カラーやフィッシュボーン、ユッスー・ンドゥールといった黒人アーティストが白人ロック市場に参入してきたのもこの頃のことである。 | ▼ The Finest - Fine Young Cannibals ('96)  HONDAのコマーシャルにも使用されていた「She Drives Me Crazy」があまりにも有名なFYCのベスト盤。機械的なドラムのループ、耳あたりきらびやかなギター音、拡がりのあるミックス、どれをとっても80年代的AORといった感じだけれども、楽曲的にはR&B的に素晴らしいものが多いし、この時代にあっても「慣れ」れば結構いけると思う。 HONDAのコマーシャルにも使用されていた「She Drives Me Crazy」があまりにも有名なFYCのベスト盤。機械的なドラムのループ、耳あたりきらびやかなギター音、拡がりのあるミックス、どれをとっても80年代的AORといった感じだけれども、楽曲的にはR&B的に素晴らしいものが多いし、この時代にあっても「慣れ」れば結構いけると思う。▼ Vibrator - Terence Trent D'arby ('96)  同じ黒人のR&Bでも、今のヒップホップ的な解釈ではなく、よりロック的なアプローチを以って音楽のパッションを作品に封じ込めたテレンス・トレント・ダービー。その音楽性はラテン、ソウル、ゴスペルと幅広いが、決して白人には真似できないしなやかさを全編に漂わせながら、今や死語となりつつあるファンキー・ミュージックを奏でる稀有なアーティストとなった。幅広いファン層を獲得したのもうなずける、そこまでに至る才能と大衆性が節々から感じ取れる力作。 同じ黒人のR&Bでも、今のヒップホップ的な解釈ではなく、よりロック的なアプローチを以って音楽のパッションを作品に封じ込めたテレンス・トレント・ダービー。その音楽性はラテン、ソウル、ゴスペルと幅広いが、決して白人には真似できないしなやかさを全編に漂わせながら、今や死語となりつつあるファンキー・ミュージックを奏でる稀有なアーティストとなった。幅広いファン層を獲得したのもうなずける、そこまでに至る才能と大衆性が節々から感じ取れる力作。 | |
■ 90年代はイギリスから始まった?! | ||
| そして90年代の本当の意味での幕開けとなれば、やっぱりストーン・ローゼズ!!!と行きたいところなのだが、「石と薔薇」のタイトルにひいてしまった筆者はレンタルCD屋で撃沈。この頃にはライド、シャーラタンズ、ハッピーマンデーズ、インスパイラル・カーペッツなどがマンチェスター、だのマッドチェスターだのというムーヴメントに乗ってシーンに登場したらしいことは覚えている。 同時に「渋谷陽一のミュージックスクエア」などというFM番組(毎週月曜:21:00〜22:45にNHK-FMで放送されていた。)を聞いていると毎週のように妙な発語の快感を伴うバンドが渋谷陽一の注目を浴びていた。それがカーター・ジ・アンストッパブル・セックス・マシーン、略してカーターUSMである。しかし同じく発語の快感が高かったレッド・ホット・チリ・ペッパーズに較べ、彼らが日の目を見た年月は実にはかないものであったが。 | ▼ Carnival Of Light - Ride ('94) 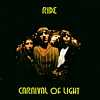 現オアシスのアンディ・ベルがいたライド。文句なしの快作。92年のレディングフェスの映像でしか彼らの姿&音を知らなかったが、ここでようやく彼らのグルーヴ・マジックの片鱗をみることができた。ここ2,3年でようやくシャーラタンズが到達した音楽的な高い地点に、ライドはこのアルバムですでに達していたかのようなハイレベルな音作り。ものすごく気持ちの高揚する作品。 現オアシスのアンディ・ベルがいたライド。文句なしの快作。92年のレディングフェスの映像でしか彼らの姿&音を知らなかったが、ここでようやく彼らのグルーヴ・マジックの片鱗をみることができた。ここ2,3年でようやくシャーラタンズが到達した音楽的な高い地点に、ライドはこのアルバムですでに達していたかのようなハイレベルな音作り。ものすごく気持ちの高揚する作品。▼ Worry Bomb - Carter USM ('94)  バンド崩壊直前、もう一発当てたる!ってな気合の入った作品。個人的にはキーボード音が邪魔かなあ、と思ったりもするけれど、逆にそれがこのアルバムの個性的な作りを表す形になっており、ただのギターバンドではないことを強くアピール。いかにもブリティッシュ的節回しに抵抗を感じる人でなければかなりお勧めな盤。 バンド崩壊直前、もう一発当てたる!ってな気合の入った作品。個人的にはキーボード音が邪魔かなあ、と思ったりもするけれど、逆にそれがこのアルバムの個性的な作りを表す形になっており、ただのギターバンドではないことを強くアピール。いかにもブリティッシュ的節回しに抵抗を感じる人でなければかなりお勧めな盤。 | |
■ その頃アメリカでは | ||
| レッチリと言えばこの頃、つまり90年代が始まってすぐのアメリカを牛耳っていたのは、ロックやグラムやメタルやパンクなどをとてつもないマスのレベルで成功させ完結させたメタリカとガンズ&ローゼズであった。特に90年代末に登場した今風のバンド=リンプ・ビズキットやゼブラヘッドのヘビネスの根源はここにあると言ってもいい。「ああ、俺と似たような音楽を聴いてきたんだな」と感じさせるこれらのバンドは、他にもフェイス・ノー・モアやモトリー・クルー、スキッド・ロウにアリス・イン・チェインズなどのお世話にもなっていたに違いない。 筆者も彼らにはずいぶんと彼らのお世話になったものだが、しかしその一方で自分はある時、人間とも動物とも宇宙人とも判別不能なとんでもないロックボーカリストを発見してしまった。 それはLA出身、ジェーンズ・アディクションのボーカリスト=ペリー・ファレルだ。後にポルノ・フォー・パイロスとしてもその活躍はお茶の間を飾る事になるのだが、彼の功績はいわゆるメインストリームとはちょこっと外れたところで頑張っているオルタナティブとかいうカテゴリーに属するロックバンド達を引き連れての音楽フェスティバルを、これまたかなりなマスなレベルで成功させてしまったことにある。このロラパルーザと銘打ったオルタナフェスのトリを飾ったアーティスト、例えばレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、スマッシング・パンプキンズ、プロディジー、メタリカ、ソニック・ユース、プライマスなどはいずれもそのまま90年代のアメリカを象徴するアーティストとして認識されるようになったし、事実自分もこのフェスのラインナップから当時の音楽状況を把握していたといっても過言ではない。その中には日本からの少年ナイフやボアダムス、デビュしたてのパール・ジャム、素っ裸で立ち尽くしたレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、そして長きに渡ってインディーズで独自の活動をしていたフレーミング・リップスなどがいたのだ。 だから自分はこのフェスに行きたくて行きたくて仕方がなかった。そしてその夢はロラパルーザ最後となった97年に叶ったのだが。そしてそこに出演したプロディジーによって、音楽観を変えられるようなステージを見せ付けられてしまったわけだが。 もちろんロラパルーザの一連のムーヴメントと並行する形で、シアトル出身の「あの」バンドが世を席捲するのであるが・・・・それは次のページで。 | ▼ Introduce Yourself - Faith No More ('87)  ヘビーメタル、ファンク、ヒップホップなどをごちゃ混ぜにしたミクスチャーロックのその先駆けとして、レッチリと並ぶ先進性をバンドの内に持っていたフェイス・ノー・モア。そんな彼らの爆発的ヒット前夜に発表されたセカンドアルバムがこれ。 とても80年代とは思えぬその音作りは、(今となって思えば)来たる90年代を予見していたかのようなヘビネスに満ち溢れている。もう少しこのバンドにも運があれば、レッチリ以上のポピュラリティが獲得できただろうに・・・・残念。 ヘビーメタル、ファンク、ヒップホップなどをごちゃ混ぜにしたミクスチャーロックのその先駆けとして、レッチリと並ぶ先進性をバンドの内に持っていたフェイス・ノー・モア。そんな彼らの爆発的ヒット前夜に発表されたセカンドアルバムがこれ。 とても80年代とは思えぬその音作りは、(今となって思えば)来たる90年代を予見していたかのようなヘビネスに満ち溢れている。もう少しこのバンドにも運があれば、レッチリ以上のポピュラリティが獲得できただろうに・・・・残念。▼ Porno For Pyros - Porno For Pyros ('93)  ジェーンズを解散したペリー・ファレルのニューバンド、ポルノ・フォー・パイロスの記念すべきデビューアルバム。決して洗練されない、延々と続く覚醒したジャムセッションを聴いているかのようだが、その中で変幻自在のリズムセクションをさらに横臥し、すべての色を塗り替えるファレルの変態ボーカルに最敬礼。なんでもいいから早く来日してくれ。 ジェーンズを解散したペリー・ファレルのニューバンド、ポルノ・フォー・パイロスの記念すべきデビューアルバム。決して洗練されない、延々と続く覚醒したジャムセッションを聴いているかのようだが、その中で変幻自在のリズムセクションをさらに横臥し、すべての色を塗り替えるファレルの変態ボーカルに最敬礼。なんでもいいから早く来日してくれ。▼ Hit To Death In The Future Head - The Flaming Lips ('92) 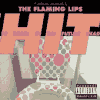 とても変なバンドだった、という先入観があったため、妙に身構えてCDデッキのスタートボタンを押したが、ひょっとすりゃ最新作「The Soft Bulletin」よりもポップじゃないのか? というかなりいい意味での肩透かしをくらったこの作品。フレーミング・リップス独特のメロディセンスと変幻自在なポップビートがうまく融合した、ものすごく聴きやすいアルバムだ。 とても変なバンドだった、という先入観があったため、妙に身構えてCDデッキのスタートボタンを押したが、ひょっとすりゃ最新作「The Soft Bulletin」よりもポップじゃないのか? というかなりいい意味での肩透かしをくらったこの作品。フレーミング・リップス独特のメロディセンスと変幻自在なポップビートがうまく融合した、ものすごく聴きやすいアルバムだ。▼ Transmissions From The Satellite Heart - The Flaming Lips ('93)  前作でリップスに対する誤解が理解へと移り変わり、安心して彼らの世界に入り込めたこの作品。リズムに太さが加わり、よりロックファンにとって聴きやすいアルバムになっている。ウェインのボーカルも不器用ながら自信に漲っていることからも、これはリップスファンならずとも絶対聴いてほしい名盤一歩手前。なんかすごすぎて笑ってしまうよこれは。 前作でリップスに対する誤解が理解へと移り変わり、安心して彼らの世界に入り込めたこの作品。リズムに太さが加わり、よりロックファンにとって聴きやすいアルバムになっている。ウェインのボーカルも不器用ながら自信に漲っていることからも、これはリップスファンならずとも絶対聴いてほしい名盤一歩手前。なんかすごすぎて笑ってしまうよこれは。 | |
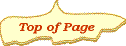
Last updated: 4/13/00 |
