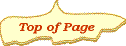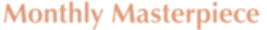 - March 2000 -
- March 2000 -
| 105円x15枚の合計1,575円で、90年代のロックを振り返る − 後編 | ||
|
■ ニルヴァーナに思うこと その日の朝日新聞朝刊では「カート・コバーンさん」自殺のニュースを彼のモノクロ写真入りで伝えていた。とてつもなく悲しい出来事だったけれど、数日前にローマでなんらかの理由による昏睡状態(in coma)を経験していたことを伝え聞いていたので、先は短いかもしれないなという思いの元に「昨日まであんなに元気だったのに・…」という感じの死ではなかった。その後は情報が錯綜してなにがなんだかよくわからなかった。音楽各誌のカート追悼特集を読んだら余計にわけがわからなくなった。おまけに「これがカートのラストインタビューだ」「いやそうじゃない」といったレベルでの争いまであってそれもかなり醜く映った。 | ||
| 前述のオルタナフェスの勃興と時を同じくして、というかその中心的存在として、グランジと呼ばれる音楽が台頭した。ギターをぐにゃーーっと鳴らして、自分自身の弱い内面をえぐり出すような歌詞を乗せた、ダラダラファッション(=GRUNGE)のバンド、みたいなパブリックイメージはあったけれど、それぞれのバンドは様々な音楽的バックグラウンドを持っていた。初期のころはパンク+サバスみたいに言われがちだったニルヴァーナのカート・コバーンも、フェイバリットアーティストに、ピクシーズ、ソニックユース、ブリーダーズ、エアロスミス、メタリカ、レッドベリー、デヴィッドボウイなどといったメジャー/マイナー、メロディアス/ラウド、オルタナ/ヘビメタを問わない音楽的嗜好を持っていた。と同時にそういった様々な異なる嗜好を持った異なるファン層を獲得できたのは、そんなカートコバーンの広い音楽的嗜好が成せる業だったのかもしれない。というかエアロにせよメタリカにせよビースティーボーイズにせよベックにせよ、90年代を生き残った(=セールスが高く安定していた)アーティストはその登場時にすべて「グランジ」「ヒップホップ」「ロウファイ」「メタル」だのというカテゴリの代表選手のように取り上げられつつも、実は逆にそこに留まらない幅広い音楽的嗜好と表現と絶妙のタイミングとによって、いつのまにかそのカテゴリを超越した存在になっていた。いまさらレッドホットチリペッパーズを「ミクスチャー」と呼ぶものはいないし、ブラーを「ブリットポップ」と呼ぶものもいないであろう。いや、いないことはないのだが、それはカテゴライズするのが好き、とかいう次元ではなくて、ただ単に彼の無知をさらけだしているに過ぎない。 |
|
▼ Soup - Blind Melon ('95) 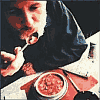 90年代のもうひとつの死。シャノン・フーンの薬物過剰摂取による死。とっくに死ぬべきだったアクセル・ローズの身代わりとなってあの世に逝ったシャノン・フーン。彼の率いるブラインド・メロンの実質のラストアルバム。カテゴライズ不可能な音楽性とペリー・ファレルにも引けを取らないシャノンのボーカリゼーション。あらゆるロックンロールを貪欲に食い尽くすその姿を、初めて彼らの音に触れる人も焼き付けておいていただきたい。
90年代のもうひとつの死。シャノン・フーンの薬物過剰摂取による死。とっくに死ぬべきだったアクセル・ローズの身代わりとなってあの世に逝ったシャノン・フーン。彼の率いるブラインド・メロンの実質のラストアルバム。カテゴライズ不可能な音楽性とペリー・ファレルにも引けを取らないシャノンのボーカリゼーション。あらゆるロックンロールを貪欲に食い尽くすその姿を、初めて彼らの音に触れる人も焼き付けておいていただきたい。
▼ Teenager Of The Year - Frank Black ('94)  ご存知ピクシーズの中心人物だったお方で、そのパンキッシュな音楽性とレスラーチックな外観とが少なからぬ話題を呼んだ、というかものすごく玄人ウケしたお方である。速い、短い、うるさい、と三拍子ソロったこのソロアルバムも、ストレートでありながらどこかトチ狂った、どこか偏屈な、どこか筋肉質な、とんでもない魅力を持ったものに仕上がっている。これが100円とは死ぬほどお得。
ご存知ピクシーズの中心人物だったお方で、そのパンキッシュな音楽性とレスラーチックな外観とが少なからぬ話題を呼んだ、というかものすごく玄人ウケしたお方である。速い、短い、うるさい、と三拍子ソロったこのソロアルバムも、ストレートでありながらどこかトチ狂った、どこか偏屈な、どこか筋肉質な、とんでもない魅力を持ったものに仕上がっている。これが100円とは死ぬほどお得。
▼ Sweet 75 - Sweet 75 ('97) 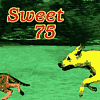 カート亡き後、ドラムのデイヴがフー・ファイターズとして華々しい再出発を果たした後、ベーシストのクリスが女性ボーカリストとユニットを組んで発表したのがこの一見地味な作品。いや確かに地味だ。しかしニルヴァーナのベーシストという先入観を取り除いて聴いてみるとこれがまた非常に味わい深い。ベルセバにも通じる静かな暴力性を持った無印良品。ボーカルのイヴァは中学の時の担任似。
カート亡き後、ドラムのデイヴがフー・ファイターズとして華々しい再出発を果たした後、ベーシストのクリスが女性ボーカリストとユニットを組んで発表したのがこの一見地味な作品。いや確かに地味だ。しかしニルヴァーナのベーシストという先入観を取り除いて聴いてみるとこれがまた非常に味わい深い。ベルセバにも通じる静かな暴力性を持った無印良品。ボーカルのイヴァは中学の時の担任似。
|
|
■ 各ムーブメントとその影に |
||
|
逆に様々にロックが細分化させられていく中で、その枠の外に跳躍するタイミングを逃してしまったバンドは数多い。まず「グランジ」という90年代アメリカ最大の音楽ムーブメントの中で結局生き残ったのは恐らくスマッシング・パンプキンズぐらい。パール・ジャムも頑張ってはいるがセールスに比例するかのように次のステップを模索する彼らのもがきも強まっているし、サウンドガーデンなんかは音楽的には器用だったけれどもマスコミ的には不器用だったのでいつのまにか解散してしまっていた。両方とも不器用なマッドハニーはかなりがんばっていたけど、90年代最後の年に解散してしまった。 そんなグランジ勢の衰退を横目に、特にカートコバーンの死を境にして、「ノリ的にはグランジっぽいんだけど、俺らもっとうまいぜ。メロディアスで泣かせるぜ。レッドツェッペリンも好きだしニールヤングも尊敬しているが、声はこっちのほうがメリケンだぜ。骨太だぜ。」といった感じでこれまたうまいタイミングで登場してきたバンドが竹の子のように現れた。そして海外では軒並みミリオンセラーを連発した。ブッシュとかライヴとかコレクティブソウルとかマッチボックス20なんかがそんなバンドの代表格なんだろうが、不思議と日本ではメディアがあまり大々的に取り上げてくれなかった。 オアシス、ブラーをその代表として「ブリットポップ」という90年代半ばのイギリス最大のロックムーブメントから生き残り、違う境地を開拓しているバンドはそんなに少なくはないが、自分が買った100円CDの中ではエコーベリーあたりがそんなバンドのひとつに該当するのだろうか。とにかくこちらの方は日本のメディアでも大々的に取り上げてブームを煽ってくれたお陰で、星の数ほどのバンドがブリットポップの名前のもとに現れ、音楽誌のカラーページを飾り、客を集め、喉もと過ぎれば皮肉られ、そんで終いには「ブリットポップは終わった」ときて本当にすべては泡と消えた。どういうわけかどのバンドも「俺らはブリットポップの渦中にはいなかった」と言い残して去っていったのは如何したものか。なんだったんだあれは。 一方アメリカではよりノイジーによりクレイジーに、ってなわけで「インダストリアル」ムーブメント。ナイン・インチ・ネイルズ、ホワイト・ゾンビあたりを筆頭としてアメリカではかなり大きな動きを形成したが、結局そこから跳躍を果たして生還したのはナイン・インチ・ネイルズだけだったかも。ミニストリーもがんばったが、一時期ほどのセールスを上げるには至らなかった。 |
|
▼ Down On The Upside - Soundgarden ('96) 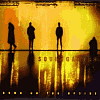 自分がテキサスへ留学したその最初の夜にMTVで聴いた「Burden In My Hand」を含む、サウンドガーデンのラストアルバム。あまりにもあっけなく解散してしまってビックリしたが、この作品を聴いてみても「なぜに?」という想いが募るばかり。明らかに音楽的バックグラウンドはレッド・ツェッペリンだが、こんなに豪快で緻密で優秀なバンドを失ったのは世界的損失だ。演奏の安定感でいえば、100円アルバム随一の出来。
自分がテキサスへ留学したその最初の夜にMTVで聴いた「Burden In My Hand」を含む、サウンドガーデンのラストアルバム。あまりにもあっけなく解散してしまってビックリしたが、この作品を聴いてみても「なぜに?」という想いが募るばかり。明らかに音楽的バックグラウンドはレッド・ツェッペリンだが、こんなに豪快で緻密で優秀なバンドを失ったのは世界的損失だ。演奏の安定感でいえば、100円アルバム随一の出来。
▼ Secret Samadhi - Live ('97) 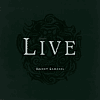 「ライヴ」というバンドを知らなくても、このジャケットには見覚えがある人も多いことでしょう。とにかくアメリカを中心に売れて売れて売れまくったこの作品。このアルバムのプロモーションツアーでは軒並みアリーナ級の会場をソールドアウトしてたっけ。ゴリゴリのアメリカンオルタナティブに日本の音楽ファンからは好感度を得難いのかもしれないが、サウンドガーデン同様安定感は抜群で、ツボにハマればどっぷりハマれる、そんな結局マニア向けな一枚? いや、そうじゃなくて。
「ライヴ」というバンドを知らなくても、このジャケットには見覚えがある人も多いことでしょう。とにかくアメリカを中心に売れて売れて売れまくったこの作品。このアルバムのプロモーションツアーでは軒並みアリーナ級の会場をソールドアウトしてたっけ。ゴリゴリのアメリカンオルタナティブに日本の音楽ファンからは好感度を得難いのかもしれないが、サウンドガーデン同様安定感は抜群で、ツボにハマればどっぷりハマれる、そんな結局マニア向けな一枚? いや、そうじゃなくて。
▼ Everyone's Get One - Echobelly ('94) 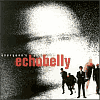 ブリットポップの・・・・と言い切れないところはあるが、とにもかくにもボーカル、ソニヤ(女)の魅力には、本国英国人よりも日本人のほうが理解を示していたことは間違いない。そんなエコーベリーのデビューアルバムでもなにはともあれソニヤ、ソニヤ、ソニヤ。モリッシーにも通ずるその歌声とポップソングに乗せた内省的な詩とが彼らのキャラを決定付けている。これからもう一花咲かせて欲しいバンドである。
ブリットポップの・・・・と言い切れないところはあるが、とにもかくにもボーカル、ソニヤ(女)の魅力には、本国英国人よりも日本人のほうが理解を示していたことは間違いない。そんなエコーベリーのデビューアルバムでもなにはともあれソニヤ、ソニヤ、ソニヤ。モリッシーにも通ずるその歌声とポップソングに乗せた内省的な詩とが彼らのキャラを決定付けている。これからもう一花咲かせて欲しいバンドである。
▼ Fifth Pig - Ministry ('95) 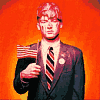 とってもノイジーなイメージでCDプレーヤーを回すと肩透かしを食らう作品。というかこういう音に時代が付いてきたのか、自分が慣れたのか。つまりとっても聴きやすいインダストリアルロックになっていて、ナイン・インチ・ネイルズのような爆発的な瞬発力よりもむしろ、錆ついたジェットコースターに乗ってハラハラしているかのような危うさに近いものを感じる。新しいアトラクション巡りに疲弊してきた頃に聴くと結構ハマるかも。
とってもノイジーなイメージでCDプレーヤーを回すと肩透かしを食らう作品。というかこういう音に時代が付いてきたのか、自分が慣れたのか。つまりとっても聴きやすいインダストリアルロックになっていて、ナイン・インチ・ネイルズのような爆発的な瞬発力よりもむしろ、錆ついたジェットコースターに乗ってハラハラしているかのような危うさに近いものを感じる。新しいアトラクション巡りに疲弊してきた頃に聴くと結構ハマるかも。
|
|
60、70年代とは比べ物にならないぐらい情報があふれ、現代の音楽のみならず過去の音楽もあふれ、その過去の遺産の寄せ集めから自分のオリジナリティーを模索し、90年代後半に登場したインターネットを含み増え続けた音楽メディアはこぞってそのムーブメントをリアルタイムで文章化し、否定し、肯定し、その情報と論壇とを情報の拠り所とする我々がいて、音楽を聴き、またそんな我々の日常の中からステージに立つ人間が現れて……ということを繰り返したのが過去のディケイドとは徹底的に違う90年代の全体的なロック界のサーキュレーションだったのではないかと思う。ここでフォローし切れなかった数多くのムーブメント=メロディックコア、ヒップホップ+メタル、デジタルロック的な潮流は今後も続くだろうし、そんな流れにあるアルバムはまだ100円で石丸電気の店頭に並ぶことはないが、ドンドコドンドコ消費されまくって、10年後に100円で売られていることを望みたい。そしてそのとき、俺は38歳か・・・・・・。 *** ここで管理人からちょっと嬉しいお知らせ *** ここまで読んでくださった感謝の意を込めて、BURPS読者から抽選で5名の方々に、この100円CD15枚から選りすぐったナンバー15曲を収めたCD-R、その名も「お得なBurps Millenium」を差し上げます。ご希望の方は下のフォームに必要事項を記入して送信してください。当選者にはメールで個別にお知らせします。 ただし! 4/1に当ホームページ掲示板上におきまして、4月バカにまんまと引っ掛かってBBSに足跡をいただいた方には、無条件でこのCD-Rを差し上げます。同様に下記フォームにご記入いただいた上でご送信ください。 応募〆切は2000年5月15日!よろしくお願いします!
|