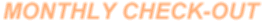 - January 1999 (2) -
- January 1999 (2) -
| By Your Side | The Black Crowes |
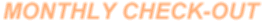 - January 1999 (2) -
- January 1999 (2) -
|
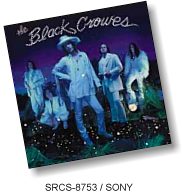 今回はしげやんとワタクシ、Katsのクロスレビューと相成りました。しげやん様、お忙しいところありがとうございました。 今回はしげやんとワタクシ、Katsのクロスレビューと相成りました。しげやん様、お忙しいところありがとうございました。
1990年デビューのアメリカはジョージア州アトランタ出身 The Black Crowesの面々の5枚目のアルバム.前作 "Three Snakes And One Charm" より長い沈黙を保っていたが,その後,ドラッグ問題,離婚問題,ギターの Marc Ford や ベースの Johnny Colt が脱退するなど,彼らを取り巻くニュースは決して芳しいものではなかったが,今作はすご過ぎる.結論から言うと,すでに今年のベストアルバムはこれで決まったかもしれない! The Black Crowes というと,最新のテクノロジーとは関わることなく我が道を歩き,泥臭くて汗が伝わってくるような迫力が持ち味であったと思うし,実際 1作目 "Shake Your Money Maker",2作目 "The Southern Harmony and Musical Companion" はエレクトリックな音がチヤホヤされる時勢の中にもかかわらず,多くの人が惹かれミリオンセラーに輝いた.しかし,一方で,3作目・4作目はかなり計算され複雑に作り込まれたものとなり,(個人的には,あれはあれで大好きなのだが)売り上げ,という点では遠く及ばなかった. しかし,今作といったら...!!! 1曲目から気合の入ったボーカルのカウントに手グセギターが合いの手を入れ,それからドラムパターンが始まる.もうその時点で体中から鳥肌が立っているのに,その後ギターのカッティング,ブルーズハープが入り...あー,イントロだけなのに何故ここまでかっこいいのだろうか.それから歌メロが始まった後は...このエネルギーは,Led Zeppelin 初期のそれを彷彿させるほどである. このバンドの最大の華はやはり Chris & Rich Robinson 兄弟であろう.Chris のぶっちぎれたボーカルが Steve Marriot (Humble Pie) や Faces 時代の Rod Stewart に例えられるのは他のどのレビューでも書かれているので,ここではあえて割愛したい.むしろ,注目したいのはギターの Rich.1枚目からギターは2人,というのがこのバンドの掟であったが,今作では1人立ち.リードギターを担当していた Marc Ford が脱退した穴を全く感じさせず,むしろ自信満々のプレイが満載である.まあ,インタビューによると,4枚目のときは Marc はドラッグでヘロヘロで,殆ど演奏出来るような状態にはなかった,とのことらしい... 何はともあれ今作のギターはかっこいい.ノッケの "Go Faster" のザクザクとした生々しい音,2曲目 "Kickin' My Heart Around" (シングルカット曲)の "Draw The Line" (Aerosmith) に "Born to be wild" (Steppenwolf) の迫力が乗っかったような(?)フレーズ,4曲目 "Horse Head" に至ってはリフがカッコ良すぎて,むしろギターが演奏していない「間」がものすごくセクシーだったりする.8曲目 "Go Tell The Congregation" に至ってはとんでもなくかっこ良いフレーズをベースとユニゾンで弾いていて,言葉を失ってしまう. ギターの細かいハナシになってしまい恐縮だが,そもそも,Rich のギターはオープンG チューニング(低音弦から DGDGBD)と,チューニングからして違うのである.それが彼ら独特の和音の響きを作り出している.1曲目・2曲目のスライドをはじめ,4曲目・10曲目・11曲目のような通常チューニングでは演奏できない低音を交えたフレーズなどはそれを象徴している. また,他のメンバーの頑張りぶりも以前とは比べ物にならないほどで,ベースのメンバーチェンジもプラスに作用しているのは,リズムセクションの安定度を考えると明らかだろう.キーボーディスト Eddie Harsch も,語られることが少ないのが不思議なほど良い味を出していて,全体のサウンドに花を添えている.特に,オーラス "Virtue and Vice" のナンバーが終わる直前のピアノは涙が出るほど美しくて,最初に聴いたときは体中が「炭酸シュワ〜」状態(!?)になってしまった. 能書きはさておき,是非このカッコ良さを体験することを強くオススメしたい.あと,お聴きになるときには2つだけ注意. 1) ヘッドフォンにしろ,スピーカーにしろ,大爆音で聴くこと. 2) CDのリピートボタンは必ずオフにしておくこと.そうじゃないと,いつまでたってもサルのように聴きまくり,このアルバムから離れられなくなるので...
いつも思うこと。それは「正統派ロックンロール」とか「ストレートなロック」って一体何じゃい?っていうこと。どうもそういうロックってのはこのブラック・クロウズやブライアン・アダムスみたいなロックのことを指すらしい。 でもさ。「正統なロック」ってなんだい? それって「健康的」で「爽快」だってこと? 健康的なロック? 確かにこのアルバムを聴くと、スカっと爽快になる。それが「健康的」の意味? でもその爽快さはプロディジーを聴いたって、ビースティー・ボーイズを聴いたって感じるぞ。そんで自分に言わせればビースティーズもプロディジーも紛れもないロックンロールだから。これには異論を挟ませない。そもそもロックにおける「正統性」ってなんだい? 響き通りの「正統派ロックンロール」って言葉がさも正しいように誤魔化されてない? 自分に言わせりゃある意味でビースティーズやプロディジーだって「正統派」だ。ロックンロールってやっぱりダンスミュージックだから、その踊りに必要な、速いビート、韻を踏んだリズミックな歌詞、そして聴衆を熱狂させるためのステージパフォーマンスが必要。だからこれらの要素を含んでいるプロディジーやビースティーズを「正統派ロック」と呼ばずして何と呼ぶ。「ストレートなロックンロール」っていう意味では彼らの音楽ほどシンプルでストレートなものはあるまい。 言っておくが「正統派=保守的」ではない。保守的な音楽なんてもうロックンロールではない。そんな音楽はアートとして絶対に認めたくもないし、自分にとっては存在価値が微塵も感じられない音楽だ。例えば外部に対して閉鎖的で至極現状満足的な一部のカントリーやクラシック(・・・だってそれが作られた当時は「クラシック」じゃなくて「新しいもの」だったはずなのに・・・。当時はある意味でそれがロックだったんだろうな・・・。)なんかがそうだ。ロックンロールが誕生して半世紀近く。そしてその成長のあゆみは、常に過去の遺産の拡大再生産から生み出されてきたことは明らかだ。上の2つのグループもそう。オアシスもレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンもそう。アマチュアでは特に顕著だが、「まったく新しい音楽を作る」なんてバンドほど新しくない。「誰々に影響を受けました。パクりました!」って公言しているバンドの方がはるかに新しいものを創造している。変な言い方だがこれが「正統的な」、「ストレートな」、ロックンロールのあり方だったのではないだろうか。 そしてこの意味で「ブラック・クロウズ=フェイセズ&ローリング・ストーンズ」という認識。これはある意味で正しいがある意味で全然正しくないというか誤解されている。まあ確かにボーカルはまるっきしロッド・スチュワートだし、ギターはスライドを使いまくりだし、ドラムもシンプルな8ビートが主体。でもしょうがないじゃん。かっこいいって感じてんだから連中が。 そんで連中はその手法をもう10年にもわたって「古くせえ」だの「真似しやがって」とか「時代錯誤」とか周りから揶揄されながら、また性懲りもなくこのアルバムでも同じことやっちゃってるんだから。もうこりゃすごいよね。ミック・ジャガーだったらとっくに方向転換して、ラップでもドラムン・ベースでも入れてるはず。そのストーンズにだって、「また72年かよー。どうなってんだ連中は?」って呆れられている。でもそんな本家本元にバカにされながらもブラック・クロウズは、「もうあの音が好きで好きでたまらねえんだ。だからおめえらごちゃごちゃうるせえんだよ! 黙って聴けバカやろー!」ってな感じ。いわば逆切れ状態。もう散々殴りまくられた後のいじめられっ子が、半泣きになって鼻水垂らしながらなりふり構わず「うううう・・・・このやろ〜ばかやろ〜このやろ〜」ってボカボカ殴りかかってくるみたいなそんな感じ。手がつけられない。降参するしかない。でも傍目に見てるとそれって鳥肌が立つほど気持ちいいんだよね。本人には悪いけど。 そんなもんだから完全にメーターが振り切れている。この時代にこのリフで来るかー!ってなフレーズが満載。普通こんなにいじめられたら、もうカントリーとかクラシックみたいにすんなり登校拒否しちゃうもん。でもそれでもやっぱりみんなと同じ土俵に上がらんとするこの心意気。いやただ単純に素晴らしい。拍手。いじめバイバイ。 と考えてくると、「正統派ロックンロール」っていい言葉じゃないかぁ(笑)。思えば90年代はそんな「正統派ロックンロールバンド」で一杯だったなあ。それって「ひねくれ者」に対する最高の賛辞だよね。ロックでは「ひねくれ」が「正統」なんだもん。ブラック・クロウズは大いなるひねくれ者で頑固者だ。おー、それでよし。 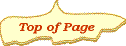
Last updated: 1/22/99 |