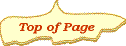|
このアルバムを聴いてまず思ったこと。それは「やっぱり70年代の曲はかっこいいなあ〜」という事実を再認識させられたということ。そして80年代の曲は80年代っぽく、90年代の曲はやはり90年代の響きを持っているということである。
「Same Old Song And Dance」「Back In The Saddle」「Last Child」「Walk This Way」「Sweet Emotion」など、それらの名前を挙げるだけでもぞくぞくしてきてしまう。またそれらの楽曲が20年代以上経ても現代に通用するのはすごい!などという馬鹿な物言いはしたくはないけれど、エアロがギターロックというものの一つの完成形を70年代末に提供し、未だにロック界はそこから一歩も進んでいないという事実を再認識させられる。ヒップホップとロックの融合、などということも現在盛んに行われているが、エアロはそんなことを「Walk This Way」でとっくの昔にやってしまっていたわけである。逆に言えばエアロは、あまりにも早くしてギターロックの可能性の頂点に到達してしまったため、その後しばらくの間袋小路に陥ってしまい、バンドは分裂してしまったのだ。
そして80年代に作られた楽曲「Dude」「Angel」「Rag Doll」らでは、当時のヴァン・ヘイレンやボン・ジョヴィらが明示した80年的サヴァイヴァル術を、分厚いストリングスを全体的に覆い被せることで成し遂げた。そして90年代には、70年代と80年代のそれぞれの方法論をミックスする形で現在彼らは商業面でも最強にあるわけである。しかし「Eat The Rich」や「Walk On Down」といった70年代的なシンプルなギターロックの方が、「Falling In Love」や「The Other Side」といった80年的装飾過剰な楽曲よりも圧倒的にかっこいいし、少なくとも自分の耳にはしっくりくる。なおかつ装飾過剰でありながら肝心要のジョーとブラッドのギターコンビネーションの妙がまったくもって生かされておらず、中途半端な印象を自分に持たせてしまうところが、実はこれらの80年代的楽曲の最大の欠陥と言わざるを得ない。しかしまたその「Eat The Rich」や「Love In An Elevator」で顕著なように、分厚い80年代的コーラスワークをここでは敢えて控えめにすることで、オリジナルで見られたある種のいやらしさがここでは完全に消え、それらの楽曲としての素晴らしさをここにきて改めて示してくれたような、そんなものもある。
すなわち、このアルバムはエアロスミスの歩んできた道程を見事なまでに映し出しているだけでなく、その時期ごとに移り変わっていくエアロスミスの音楽性にあなたの感性がどのように対応できるか改めて問い正している。このアルバムを聴いてもつ感想はその人の嗜好、及びエアロ観によって各人様々であろうが、自分は70年代的エアロスミスを圧倒的に支持するし、改めてそのパワーの有り様を確認したのである。
このアルバムに収録された楽曲をそれぞれ主にギタリストの観点から感想を書いてみたいと思う。またこれらの曲のほとんどは、実際のライヴレポートでもその様子を察していただけると思うし、比較しながら読んでいただけるとより分かりやすいのではないかと思っている。またカッコ内はそのオリジナルの発表年である。
(Disc-1)
● Eat The Rich ('93)
93〜94年のワールドツアーでトップを飾っていた曲で、個人的には大正解のオープニング! 97〜98年ツアーでの「Nine Lives」も良かったが、やはりあれはヴィジュアル面での派手さに比べて音の面ではさして驚かせられるものではなかった。この「Eat The Rich」ライヴヴァージョンは、観客の歓声が余りにも派手にイコライズされているためやや興ざめするが、確かに実際もあんな感じであった。ジョーとブラッドのコンビネーションは90年代最高の1曲といっても過言であるまい。
● Love In An Elevator ('89)
イントロのギターリフを聴いているだけでぞくぞくしてくる。実際のライヴでも最高に感動した曲で、あの「オウ、イェイ〜」という嫌らしい部分を観客に任せているため、すごくモダンでかつ70年代の勢いを秘めた楽曲としてここに提供されている。様々なギターリフをパッケージングし、なおかつ多彩なソロワークで飽きさせず、ギタリストならずとも耳を奪われるそんな1曲。
● Falling In Love ('97)
いかにも80年代的エアロの延長線上にあるかのようなこの曲。オリジナルはホーンがかなり効いていたが、このヴァージョンでのキーボードはなんかすごくいやらしい。ブラッドのプレイに精細がなく、もっと工夫すればキーボードはいらなかったはず。しかしジョーのソロワークはオリジナル通りで微笑ましく、なおかつ魅力的。
● Same Old Song And Dance ('74)
前曲とはうってかわってのいかにもな70年代テイストを発散させているこの曲。特に「What the fuck are you smokin'?」というMCが微笑みを誘う。しかしこのDisc-1では最高の輝きを放っていると思う。まずジョーのES-355での太いイントロでぶっ飛ぶし、ブラッドのソロも縦横無尽である。ギターワークが全面に押し出されているため、キーボードも邪険に聞こえないしはっきり言っていらない。いや入れるなら本物のホーン隊を従えるべき。
● Hole In My Soul ('97)
メロディーの美しさと、転調の大胆さと、スティーブンのエコーがかったヴォーカルでかなりイケてる曲。でもやっぱりなぜかストリングスがいやらしい。もう少し自然に入ることは出来なかったか? でも「Dream On」に並ぶことが出来そうな佳曲であろうと思う。
● Monkey On My Back ('89)
90年代の隠れた名曲で、かなりの割合でセットに加えられることからメンバーにとっても相当なお気に入りなのであろうことが想像できるこの曲。ピアノでのアクセントが気持ちいい。
● Livin' On The Edge ('93)
おそらく90年代のエアロにとってのエポック・メイキングなこの曲。7曲目という配置も絶妙。プレイの方はライヴだからといって特別変わったことがあるわけでもなく至極まっとうな演奏。でも聴けば聴くほどどうやってこんな曲がエアロに作れたのか、ちょっと疑問にも思うそんな優れた1曲。
● Rag Doll ('87)
ちょっと順序は前後するが、ジョーのペダル・スティールがフィーチャーされたこの曲、実はあんまり自分は好きじゃなかった。でもこの曲のメインは実はブラッド。エッチなイントロの入り方と歌メロの背後で絶妙のフレーズを絡ませているのはブラッドである。しかしキーボードのフレーズはやっぱり安っぽい。なくてもなんら影響はないと思うが。
● Cryin' ('93)
● Angel ('87)
● Janie's Got A Gun ('89)
● Amazing ('93)
印象的にはそんなに変わらず、かついい意味でも悪い意味でも80〜90年代のエアロを象徴しているこの4曲。ジョーやブラッドはあんまり好んでいないはず(笑)。思い切ってアンプラグドででもやってほしい。
(Disc-2)
● Back In The Saddle ('76)
間違いなく本アルバムの最高傑作がこの「Back In The Saddle」だ。出だしのスティーブンの声の張りがかつてのそれほどじゃないことを差し引いて考えても、圧倒的なパワーにはただ脱帽である。ジョーのベースラインは信じられないぐらいうねりまくっているし、ブラッドのプレイは恐らく彼のキャリアの中でも最高のものではないかと思えるほどにトリッキーさと気合いとが見られる。恐らくギターもエディ・ヴァン・ヘイレンモデルであろう。そしてやっぱり「Rocks」は名作だったとうなずかされてしまうそんな1曲。
● Last Child ('76)
再びその「Rocks」からのナンバーで、実際のライヴでもそうだったがこれもブラッドのプレイが冴えまくっていて、「Back In The Saddle」と並んで優れたバージョンに仕上がっている。恐らく80年代以降に覚えたのではないかと思われるピッキングハーモニックスを駆使して、自分好みのソロを操りまくっている。一方のジョーもさりげなくファンキーなおかずを入れまくっていたりして、シンプルでありながらこれだけのうねりを生み出しているのは、この2人のギターコンビネーションに他ならない。
● The Other Side ('89)
山を登り詰めたと思いきや、再び奈落の底へ転落させられる、そんな気分にさせてくれるこの曲。エアロのパクリをしたB'zの曲を、またエアロがパクったようなそんな感じである。ギターの2人もなんかやる気なさげで、単なるブギのフレーズに終始している。耳を覆いたくなるほどに気色悪いキーボードフレーズとコーラスが続く。さ、早送り早送り、と・・・・・。
● Walk On Down ('93)
ちょっと意外だがジョーのヴォーカルナンバーは、今回がライヴアルバムでは初登場になる。93〜94年ツアーでほぼ毎回演奏されており、まあいかにもジョーらしいシンプルなロックンロールだけど、ギターの定位が悪くてなんかちょっと気持ち悪い。しかしギブソンのぶっとい音が全編に聴かれて至極満足。
● Dream On ('73)
最高のバラードだが、もう飽きるほど聴いてきてやや食傷気味。ライヴでもあまり盛り上がれなかった。
● Crazy ('93)
出だしの「Come here, ベイ〜び」ってのがどうにも恥ずかしい。ジョーのストラトはなかなかいい味を出しているけれども、やっぱちょっと早送り早送り・・・・。
● Mama Kin ('73)
ブラッドがソロをとっていることから考えてみても、間違いなく97〜98年ツアーで録られたものであろう。シンプルなリフの中での多彩なギタープレーを楽しむことができるが、やや難癖をつければ、ライヴでは顕著だったピアノでのアクセントをもう少し全面に出してほしかった。
● Walk This Way ('75)
やっぱこの「Mama Kin」「Walk This Way」という流れはどうにもたまらないものだが、でもなんで「Mother Popcorn」をカットしたん??? そのメドレーを省いたおかげで、ちょっとどうにも間抜けな入りになっている。演奏自体もそんなにいいものとは思えない。しかしジョー&ブラッドのリフはやっぱり美しいし、特にブラッドのリフの弾きこなしは悦に入っている。
● Dude ('87)
これも97〜98年ツアーからとられたものであろう。でも個人的には93〜94年のツアーでのヴァージョンの方が気に入っている。しかしそちらの方は「Wayne's World 2」のサントラに入ってるので今回はボツか。いかにも80年代中期的アレンジだが、それを現代にも通用させているのはひとえにギターフレーズの組み立てと、スティーブンのボーカルに依るところが大きいだろう。
● What It Takes ('89)
スティーブンのアカペラが印象的だが、シンプルにするならもっともっと贅肉をそぎ落としても良かったのではないか。でもこのアルバムのバラードの中ではなかなかの出来。ぜひライヴでも聴きたかったなあ。
● Sweet Emotion ('75)
もし短く編集されていないのであれば、これは93〜94年ツアーからのものではないだろうか。97〜98年の超絶ロングヴァージョンが好きだった自分にはちょっと不満足で、この大ライヴアルバムの最後を飾る曲としてはやや物足りなさが残った。たぶんこの曲が食傷気味であることとも関係しているのだろうけど。
・・・というわけでお分かりの通り、70年代の曲でも、ビデオなんかで何度も聴いている定番ナンバーや、バラード、それからもろ80年代の曲にはやや辛口採点をしている。しかしこれもエアロを長いこと愛し続けてきた上でのことなので、その辺はご了承を。
まあ上のアルバム全曲解説を読んでいただいてお分かりの通り、自分はギターのブラッド・ウィットフォードがかなり好きである。よってこの人がからんでいない曲は好きではない。なおかつこの人が絡んでいない曲はいい曲とは言えないと思う。逆に言えば、この人がしっかり絡んでいる曲はいい曲なのである。
例えて言えば、自分の趣味の範囲で申し訳ないが、ブラッドとはストーンズ中期黄金期のミック・テイラーのようなものである。キース・リチャーズというギタリストの陰に隠れて表立っては派手な活動をしてこなかったように見えるこの人だが、名盤と呼ばれるアルバムでは実は中心的な役割を果たしてきたのがこの人だ。「Honky Tonk Women」のソロも、「Brown Sugar」でキースのリフを輝かせているのも、「Happy」の味のあるスライドも、「Heartbreaker」の叙情的なソロも、「Angie」の美しいピアノプレイも、みなこのミック・テイラーの力あってのことである。表のギタリストとしての看板がキース・リチャーズ、すなわちエアロスミスにおけるジョー・ペリーだとするならば、本当のギタープレイの鍵を握っていたのはミック・テイラー、すなわちエアロにおけるブラッド・ウィットフォードだと思っている。
さてそのブラッドが、このアルバムにおいてどのように重要な、すなわちストーンズでいうミック・テイラー的な働きをどのようにしているかは、上の全曲解説を読んでいただければおおよそお分かりになることであろう。逆に言えばブラッドの働きが狭められている楽曲は、そのほとんどが凡庸なものばかりである。(・・・ストーンズの場合、必ずしもそうとは言えないが・・・。) 「Angel」「Falling In Love」「Other Side」など、ジョーがその主導権を完全に握ってしまい、ソロから何まで全てやってしまっているような曲は退屈きわまりない。いやジョーのギタリストの力量を否定するとかそういうことではなくて、すなわちジョーとブラッドとの絡みがない曲はつまらないと言っているのである。なおかつこれらの曲では、ブラッドのギターの音量を下げておいて、その代わりにキーボードの音量を上げるなど、本末転倒もいいところである。
「Back In The Saddle」「Last Child」「Walk This Way」「Mama Kin」「Dream On」などをしっかり聴いてみてほしい。ブラッドの持ち場がしっかりと確立されているだけでなく、この人のギターなしでは成り立たない、そんな曲ばかりである。例えばこのアルバムで最高の出来を見せている「Back In The Saddle」。ヴァース部分の頭で鳴らされるブラッドの高音フレーズがスティーブンのボーカル以上の迫力を見せているし、それまでの陰鬱なイントロのムードを吹き飛ばすような快活な働きをみせている。また「Dream On」のソロのほとんどはブラッドによるものであり、「Last Child」はブラッドによって書かれたものである。これは「Eat The Rich」や「Love In An Elevator」にも言えることだが、ブラッドのキャラがしっかりと立っている楽曲、それらはいずれもエアロをエアロたらしめているし、ジョーにも知恵を絞らせる機会とインスピレーションを与えている。だからそんな曲ではジョーのフレーズも豊かなものになっているし、そんな曲には到底ストリングスなど入る余地は残されていない。80〜90年代の楽曲は、殊更にスティーブンとジョーのキャラを立てようとしてきたためか、イントロはジョー、ソロもジョー、いいとこは全部ジョー、みたいな作りの曲ばかりになってしまい、ブラッドの持ち味を殺してきただけでなく、それはジョーのプレイの精細のなさにもつながっていたように思う。ブラッドにただのパワーコードと、ローコードでのアルペジオだけをさせておくのはなんともったいないことか!! そんな曲に限って分厚いストリングスが被っていたりするのである。
すなわち自分がエアロスミスの70年代の楽曲を圧倒的に支持するといった意味、それはブラッドのプレイと大きい繋がりがあるということがお分かりいただけたであろうか。もしあなたが「エアロとはスティーブンとジョー!」という方なら、ぜひこれからはブラッドのプレイにも注目していただきたいと思う。でもテレビなんかではほとんど映らないところがちょっとつらいところだけど。
まったくもって蛇足だし、特に輸入盤を買った方は読んでも何のことだかさっぱりわからないところでもあろう。なおかつこれはちょっと揚げ足取りでもあるので気分を害される人もいるだろうが、やっぱ書きたいので書く(笑)。
ヘヴィメタ界では知らぬもののいないほどの重鎮、伊藤政則氏のライナーノーツ。全然つまらなかった。そもそもなんでこの人に今のエアロのライナーを書かせるのか。全くもって介せないし、エアロというバンドを、伊藤氏の大好きな保守的なヘヴィメタバンドと同様に扱われてはたまらん!という気持ちも強い。
まずこのライナーを読んでわかること。それはこのアルバムの内容に関しては一言も触れられていない、ということである。ひょっとして一度も聴かずに原稿書いた? もしそうならばエアロスミスのみならず、エアロスミスのファンに対してもまことに失礼な話しである。書いてあるのは「身体を貫く衝撃波が待っている」と「ロックンロールに対して飢えている」というこの二句だけである。こんなことは別にアルバムを聴かなくたって書ける。「あの時代のスピリットもアティトゥードも健在であることを示したかったのではないか」と書くならば、我々若い世代のほとんどが知らないその「あの時代のスピリット」とやらを解説してほしいし、それが今のクリーンなエアロとどのようにリンクしているのかの説明もなされるべきである。そもそも「(Live Bootlegから本作までの)約20年近い歴史の中で変わることのないAEROSMITH像を知ってほしいとの感覚」って大きな勘違いだと思う。逆にこの作品を聞けば、その時代時代のエアロ像の移り変わりというものが手に取るようにわかるはずなのであるから。
そして自分が最も引っかかりを覚える部分、それは「スティーブンやジョーが少年期に聴いてきたすばらしい先輩達のスピリットを継承しようとする意識と、その先輩達に対する純粋なる敬意が、作り出す音楽の底流を支えているという事実である」という下りである。言うまでもなくこれはヘヴィメタ系の評論家の常套句でもある。しかしそれをエアロに当てはめて、「彼らの音楽の底流」とするのはいかがなものか? でもまあそう聞かれればスティーブンやジョーあたりは「No」とは言わないだろうけどね。
でも「先輩達のスピリットを継承しようとする意識」が本当にエアロにあるかどうかは疑問である。そもそも「先輩達のスピリット」って何だ? ストーンズやクリームにどんなスピリットがあった? スティーブンやジョーが強く感じ入ることはあったと思うけれども、それを受け継ごうとかそういうのはあっただろうか? 思うに「うわあ、かっこいい! 俺もあんな音楽やって、あんな風にギター弾いて、ああなりてえ〜!」ってもんだったのではないだろうか。それを「スピリットの継承」って言うのかな? 下手に「先輩達のスピリット」とか「敬意」とか意識すると、クラプトンのブルースアルバムみたいに過去の曲のただの真似事になるか、場末のクラブで歌うブルースシンガーになってしまうのである。
百歩譲って仮にエアロが「先輩達のスピリット」を継承しているとしても、それがこのアルバムとどんな関係があるん?? そういう肝心のところが全く記されないまま、いきなりスティーブンの怪我の話しになったりする。全くもってわけが分からない。そしてこのアルバムの内容にこれっぽっちも触れないまま、「このアルバムは通過点にしかすぎない。」とはどういうことだあ!! 「ロックンロール求道の旅はまだまだ続く」と書くならば、本作で示された現時点での「ロックンロール求道の旅」の成果を見つめ直すことすらせずに、「通過点」と言ってしまう感覚。自分にはよくわからない。
とにかく今年、全国ドームツアーを完全に制覇するほどの勢いにあるエアロスミスの、かつその記憶を克明に映し出したこのライヴアルバムで、このようなお粗末なライナーが書かれたことは全く許すまじことだと思う。あ、ひょっとして本人が書いたやつじゃなかったりして。
| Back to Menu |
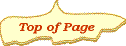
Send comments to: Katsuhiro Ishizaki .Last updated: 10/17/98
| 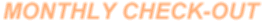 - October 1998 (2) -
- October 1998 (2) -
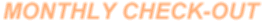 - October 1998 (2) -
- October 1998 (2) -
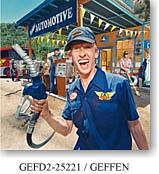 あのエアロスミスがアルバムを出した。なおかつそれがライヴアルバムとなればこれはこのディスク・レビュー始まって以来のビッグ・イッシューとなって当然。詳細にレポートするため、下のようなメニューを用意してみた。
あのエアロスミスがアルバムを出した。なおかつそれがライヴアルバムとなればこれはこのディスク・レビュー始まって以来のビッグ・イッシューとなって当然。詳細にレポートするため、下のようなメニューを用意してみた。