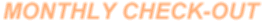 - October 1998 (3) -
- October 1998 (3) -
| No Security | The Rolling Stones |
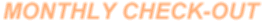 - October 1998 (3) -
- October 1998 (3) -
|
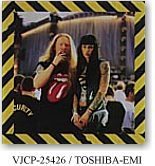
個人的にも特別の感慨を抱かせるのが、ローリング・ストーンズのライヴ・アルバムだ。そんな私からみなさんにお届けする、支離滅裂で五里霧中で勝手気ままなレビューなのだ!
|
■ Warning!
最初に断っておくけれども、このストーンズのニューライヴアルバム「No Security」 をまだ聴いていない人は、次の「全曲解説」を絶対に読まないように!(笑)このアルバムのもっともいけない聴き方、それは腕組みをして眉間にしわを寄せ、分析的にこのアルバムを聴くことである。特にストーンズファンを自認しているあなた! 絶対にそういう聴き方はやめるように! できれば曲目も見ず、ライナーノーツなんて開きもせず、買ってきたアルバムを速攻でCDプレーヤーの上に乗せていただきたい。希望としては大きなステレオセットの方がいい。なければ近所のロックバーにでも行って、大音量でかけてもらうこと。そしてイントロが流れ始めたら絶対に立つこと。これ絶対である。あとはストーンズのファンキーグルーヴ(笑)に身を任せて踊るがいい、歌うがいい、騒ぐがいい。いや、無理にそんなことしようとしなくても、自然とそうせざるを得ないアルバムに仕上がっているのだこれは! ■ After the show in Texas.... 自分は去年(97年)にテキサスで彼らのライヴを観てから、今ツアーの映像、音源、写真に至るまでほとんど手に入れていない。前回の来日(95年)のときは3回も東京ドームへ足を運んだものの、今年の来日公演は結局1回も観ずじまい。もちろん自分の当時のふところ事情その他諸々理由はあるけれども、一番大きかったのはそのテキサスでのライヴの思い出が余りにも鮮明でかつ絶対に忘れたくないようなそんなすばらしいものだったからである。そのファンタスティックな記憶をありのままに留めておくために、その後の一切のストーンズを断ってしまったのだ。もちろん春に出たセントルイスでのライヴ映像を納めたビデオも欲しかった。しかしそのアイテムがあのナマの感動を上回ることはないと思ったし、かつその記憶がビデオという第3者に犯されるのが怖かったのだ。実際エアロスミスの場合、せっかくマジソン・スクエア・ガーデンでライヴを観たにも関わらず、その後に日本で入手した当日のブートビデオを観てしまったことによって、その記憶はビデオを観る以前のそれとはかなり違うものになってしまったりしていたからだ。 ■ Need no security no more しかしそのテキサスでのライヴから1年を経て自分の耳に届いたこのオフィシャルライヴ盤は、その凛々しい記憶に変化を及ぼすようなものではなかった! 変化を及ばさないどころか、ある時点ではその記憶をより鮮明に思い起こさせ、またある時は「いやあこの曲をライヴで観たかった!」と思わせるような、そんな内容になっているのである。記憶に変化を及ぼさないその第一の理由はまずツアーの時とは曲順や構成が全く違うということ。そしてその記憶をより鮮明に思い起こさせる理由は、スピーカーから出てくる音像が、「Flashpoint」あたりで顕著だったことさらスタジアムクラスの拡がりを意識したようなものではなく、また逆に前回の「Stripped」のように殊更ライヴハウスやレコーディングスタジオのわざとらしいナマ感覚を意識したものでもなく、より自然にストーンズのライヴを体感できるということである。これは自分がテキサスで観た2〜3万人クラスの野外ステージで自分が観たあの感覚に非常に似ていて、チャーリー・ワッツのスネアといい、キース・リチャーズのエッジの立ったギターといい、チャック・リーベルの控えめなキーボードといい、全くもってあの日、あの時、ナマで観たストーンズそのままだ。めちゃくちゃクリアなわけでもなく、なにかざらついたような音像は、ステージとの適度な距離感を認めさせてくれる。しかしそれは途方もなく遠いものでは決してなく、ミックが舞う姿を正面に捕らえ、ロニーとキースがポーズを決め、チャーリーが斜め45度の方向に頭を向けているのが遠巻きに確認できる、そんなほどよい距離なのだ。 自分はこのアルバムを初めて聴いたときには、ライナーノーツどころか、曲目すらも見ていなかった。そのライナーノーツなどはこのアルバムをほんとに楽しみたいリスナーにはまったくもって百害あって一理なしといった感じで、詳細なレコーディングデータなどというのはほんとにどうでもいいことであって、なおかつそういうことを知らないとストーンズファンであってはいけない、みたいな雰囲気があることに、正直言ってげんなりしてしまったのだ。詳細なレコーディングデータを記していないストーンズ側としてもその辺ばかりを詮索されるのは本望ではないだろうし、それがストーンズの今を感じ、グルーヴしていくことには何の関係もないのだ。逆に何の知識もなくて、素直に大音量でこのアルバムを聴くことこそが本当の聴き方ではないだろうか。自分は何の詮索もなくこのアルバムを聴いた(もちろん立って!)お陰で、一曲一曲が終わる度に「次はなんだろう!」とまるで本物のライヴを観ているかのように心をときめかせていたし、キースのイントロを聴く度に「おお!こう来るかあ!」「こりゃかっこいい!」といった感動をその曲々で味わっていた。どこがどうだったかという詳しいことは後の「全曲解説」に譲るが、ライナーノーツでも顕著なように、レコーディングデータとにらめっこしながら、これはいついつの音源に違いない!などと鬼の首でも取ったかのような感想しか持てない、腰骨の弱り切った自称ストーンズフリークなどはいったいストーンズの何を聴いて、何を感じ取っているのだろうか。77年の傑作ライヴアルバム「Love You Live」発表の時に山川健一は「ブートでさんざんこの辺の音源は聴いてたから、大していいとも思わない」と言ったという。腕組み禁止! これだけはストーンズのライヴのときだけじゃなく、このアルバムを聴くときにもそのリスナーに求めたい。 ■ This could be the FIRST time といったわけで、このアルバムの個人的な楽しみ方を文字で連ねただけだが、恐らくまだこのライヴアルバムを購入していない普通のストーンズリスナーには、これがいったい何のことだかさっぱりわからないことだろう。いや、わからなくていい。実は上の話しがまったくわからないリスナーにこそこのアルバムは聴いていただきたいのである。そのへんはなおゆきさんのイギリス村でのストーンズ・ディスクレビューでも触れられているが、今のストーンズは、パルプやマニック・ストリート・プリーチャーズ、はたまたオアシスやスマッシング・パンプキンズらと並べて語っても音楽的には全く持って違和感のない存在だ。かつてマドンナやマイケル・ジャクソン、ピンク・フロイドらのスタジアム級エンターテイメントに無理して追いつかんと躍起になり(←特にミック。)、キーボードやホーンの分厚い音で辺に武装していた90年頃のストーンズとは違い、キャパ的には今でもまだスタジアム級だけれども、音楽的にはマンサンやクーラ・シェイカーらと同じ地平にいるのが現在、98年のストーンズなのだ。そのことはこの「No Security」で鳴らされている若い音楽ファン層にもおなじみのシンプルなギターロックを聴いてもらえばわかることだし、前座にフーファイやスマパン、ジャミロクワイややシェリル・クロウら若手を起用し、なおかつそれらがストーンズと同じステージの同じ地平で鳴らされていたことからも確認できるはずである。 むしろストーンズへの入り口を閉ざしているのは、ズボンズのドン・マツオも語っていたことだが、このライナーノーツを書いている越谷氏や山川健一氏らの頭でっかちで閉鎖的なストーンズに対する価値観である。(特にそのライナーの「世界最強のロックン・ロールバンド」ってコピー、いい加減にやめてくれ!)別にストーンズを理解するために無理に古いブルースを聴いたり、ギターをオープンGチューニングにしてスライドギターを弾いてみたり、くわえたばこで写真を撮ってみたり、1枚2万円もするレコードやブートレグを集めたりしなくてもいいのである。そんなものには「Fuck!!」と中指を突き立ててちゃえばいい。そしてマニックスやストーン・ローゼズやシャーラタンズを聴くときと同じように、アルバムをCDトレイに乗せ、踊りたきゃ踊る、聴きたきゃ聴く、歌いたきゃ歌詞を覚える、それでいいのだ
ストーンズデータ主義を徹底的に否定しながら、全曲解説なんかをやってしまう自分ってやっぱ矛盾してるかもしれない(笑)。 でも好きなアーティストのことを詳しく知りたいと思うのは誰でも、そしてどんなアーティストに対しても同じはず。よってこの「No Security」を聴いてみて、よりストーンズに興味を持たれた方はちょいと各曲に対する自分の感想なんてものを読んでいただけると非常に嬉しいし、今後のなんらかの指針になってくれればいいと願っている。でもまあ、本当に参考になるかはわからないけど、こういう人間もいるということでお見知り置きしていただきたいたら幸いだ。またそれぞれ主にギタリストの観点から感想を書いていて、またこれらの曲のほとんどは、実際のライヴレポートでもその様子を察していただけるかと思う。ちなみに分からないギター関連の用語は、Concert Review内にある「コンサートレビュー用語解説」などを参考にされたい。またカッコ内はそのオリジナルの発表年である。
あとこのCDをまだ聴いていない人は、決してこの先に立ち入るべからず! (きっぱり) ■ You Got Me Rocking ('94) 恐らく90年代のストーンズを代表するナンバーとくれば「Rock In A Hard Place」かこの曲ということになるであろう。前回の「Voodoo Lounge Tour」の時からほとんど毎回と言っていいほどセットリストに加えられてきたシンプルなロックンロールナンバーで、特にキースのこなれまくった演奏が印象的。オリジナルと異なり、乾いたギターのトーンがもろ「テレキャスター!!」って感じ(笑)。ちなみにこれまでのストーンズオフィシャルアルバムでは、「Under My Thumb」を除き、すべてキースのオープンGチューニングの曲でスタートしている。もちろんこの「You Got Me Rocking」でもキースはオープンGチューニングで弾いているが、このアルバムでオープンGにしているのはこの曲だけで、あとはすべてノーマルチューニング。そしてこのヴァージョンのもう一点特筆すべき点は、サポートベーシストのダリル・ジョーンズのプレイである。オリジナルではルート弾きに徹していた彼のベースだが、ここではより自分のオリジナルを発揮しており、時折「ドバババ!」とすごいフレーズを聴かせている。しかしながらキースとのコンビネーションもばっちり! ほんとにこの曲がツアーの1曲目でもよかったんちゃう? とも思ってしまうほど秀逸なヴァージョン。 ■ Gimme Shelter ('69) ひょっとして本アルバムの中では最も有名(?)なのがこの曲。だがしかしライヴアルバムに入るのは意外にもこれが初めてだったりする。89〜90年ツアーの時よりもテンポはゆったりと、しかし94〜95年ツアーのときよりも速く、すなわち最近のツアーの中ではもっともオリジナルに近いリズムでプレイされているこの「Gimme Shelter」。イントロではクリーンなトーンで聴かせるキースのギターも、バンドが入った途端に無茶苦茶な歪みを携えて、パワーコード+オブリガード一辺倒になってものすごくパワフル。しかしその陰でロン・ウッドがしっかりとギターリフを絡ませているところがなかなか心憎い。 ■ Flip The Switch ('97) ストーンズの歴史上、最もテンポの速い曲の一つとして最新スタジオアルバム「Bridges To Babylon」のトップを飾っていたこの曲。「Anybody Seen My Baby?」なんていうかったるい曲をシングルカットせずに、こっちを切った方が売れたろうになあ、などと改めて思わせるこのバージョン。「This one's called Flip The Switch!」とミックが言うも、客の歓声が少ないところがやっぱニューアルバムからの曲だなあとも思わせる。しかし演奏的には文句の付けようがなく、オリジナルよりも何倍もいい。その要因となっているのが無理のないチャーリーのドラミング、そしてキースのフィンガーピッキングを交えた、低音弦での太いリフと、キーEでの切れ味抜群のソロプレイである。特に途中で出てくる「これほんとにキース?!」と疑いたくなるような、チョーキング+ピッキングハーモニックスのプレイには驚かされるばかり。 ■ Memory Motel ('76) 前回のVoodoo Lounge Tourから再びセットリストにちょくちょく顔を見せるようになったこの名曲バラード。テキサスのモーテルで作られたとの話しがもっぱらであるが、再びツアーで演奏されるようになったきっかけは、ロッキング・オンでリクエストされたから、という噂もある。しかしとりあえず笑えるのがゲストのデイヴ・マシューズで、この人のボーカルが入った途端に、いきなり曲がAORに聞こえてしまうのはなぜ? なおかつ歌の達者なデイブ・マシューズがミックとキースの歌い方を真似ているように聞こえるのは私だけ? しかしそんなボーカルの裏で、ロニーがさりげなくワウできれいなカッティングを聴かせながらその雰囲気作りに貢献している点は見逃せない。 ■ Corinna ゲストのタージ・マハールの曲で、ここでのボーカルも本人。68年のストーンズのスペシャルテレビ番組、ロックン・ロール・サーカスでは怪演を聴かせてくれた彼だが、ここではストーンズの現役ぶりと、タージの年寄り加減が本当に見事なまでに浮き彫りになってしまい、聴いていてちょっと苦々しく感じてしまう。特に次の「Saint Of Me」の躍動的なリズムを聴くと、タージのこの曲もほんとにたーじたじ(苦)。 ■ Saint Of Me ('97) 「Flip The Switch」同様、最新スタジオアルバム「Bridges To Babylon」からの曲。正直言ってストーンズがあの現代的アレンジのオリジナルバージョンをここまで再現できていることにかなり驚かされた。まあもちろんベースのダリルと、キーがFということもあってキーボードのチャック・リーベルの力に依るところも大きいが、てっきりオリジナルではゲストミュージシャンのワディー・ワクテルのものとばかり思っていたギターソロが、ロニーの手によってしっかりと弾きこなされているところには本当にびっくりした。それどころかこの部分はロニーとキースのツインソロになっており、それぞれ全く違ったことをしていながらそれが一つのグルーヴとなる、というストーンズマジックの神髄をこの曲で再び見た気がした。そしてミックのボーカルの冴えはここでのそれが一番。しかし最後の観客の大合唱は、拍手の音に比べてかなり小さいものなので、実際のコンサートでは大したものではなかったことが想像できる。ちなみに自分はこの曲をライヴで観られなかった。 ■ Waiting On A Friend ('81) 派手な前曲のアウトロから一変して、キースのこの曲の静かなイントロが鳴り出したときには全身に鳥肌が・・・。オリジナルでは12弦ギターの響きを有効に活用されていたり、オリジナル発表直後の81〜82年ツアーではキーを変えて演奏されていたこの曲だが、このライヴバージョンは至ってシンプル。サックスはゲストプレーヤーのもの。 ■ Sister Morphine ('71) ミックのものと思われるアコースティック・ギターが鳴り響き、その中でキースの隙間の多いギターとロニーのスライドが絶妙に絡むこの曲。非常にレイドバックしており一見単調に聞こえるものの、特にロニーとキースの、何とも言えずまったりとしていて、なおかつコクのあるようなソロの応酬は、聴いててほんとに飽きない! とてもじゃないが、6分もあるマイナーキーの曲とは思えないほどの密度の濃さである。久々にロニーのいいスライドを聴いた、というよりもこのミック・テイラー時代のギターはどうやらロニーはほとんど完コピしているようである。なんでもロニーは、古い曲になるとキースのリフをキースに教える(・・・分かる?)らしいから笑える。 ■ Live With Me ('69) さあ再び立ち上がれ〜! ここからまたしても踊れる曲が続く。まずは元々のベースラインはキースが弾いていた「Live With Me」。前回94〜95年にかけての「Voodoo Lounge Tour」では、特に日本公演以降あたりから頻繁にプレイされるようになったこのナンバーだが、今回の「Bridges To Babylon Tour」でプレイされたのはたった2回のみ。このヴァージョンはそのうちの1回を収録したもので、とりあえずキーボードのチャック・リーベルがカウントを入れて始まっているところは少し納得いかないが、何はともあれキースのギターだ!! ブレイクの所でのタメの効いたオブリガードを好例にして、キースのロックンロールギターを全編に渡って聴くことができる。 ■ Respectable ('78) 「とにかくリズムを速く!」を合い言葉にして製作された「Some Girls」というアルバムからの曲で、もろ当時のパンクの影響下にあるようなナンバーだ。単純な3コードからなる曲だけれども、ロニーの「きゅるる、きゅるる、きゅるる」というアクセントが気持ちいいし、低音弦でのロックンロールの典型リフもここぞとばかりにうまくハマっている。サビのところもロニーにしては驚くべきほどしっかりとリフが刻まれているので要注目。ギターソロは最初がキース、そして次がロニー。両者のアプローチの違いが垣間見られて興味深い。しかしこの曲や「Waiting On A Friend」「Memory Motel」、そして次の「I Just〜」などはWeb Vote(=詳しくはConcert Review参照。)によって選出された曲だが、この出来の良さから判断するに、ひょっとしてただ単にメンバーが演奏したかったから披露されたんじゃないかと思えて仕方がないのだけれど・・・。 ■ I Just Want To Make Love To You ('63) 日本版のみのボーナストラックだが、この曲がボーナスだなんてなんともったいないことか!!! ひょっとしてこのアルバムで最も秀逸な作品かもしれない。ボーナストラックであるからして、ミックスもやや甘く、オーバーダブやボーカルの差し替えも全くない感じで、それがより生々しさを伝えることに一役買っている。前の「Stripped」の時のボーナストラック「Black Limousine」もあのアルバムの中では最高の出来だったから、まあ前例がないこともないのだけれど・・・・。それはともかく、これは輝くべきローリング・ストーンズ、ファーストアルバムからの曲で、オリジナルは言わずと知れたマディー・ウォータースのもの。デビュー当初のヴァージョンはよりテンポアップされており、キースのギターと、当時のメンバー、ブライアン・ジョーンズのハーモニカがぐいぐいと曲を引っ張っていたが、ここでのそれはオリジナルのマディー・ウォータース・ヴァージョンにより近く、ミックも「I just wanna make〜」ではなく、オリジナル通りに「I just want to make〜」と歌っている。キースとロニーのギターはこの曲で再びすさまじい輝きを見せており、まあいつもリハなんかではこういうブルースばっかりを2人で弾きまくってるんだろうなあ、などと思わせるナンバーでもある。また、この曲では隠し味的なホーン隊が素晴らしく、それは全般に渡ってまるでマディーやフレディ・キングのような雰囲気を作り出すことに成功している。そしてベースのダリルも、彼のキャリアの中ではもっともシンプルであろうこのフレーズを、実にグルーヴィーに弾きこなし、恐らくこの曲の良さは彼のベースなしでは引き出されなかったのではないかと思う。実は個人的にはこの曲で1番踊れた。 ■ Thief In The Night ('97) まず「It's great to be here. It's great to be ANYWHERE, you know.」というコメントが笑える。しかしテレキャスターをぶら下げて、ガーンとカッティングばっかりしているのがキースだと思ったら大間違い。最近のキースはバラードばっかり歌っているのである。そんなキースの嗜好が一番良く顕れたこの曲。オリジナルよりはややテンポアップされているような印象だが、バックボーカルがまるでゴスペル隊かなんかのようでかなりクール。まあ歌い方はいつものへたうまキースだが、気持ちよさそうに歌っているなあ、というのが伝わってきて、とりあえずマル。まあここからは座って聴くのもよしとしよう。 ■ The Last Time ('65) ミックとキースが初めて自分たちで作詞、作曲したといわれているこの曲。まあでもこのライヴ・ヴァージョンはちょっとしたご愛敬といったところか。ロニーは例のギターリフを一生懸命なぞっていて花マル。しかしキーボードがかなり邪険なのと、ヴァース部分の「told you twice!」「my advice!」といった重要なところにコーラスが入っていない点がかなりのマイナス面。よってオリジナルや当時のライヴで聴かれた、ポップで軽快な部分がかなり失われてしまっている。キースのロックン・ロール・ギターもここではちょっとマイナスかな。「19th Nerveous Breakdown」を聴いてみたかったよ。 ■ Out Of Control ('97) 単なる「Bridges To Babylon」アルバム収録のナンバーでありながら、実際のライヴでは最も力が入れられていたこの曲。ステージセットもかなり大がかりなものであった。そしてその曲をこのアルバムの最後に持ってくるあたりに、現在のメンバーの意地と自信のようなものが感じ取れる。とにかくミックは気持ちよさそうだし、言うまでもなくロニーのワウワウギターが効果的である。しかしこのアルバムを通して、ロニーのギターがシュアーでかなり安定していることはすごく嬉しかった。ひょっとして彼のキャリアを通じても本アルバムが一番の出来ではなかったろうか。あと最後の花火は音だけを聞いてもなあ・・・・。一応、「さんきゅー、ぐっない!」ぐらいあってもよかったのでは? それにこの花火はフジロックのよりもすごいんだから! 以前のライヴアルバムにも収録されたことがあるのは「Live With Me」と「The Last Time」のみ(それも30年も前に!)。ツアーではこの他にも意外とも言えるナンバーが数多く演奏されており、例えば過去のライヴアルバムに収録されたことのない「No Expectations」「Bitch」「All About You」「Wanna Hold You」「Fool To Cry」「She's A Rainbow」「Far Away Eyes」「Crazy Mama」などが選から漏れている。いや逆に言えば、ネタはまだまだ尽きない、ということなのかもしれない。そこらへんの曲は「次のツアー」のライヴアルバムに収められることを期待しよう!
■ Who's Chuck?
チャック・リーベル・・・・・ローリング・ストーンズのサポート・キーボーディストで、89年以来彼らのツアーには欠かせない存在となっている。なおかつこの人、サポートでありながら、実はミックとともにストーンズの音楽的全権を握っているのである。ツアーのリハーサルで主導権を握っていたのも、その日のセットリストを決めるのも、バンドにカウントを出すのもこの人だ。前回のVoodoo Lounge Tourではやたらとマニアックな過去の曲がセットに組まれていたが、そのほとんどがピアノをメインにフィーチャーした曲である、ということは意外と知られていないかもしれない。「Rocks Off」「Monkey Man」「Heartbreaker」「Dead Flowers」「Let It Bleed」などはその代表例だし、それら長年ライヴで演奏されてこなかった曲は往年のファンのみならず、自分のようなストーンズ入門者も狂喜乱舞させた。 ■ Chuck on Steel Wheels Tour しかしこの人のキーボーディングが、全てのファンが望んでいるものかと言われると、「?」である。特にストーンズ復活ツアーとなった89〜90年の「Steel Wheels Tour」では、「キーボードの音がでかくて、キースのギターが聞こえない!!」といった非難の声を多く耳にした。実際、当時のフィルムや音源を紐解いてみると特に「Midnight Rambler」や「Tumblin' Dice」「Brown Sugar」といった、キースのギターがメインとなるべき曲では、キーボードの音がかなり邪険ですらある。なおかつにこのツアーでは他にもう一人ツアーキーボーディストが同行しており、ほんとにストリングスで武装したスタジアムショーを繰り広げていたのである、当時のストーンズは。 ■ Chuck on Voodoo Lounge Tour 前述したVoodoo Lounge Tourではそのキーボーディストもチャック一人だけになり、音色もピアノとハモンドをメインにして使うなど、キースとロニーのギターを全面にフィーチャーするためのかなりのシェイプアップが行われた。しかし彼のキーボードが効果的であったか、と言われると再び「?」である。「Rocks Off」のピアノはかなりかったるいし、「I Go Wild」ではカウントを出している上にキーボードの音は分厚すぎるし、「Heartbreaker」も音がでかすぎてキースとロニーのギターの音が聞こえない。この辺はミックの意図なのかも知れないが、ファンは下手でもいいからキースとロニーのギターが聴きたいはずなのである。チャックのキーボードはうまいんだけど、物足りない。物足りないんだけど、音はでかい。 ■ Chuck on Bridges To Babylon Tour そして去年、今年のBridges To Babylon Tourではどうだったかというと、もちろん自分は実際のライヴ1回とこの「No Security」からしか判断できないのだけれど、とにかくチャックのキーボードが抑制されていたという印象を持っている。実際のライヴを思い出してみると、チャックのキーボードプレイがメインにフィーチャーされていたのは「Let's Spend The Night Together」ぐらいだったと記憶しているのだけれど、むしろこの曲はオリジナルでもピアノがメインだった、というかはっきり言ってライヴではチャックのピアノと同じかそれ以上の音量でキースのギターも鳴っていた。そしてこの「No Security」でもチャックのピアノ、キーボードプレイは「Saint Of Me」「Waiting On A Friend」などでかなり聴かれるのだけれど、なんかそれらは必然として鳴っている、というかなしじゃまずい、そんな感じである。以前だったらキースとロニーのギターの隙間を埋めるためにかなりキーボードが入れられたであろう「Sister Morphine」「Live With Me」「Flip The Switch」といったチューンでのそれは逆に非常に抑制がかっている。そしてその結果として必然的に音が大きくなっているロニーのギターは、そのキーボードのサポートがないためかかなり一生懸命。やればあんたもまだまだ出来るじゃん!といった感じである。 いやもちろん今でもライヴの総指揮を執っているのはチャックであろうし、そしてそれを許しているのはミックであり、もちろんストーンズのメンバー各人でもある。しかしチャック自身がストーンズのグルーヴにおける自分のキーボードの役割というものを認識したこと、そしてフロントのミックとメンバー各自が、ファンの求めているストーンズの姿というものを正しく捕らえ直したということによって、以前の産業ロック然としたストーンズからの脱却を促し、そしてファンだけではなく全ギターロックファンが求める生身のストーンズ象を捕らえた「No Security」へと繋がっていったのではないだろうか。この「No Security」を素晴らしいものにしている鍵、それは実はチャック・リーベルの「抑制された」キーボード、それ自身なのである。
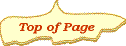
Last updated: 10/23/98 | |||||||||||||||||||||||||||