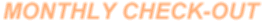 - March 1999 (2) -
- March 1999 (2) -
| Peasants, Pigs & Astronauts | Kula Shaker |
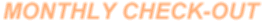 - March 1999 (2) -
- March 1999 (2) -
|
 デビューアルバム「K」を聴いたとき、「こりゃあやっつけ仕事で完成させたな」、
というイメージをまず持った。エスニック調の曲でのアレンジがかなり絞り込まれた凝った作りだったのに対して、特に「Grateful When You Are Dead」や「303」といったハードロック調の曲はどうも1,2日ぐらいでさささっと作ってしまったような印象が強かった。 とにかく限りなく3コードに近い曲構成、やたらと多用されるブレイク、アンプに直結のギターカッティング、ブルースペンタ一発弾きのソロとオブリ、そしてそれらの音をボーンと鳴らして、はい完成! みたいな。 やたらとギターの音が強調された不安定なミックスの仕方もどうにも気になって仕方がなかったのだが、早い話、自分がファット・ボーイ・スリムを初めて聴いたときの感覚に似ていて、「こりゃあずるすぎる!! 踊れて当然じゃん!!」というダイナミクスに溢れたツボ押しまくりの曲構成には本当にビックリしたし、なんだかちょっと複雑な気持ちにもなった。やっつけ仕事のくせになんなのこれ?!という感じだろうか。
デビューアルバム「K」を聴いたとき、「こりゃあやっつけ仕事で完成させたな」、
というイメージをまず持った。エスニック調の曲でのアレンジがかなり絞り込まれた凝った作りだったのに対して、特に「Grateful When You Are Dead」や「303」といったハードロック調の曲はどうも1,2日ぐらいでさささっと作ってしまったような印象が強かった。 とにかく限りなく3コードに近い曲構成、やたらと多用されるブレイク、アンプに直結のギターカッティング、ブルースペンタ一発弾きのソロとオブリ、そしてそれらの音をボーンと鳴らして、はい完成! みたいな。 やたらとギターの音が強調された不安定なミックスの仕方もどうにも気になって仕方がなかったのだが、早い話、自分がファット・ボーイ・スリムを初めて聴いたときの感覚に似ていて、「こりゃあずるすぎる!! 踊れて当然じゃん!!」というダイナミクスに溢れたツボ押しまくりの曲構成には本当にビックリしたし、なんだかちょっと複雑な気持ちにもなった。やっつけ仕事のくせになんなのこれ?!という感じだろうか。確かにそういった速いナンバーは即効性絶大。 特にクーラのハードチューンは凡庸なロックバンドが作るそれなんかよりもはるかに高レベルで安定しているから、彼等のハードな楽曲はロックファンのツボに見事にハマり、ダンスフロアで人々を踊り狂わせてしまう機能と魅力を持っている。 はっきり言ってクーラ・シェイカーはこんなロック然としたロック・ナンバーを作るのはお手の物なのだ。 簡単すぎる。 他のバンドとの桁違いの実力と才能。 だからこそ彼等はさくっとメジャーデビューできたのかもしれない。 そしてこのセカンドアルバムの制作に至り、そんな風に分かり易くて、彼等のポテンシャルからすれば安直とも言える方法で新しい作品を世に送り出すことはしなかった。 正直なところシングル「Hush」が出たあたりで、「次はこういうハードチューンばかりのアルバムになるのかなあ?」と思ったし、それをちょっと期待してみたりもした。 だが彼等はその期待を気持ちいいまでに裏切ってくれた。というか自分が観た97年2月のライヴで新曲として披露されていた「For This Love」という曲が、まさにこの「Shower Your Love」や「Great Hosannah」のような穏やかなポップチューンだったから、その時点でこの展開が 読めて当然だったのかもしれない。 しかしまさかインド趣味がこれまで深く表現されようとは思ってもみなかったが、つまるところ、彼等はインド音楽に対して至極本気だということだ。 仮にここで「Hey Dude」を10曲用意してまっとうなロックアルバムを作っていたら、「いったいあのインド趣味はなんだったの?」という疑念をこちら側に抱かせたことであろう。 つまりクリスピアンの頭の中ではデビューの頃からずっとインド音楽に対しては本気で付き合うつもりだったに違いない。 ビートルズのように、インド文化といい加減な付き合い方をしていないのだクリスピアンは(・・・この点で、自分のインド人の友達の中でも、ビートルズを嫌う人達が結構多い。) 彼等のインド趣味を笑うことは、間接的にインド人とインド文化を笑うのも同然である(・・・日本文化を一生懸命に学ぶ外国人を考えれば分かりやすい)。 8ビートのロックンロールの頂点に簡単に行きついてしまったクーラ・シェイカーが、次なる新たなるグルーヴを求めて他なる音楽、この場合インド音楽にたどり着いたのは当然の結果であろう。 そして、自分が観たアメリカでの3度のライヴからも、このインド風楽曲へのより一層の傾倒は必然的だったと言える。なにせそのライヴの中では、前作「K」からのナンバーの中では「Govinda」や「Tattva」といったインド風楽曲の盛り上がりが想像以上に良かったのだ。「Hey Dude」では静観していた客が、「Govinda」ではダイヴやモッシュまでしてしまうのだから、次の方向性はこの時点で決まったようなものであろう。 よりワールドワイドなサクセスのためのアメリカのマーケット戦略。それはアメリカ人の剛腕プロデューサー、ジョージ・ドラキュリアスとリック・ルービンの起用となって表れた。しかしアルバム制作の過程で彼等とは訣別。そして最終的なプロデュースはキッス、アリス・クーパーなども手がけたボブ・エズリンに託されることになる。 すなわちクーラ・シェイカーが最も得意とし、なおかつ彼等のオーディエンスが切実に求める「新しいグルーヴ」のイメージを、レコードという形でパッケージングすることが出来る有能なスタッフを見つけるために、約2年半という月日を要したとも言えるのではなかろうか。ファーストアルバム制作の時点では、彼等にはそのための時間も金も実績もなかったし、オーディエンスが真に求める音というものも測りかねていた。 とにかく早くレコードを作って売らなければならなかった初期段階を経て、こうしてようやく彼等の本当にやりたいことが表現され始めたセカンドアルバム。 「S.O.S.」や「Great Hosannah」といったポップチューンではストイックなまでにアレンジが絞り込まれ、前作ではせっぱ詰まった曲の癒しとして機能していた印象のあるインド風スローチューンが、ここでは違和感なく曲間に収まり、トータルアルバムとしてのレベルを保つことに高い貢献をしている。 あとはこれらをいかにしてライヴ空間で表現するか、ファーストアルバムの曲といかにバランスさせていくかが問題であろう。しかし最近のマンサンがそうであったように、その辺の壁は案外軽くクリアーしてくれそうな気がするのは自分だけではないと思う。 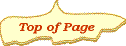
Last updated: 3/6/99 |