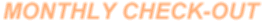 - July 1999 (1) -
- July 1999 (1) -
| Significant Other | Limp Bizkit |
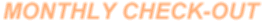 - July 1999 (1) -
- July 1999 (1) -
|
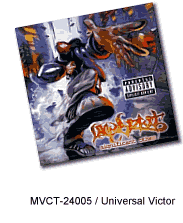 この衝撃的な瞬間を当分忘れることはないだろう.
この衝撃的な瞬間を当分忘れることはないだろう.フジロックの会場の下見を兼ねたノースオフ会中,苗場の会場周辺を車で走っていたときの出来事だった.それまでリンプ・ビズキット(以下リンプ)のことに対して殆ど知識がない自分に対して,同乗者2名が歌舞伎町のポン引きの如く「ダンナ,いいものありまっせ.ヘヘヘ」とニヤニヤしながら車のカーステレオにCDを入れた.(注:はて、誰でしょう、この2名って?(笑) by Kats)そこでかかったのは80年代に大ヒットしたジョージ・マイケルの "Faith" のカヴァーだった.そう,リンプのファースト・アルバム "Three Dollar Bill, Y'all $" に収録されていたあの曲である.最初は「原曲とコード進行違うで〜」とか「ベーシストが5弦ベース使ってまんな」とか,どうでもいいことをブツブツとほざいていたが,その直後「I gotta have faith〜〜〜〜!!!!」....とてつもない叫びが脳天を直撃し,続いて重低音が体を揺さぶった.それで全ては決まった. 彼らの音楽は漫才のボケとツッコミを強く連想させるなー,とその後つくづく感じた.例えば,抑えめの曲調にてブレイクが入り,そこで号令がかかったかの如くボーカルが叫ぶ.それにツッコミを入れるかの如く重々しい楽器陣が応え,それにボーカルは更なるツッコミを加えるべく4文字言葉を繰り返す... "Faith" はこれの典型例で,曲が進むにつれ少しずつこちらの心をつかんだ後に重々しい音が入り,そして突然ブレイクが入った後 "Get the fuck off!!!" と叫ばれた日には... もう暴れるしかない. このような衝撃的なリンプとの出会いを果たした後,ちょうど最適なタイミングで2枚目のアルバム,"Significant Other" が発売された.楽器陣とボーカルとの間のインタープレイ,という形式はすでに1枚目にて確立されていたわけであるが,本作の内容といったら...ボケとツッコミのしまくりで,これがもう大変なの大変じゃないっちゅうの. このアルバムを詳しく聞くとドラム vs. 弦楽器,ベース vs. ギター,ギター vs. ターンテーブル など,あらゆるボケとツッコミの関係が曲の中に忙しく織り込まれていて聴けば聴くほどに味が出る.まるでブラックホールかの如くリンプの世界へと吸い込まれていくところがオソロシイ. シングルカット曲 "Nookie" を例に挙げてみる.曲が始まりしばらくして歪んだギターとベースが重低音のリフを奏でるが,それにヘンなギターの高音との組み合わせがからみ良い味を出す.さらに,この高音とドラムのスネアが微妙にからんだり離れたり,これがまた妙に掛け合いをしているようである.歌メロに入るとメインとバックの歌声がボケとツッコミを入れ合い,その裏ではベースと歪みを抑えたギターが漫才をやっている.そして サビで "I did it all for the nookie..." とボーカルが叫び始めギターとベースが全開となると,これらが一体となって絡み,想像を絶するカッコ良さへと突入する. その他でも,例えば6曲目 "I'm Broke" では,やはり同様の絶妙な楽器陣のからみ合い,具体的には弦楽器-ドラム-ボーカルの3組がボケとツッコミを演じている.9曲目 "9 teen 90 nine" あたりのターンテーブルもこれまた絶妙で,更なるテンションを見事に加えている.これはバンドとしてのまとまりの強さゆえなのか,それとも計算されたアンサンブルなのか... まあ細かい分析はやめよう.漫才なんて楽しんでナンボのモンだから. まあ,彼らもこの漫才的形式のみに固執している訳ではないだろうし,実際本作では1枚目にありえなかったような展開の曲が沢山入っている.しかし,芸人がシリアスな場面でもついついボケボケのギャグを飛ばしてしまうのと同じように,リンプの「ボケとツッコミ」は常に彼らの根底にあるものなのだろう. もし仮にリンプの音を未だに経験した人がいたとしたら,自分はそれを表現するべく,以下のように答えるだろう.「 "Master Of Puppets" の頃のメタリカのような重圧度,"Check Your Head" の頃のビースティ・ボーイズのようなラップの破壊感,やすきよコンビのボケとツッコミの応酬が加わりそれを倍像したようなもの」と.一体フジロックフェスティヴァル '99 ではどういうことになるだろうか.ぜひ若手芸人には彼らのステージを体験してほしいものである. (text by しげやん)
97年はレイジ。 98年はコーン。 そんで99年はリンプ。 これみんなフジロックに出た(出る)ヘビー系の目玉バンドであると共に その年を象徴した(する)バンド。 3者に共通するのはやっぱアドレナリンっていうか怒りだと思う。 でもそれにも色々違いが感じられる。 Rage Against The Machineには政治や体制に対するものとか 自分達の信念を主張するような、なんか正義みたいのを感じる。 校則の長髪禁止に反対する生徒達みたいな感じ。 「そんなんどうでもいいよ〜」って言ってる受験勉強命みたいな人もいるんだけど、「いや、こんな校則間違ってるよ」って断固反対しながら校門で帰らされてる長髪君。 KORNはもっとドロドロしたこの恨み絶対忘れないぞ系のある種怨念のような怒り。 そこにはもうホント衝動的に刺しちゃうような、これが俺の限界ギリギリですって手をプルプル震わせてるような感じ。 Limp Bizkitはなんかさっぱりとした突発的な怒り。 不機嫌な時にムカつくコトを言われていきなり切れるとか。 でも次の日にはもう忘れてるようなある意味健康的な怒り。 で、今回のリンプのニューアルバムもそこらへんは前作と同じだった。 でもノリノリ度がバックの演奏もフレッドの歌も含めてパワーアップしてる。 中には「NO SEX」とか今までになかったタイプの曲もあるけど基本はノリノリ。 「break stuff」、「i'm broke」や「9 teen 90 nine」みたいなバックの演奏とフレッドのシャウトがガシッと合体した感じの時なんてアムロ行きまーすって1人モッシュ始まっちゃうもの。 そんでフレッド歌ってて気持ち良いだろうなーって思う。 宇治白玉みたいな甘〜い感じの歌い方やメロディーから、ドスの効いた凄みのある声までいろんな感じのラップがノリノリの演奏に乗っかってる。 そんでサビでみんなで爆発する。 これは盛り上がらない方がおかしい。 それで今までと違う感じの「NO SEX」とかも非常にメロディアスで良い感じだし、ゲストの使い方も上手い気がする。 ちょっとノリノリを期待してる人はあんま聴かなそうな遅めの曲の「nobody like you」とかでゲスト2人も使えば聴かないわけにはいかないし。 それがまた凄い良いし。 そしてやっぱりみんなに「ありがとさん」て曲があって分かりやすいですこいつら。 健康的なノリノリで、女の子大好きで、そんでどっかバカで。 フジに行かない人は単独公演待ちということで、こんなノリノリのアルバム引っさげてのフジでは確実に大暴れするんだろうなぁ。 お客さんもボクも。 (text by Kowalski)
去年のフジロック'98では、「今年のフジロックで荒らしまくるのはガービッジとコーンでっせ!」と豪語していた自分だったけど、結局両方ともあの暑さで実力の半分も出せず・・・・と相成ってしまったわけだが、とにもかくにもコーンはその規格外の破壊力を随所に見せてくれたことは印象深かった。思えばその前の年のレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンといい、去年のコーンといい、アメリカ・ロサンゼルス出身のヘヴィロックバンドがその実力を皆に知らしめて、日本でも広く知られるようになったのは、フジロックの最大の功績ではないだろうか、とちょっと思ったりもしている。 そしてこのリンプ・ビズキットだけれども、フジロック前において、どういうわけだか前述の2バンドの時と比較のしようがないぐらい盛り上がりまくっている。 本国アメリカでの評価は最近までレイジ、コーン、トゥールらに比べてまだ2番煎じぐらいの感じだったけれど、そんなアメリカでもこのニューアルバムが初登場ナンバー1をかっさらってしまったぐらい、とてつもない盛り上がりを見せている。 これはなんだかちょうど10年前ぐらいに、「LAメタル」と称してガンズ、モトリー、スキッド・ロウ、ポイズンあたりが盛り上がりを見せていた頃の状況とも非常に似ている感じがする。まあ、レイジがガンズ、コーンがモトリーあたりだとするならば、リンプがスキッド・ロウって感じかなあ。そういやなんかこの売れ具合といい、アルバムのざらついた感触といい、スキッド・ロウの「スレイヴ・トゥ・ザ・グラインド」に似てないこともないなあ。 やっぱあのアルバムも全米ナンバー1になったし。(やや遠い目) そういやスキッド・ロウのボーカリスト、セバスチャン・バックは、ちょうど去年のフジロック時期に日本に滞在していて、西新宿の某ブート屋でベックと遭遇した、なんて話もあったっけ・・・。 いやそんなことはともかく、あのLAメタル時期に登場したバンドのキーワードは「ブルース」だった。シンデレラもポイズンもガンズも「ブルース」に大きく影響され、結構ダウン・トゥ・アースな音楽をやっていた。 ギターのフレーズなんてブルーススケールばりばりだったし。 しかし一方のレイジ、コーン、リンプあたりの共通項といえば、間違いなくに「ヒップホップ」であろう。 「ブルース」も「ヒップホップ」もそうだが、黒人音楽からの影響をロックに反映させることは今に始まったことではなくて、その創世記から脈々と続いてきた「パクリ」技術のひとつでもある。 そしてその「パクリ」は必ずアメリカの白人キッズに熱狂的に受け入れられて今日までロックという音楽は存命してきたんだと思う。 でも歴史の節目節目のいずれの時もそうだったけれど、ただの「パクリ」と簡単に片付けられるものでもなく、それはそれで連中も苦労しているってとこが、日本の某バンドとはかなり違うところである。 ヒップホップのリズム感とライム感、そしてこれまでのポップミュージックの枠を完全に逸脱した言語感とを、ギターロックにいかに持ちこむか、という点において先人はかなり苦労なされた。 エアロスミスもそう。レッド・ホット・チリ・ペッパーズもそう。 結果みんな傷つき、ボロボロになるほど頑張った。 レイジだって、ヒップホップの感触をギターから発するためにトム・モレロはギターオタクにならざるを得なかったし、コーンだって7弦ギターなんていうぶっとい代物をわざわざ使用しているし、オクターブ奏法(同じ音階をオクターブ上と下の両方を一度に鳴らす奏法)なんていうジャズなプレイがこの「ヒップホップ奏法」において見直されたりもした。 歌詞だって「アイ・ラヴ・ユー・ベイベー〜〜♪」と歌っていればとりあえずなんとかなっていたものが、ヒップホップ唄法ではそれだけじゃどうにもならなくって、必然的に色々と考えなくちゃならなくなったし、その長い歌詞を全部覚えなくちゃだし、ステージではヒップホップってやっぱり動きが重要だから、ギター抱えながらあっち行きこっち行きしなくちゃならないわけだし、それでもやっぱり統一感ってのが必要だから、メンバー同士の関係性がうまくいってないととてもやれないものだし、ファッションにだって色々と気を遣わないといまどきのキッズは相手にもしてくれないし、単なるヒップホッパー気取りでふらふらしてたってただ単純に阿呆に見えるだけだし、それを考えれば、ギターをちょっと練習してライトハンド奏法でもマスターして客に見せびらかすか、カントリーバンドで決まりきったスタイルで毎日同じことをやっていたほうがはるかに楽チンなのである。結構すでに研究され尽くしていた「ブルース」ってのをキーワードにしていたLAメタル期のバンドよりも大変だと思う。日本で言えば演歌をポップミュージックに取りこんだ北島三郎とか五木ひろしぐらいすごいことだと思う。(・・・違うか?) そんなご苦労が積み重なったバンドなのであるから、いろんなバンドが出るフェスティバルで盛り上げ上手なのは当たり前なのだと思う。ちょっと大袈裟に言えば、音楽界において選ばれし才能のみが演ることを許されるロックンロールの形だとも思う。 そしてこの「Significant Other」はこれまた完璧なとてつもないアルバムである。 恐らく自分にとって年間ナンバーワンのアルバムである。 ヘヴィだった90年代の最後を飾るにふさわしい、この時代を代表する作品だと思う。 まだビジュアルで観たこともないのにここまで思わせる作品は本当に稀だ。 あとは今年のフジロックにおいて、次の10年への夢をも見せてくれるかどうか、それをこの目で確かめて来たい。 ケミカル・ブラザーズやアタリ・ティーンエイジ・ライオットに負けるな。 ZZ TOPとともに、アメリカにまたロックンロールを奪還せよ。 (text by Kats)
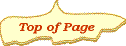
or Jun Shigemura or Katsuhiro Ishizaki. Last updated: 7/23/99 |