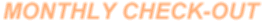 - September 1998 -
- September 1998 -
| Six | Mansun |
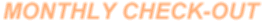 - September 1998 -
- September 1998 -
|
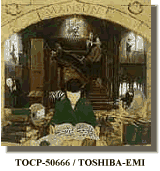
「この〜、ひねくれ者!!」。・・・思わずこう言いたくなってしまうほどのマンサン、セカンドアルバム。ポール・ドレイパーは、「昨年のツアーで、ギター・サウンドの荒々しさを発見した。」と言ったらしいが、だからといって昨今のそこら辺のバンドにありがちな、ディストーションペダルを思いっきり踏み込み、闇雲にパワーコードをかき鳴らす、なんていうパターンには絶対に陥らない。なおかつこれが彼らにとってセールス面でも勝負となるセカンドアルバムだからして、レコード会社としても「売れ線」チューン満載のアルバムを望んでいたはずだ。ところがそんなキャッチーな曲は一曲たりとも見あたらない。ラジオでのエアプレイなど根本的に頭にないかのように、このアルバムは3分以下の極端に短い曲と、6分以上にもわたる極端に長い曲群とで構成されているのである。そして中心となるべきポール・ドレイパーの声はといえば、ややノイズがかったミックスでそれすらも全面に押し出されていない。かと言ってリズム隊ビシバシのダンスアルバムというのでも決してない。オアシスやステレオフォニックスなどのコンパクトなポップアルバムに耳慣れているリスナー諸氏にとっては、一聴すると「なんじゃこりゃ?」と思われかねないアルバムである。 ところが、ところがである。およそ聴き始めて3回目ぐらいからこのアルバムの印象は一変する。曲ごとにある情景がおぼろげながら浮かんでくるのだ。真ん中にいるのは演奏しているマンサンのメンバー4人だ。しかしその背景が曲ごとに変化する。時には豪華絢爛なオペラハウスだったり、時には地平線であったり、時にはお花畑だったり、時には都市の喧騒に疲れた労働者達だったりもする。その情景の変化は、急速にやってくるものではなく、ぼんやりと、前の情景とオーヴァーラップしながら我々リスナーの眼前に拡がってゆくのだ。 そしてある時ふっと気が付く。「このバンドって4人だったよな」。そうなのだ。これだけの情景をマンサンはギターとベースとドラムだけで作り上げてしまったのである。中でもやっぱりギター。ここで始めて「ギター・サウンドの荒々しさを発見した」というポール・ドレイパーの言葉を思い出すのである。 曲の流れを崩さないように、始まりはゆったりと流麗なフレーズを組み立てて前後のオーヴァーラップイメージを作り出す。そして時に中盤で猛然と荒々しいトーンでその背景を完全に塗り替える。独りよがりのギターソロなど皆無。そんなものが必要ないほどチャドとポールのギター音の密度は濃く、華やかで、なおかつ色がある。テクニックといったレベルを超越したギターアルバムここに極まれり、といった感を持たざるを得ない。 一見すると凡庸な感性ではとても理解できない、そんなトータルアルバムを作ってしまったこのマンサン。だがしかしこのアルバムは、ひょっとして今後のギターロックの方向性を180度変えてしまわないとも言い切れない。いやこの盤の魅力と先見性に取り憑かれてしまった今、その可能性に賭けてみたい気もする。もうオアシスのフォロワーや、ニルヴァーナのコピーバンドはたくさんだ。よってこのアルバムは絶対に爆発的に売れなければならない。それもイギリス国内のみ、なんていうレベルであってはいけない。世界中の音楽マーケット、特にその中心のアメリカ市場で徹底的に売れなければならないのだ。そうじゃないと何も変わらないし、何も変えられない。去年の夏、イギリスでのフェスへの出演を終えたその日にアメリカ入りし、翌日から怒濤の全米ツアーに入ったマンサンだ。その辺のことはよく分かっているに違いない。これらのことについては来月のMonthly Checkoutでも取り上げていきたいと思っている。 とにかくこのアルバムを手に入れる。手に入れたら徹底的に聴き込む。そしてそこからギターロックの新たな地平が見えるのは間違いない。

Last updated: 8/27/98 |