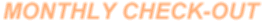 - December 1998 (*) -
- December 1998 (*) -
| On Stage | Ou Yang Fei Fei |
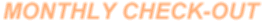 - December 1998 (*) -
- December 1998 (*) -
|
 * 注意 --- まじめに読まないでください。
* 注意 --- まじめに読まないでください。
大ヒットシングル「ラヴ・イズ・オーヴァー」で日本国民ならずとも世界の音楽ファンを熱狂させたのがこの欧陽菲菲だ。そしてこの「欧陽菲菲・オン・ステージ」は、そんな彼女による1972年大阪での来日1周年記念ギグを収録した実に画期的なライヴアルバムである。一般の人々が何と言おうが、仮にいらないということで忘年会の賞品にされようが、私はこれこそまさに徹頭徹尾のロックンロールアルバムと言い切りたいと思う。欧陽菲菲は実にロック的な精神性と時代性そして音楽性を併せ持った希有の中国人音楽アーティストだったのである。
1972年ときて、そしてまたライヴアルバムときて頭にぴんと来た方は少なくないだろう。そう、日本でライヴレコーディングされたあの普及の名盤、ディープ・パープルの「ライヴ・イン・ジャパン」が発売され、世の中を席巻していたあの年なのである。欧陽菲菲はこのアルバムでつまりそういった時代的色合いをもまるで自分のものとして完全に消化した上でそれをさらなる高みへと発展させありのままの自分として表現していっている。ジャニス・ジョップリンですら完全には成し遂げられなかったこの音楽的境地を、この欧陽菲菲はわずか来日1年で成し遂げてしまったのである。これはまさに驚異としか言いようがない。 さらに、72年と言えばグラムロックやハードロックが全盛であり、なおかつ黒人と白人とがファンクというフィルターを通して異種配合を進めていたときでもある。かつ有能なミュージシャン達の多くはさらなる「ロックなものとしての」音楽的刺激を求めて、あるものはジャマイカへ、あるものはインドへ、またあるものはモロッコへとその音楽的行動範囲を飛躍的に広めていたそんな時代だ。しかしこの欧陽菲菲の作品から顕著に見られるように、それら音楽シーンから遠く離れているように一見みえた東アジアの島国でも、ここまで時代を映し、そして時代と対峙する、そんな素晴らしいロックアルバムが発表されていたとはまさに驚愕に値する出来事であり、日本、いやアジア音楽界全体の金字塔として燦然とした輝きをもち、かつその輝きを失わない、そんな真摯なピュアネスと普遍のポインセチアを1枚のレコードに無理なく散りばめた見事な作品であるのだ。
ここで聴かれる欧陽菲菲の音楽の形態はいわゆる「ブラスロック」というやつである。ちょうどその数年前の60年代末から、シカゴ、ブラッド、スウェット&ティアーズといったアメリカのロックバンドがホーンセクションを大胆にフィーチャーして世界のロックファンの度肝を抜くことに成功していた。いまやロックにブラスなんて当たり前の事実として認識されているが、当時はこれこそ新しいアート提供のフォーマットとしてみな試行錯誤を繰り返していたのだ。そしてそんな最中におけるこのアルバムの登場である。私はまさにここに「ブラスロックの完成形」というものを見たという印象を禁じ得ない。なおかつそれが中国人女性によって達成されたという事実認識に基づき、イエローミュージックにおける新たな歴史の扉が、この1枚のアルバムによって開かれたような、そんな印象すらある。
そしてこれは内容解説ででも語るが、欧陽菲菲の音楽性はこのブラスロックにとどまらず、現在のさらに多様化した音楽ジャンルそれそのものをすでに彼女の音楽のうちに内包しているかのような、多彩でかつ先見性のある作品の作りには本当に圧倒されてしまう。これはまるでヴェルヴェット・アンダーグラウンドやフランク・ザッパの初期の作品が、あまりにも先進的でアーティスティックなものだったため、その評価は後年までに持ち越されたことと似ているが、この欧陽菲菲の場合にはそれら以上に先進的なアートをここで提供しているため、いまだに評価されるに至っていない。まさにこれこそ21世紀のFuture Musicと呼ぶのにふさわしい新型アートが提供された世界でも初めてのケースであろう。なおかつライヴアルバムとしての新しい側面と方向性を垣間見ることができ、そしてそんな様々な意味での「息吹」と「ライヴ」感がアルバム1枚からふつふつと感じられる強靱なパワーを持った作品がこの「オン・ステージ」なのだ。今この時代だからこそ評価されるべき、そんな決定的、世紀末的、かつ確信犯的な超名盤がここに再び息を吹き返したのである。
まず内容を検証する前に、何と言っても司会進行が「宮尾すすむ」だという事実がその内容の充実ぶりを音を実際に聴かずして知らしめてくれる。ライヴアルバムに司会者の語りが入る、という前代未聞のこの録音形式。これは未来のライヴアルバムの形を模索せんという意識の現れであろうし、それが録音からおよそ25年以上の月日を経てようやく時代とリンクし始めてきたかのような、そんな印象すらもある。なにせ「宮尾すすむ」である。この人がいなければ「宮尾すすむと日本の社長」は誕生しなかったのだ。まさにロックである。初期衝動に突き動かされ自分自身を貫き通す、これをロックと呼ばずして、一体全体何をロックと呼べばよいのだろうか。
またその宮尾すすむのカリスマティックな佇まいに突き動かされた欧陽菲菲の語りは、辿々しい日本語でありながら、そこにはミック・ジャガー的なユーモアのセンスと、より洗練されたヘビーメタルのような様式美のようなものを感じる。これはオアシスのリアムとノエルとは対極であるように見えながら、実はそれを反面教師として多大な影響を与えたことはここで語るべくもない。
ホーンセクションによる大仰なイントロで始まる「雨の御堂筋」がいきなり我々の度肝を抜く。そしてそのタイトなテンションの高さを保ったまま欧陽菲菲の歌へとなだれ込む様には、バンド、そして彼女自身の演奏能力の高さ、そしてこれからの時代を自ら築かんとせんとする意思表明とを高らかに聴衆の前に誇示している。まさにこれはディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」にも勝るとも劣らないすばらしい完成度を誇る名曲である。
そして続いていきなり誰も知らない中国民謡「何日君再来 〜 夜来香」をコンサートの序盤で披露するなどというこの常軌を逸脱したこのセットリスト。しかし動と静のダイナミクスがうまくブレンドされた現代的な作りには、あのニルヴァーナ的な触感を我々に強く印象づける。しかしこの音がニルヴァーナの登場する20年も前にすでにここで完成されていたという事実にはまったくもって驚かされる。いやらしい卑猥なトランペットの響きには、密かなる望郷の思いと、そこで繰り広げられた愛の思い出とが密かに綴られているのであろう。 ビートルズの「抱きしめたい」とローリング・ストーンズの「ハートブレイカー」とを足してそこにキャロル・キングのぬくもりを加えたような、そんなセンスの良さが全編に渡って聴かれる「花嫁」。ロックンロールの美味しい部分をうまくつなぎ合わせるノーマン・クック的なセンスのよさには、改めて脱帽させられる。 一方、ジャズとスカとR&Bをミックスしたような3連系のナンバーが「恋の追跡」。この曲では既存の音楽ジャンルではまったく捕らえきれない彼女の類い希なき音楽的才能が如何なく発揮されており、それはさながら今のビョークのような存在感を印象づけてくれる。後半のホーンセクションによる圧倒的なソロコーナーではメンバーのプレイヤビリティーをイヤというほど見せつけられるが、しかし決してうっとうしいわけではなく、それがまったく持って必然として鳴らされているところが欧陽菲菲のディレクションの素晴らしいところなのである。 クラウドベリー・ジャムのようなスウェーデン・ポップを彷彿させてくれる「雨のエアポート」。そしてビートルズの「ドライヴ・マイ・カー」のような「夜汽車」、そして最後の「Happy Beat」を終えてアンコールもなしにショーを終えるその姿は、在りし日のストーン・ローゼズを思い出させてくれる。つまりすでにこのときから、来る90年代の「オーディエンスの時代」を予感させる構成で欧陽菲菲はショーを行っていたのである。異境の地で歌う彼女が、「自分は自分自身でなければならない」的なメンタリティーを自然に獲得していったのは容易に想像できる。そしてオアシスやローゼズにはない高いプレイヤビリティーとジャンルの枠を取っ払った圧倒的な「音楽」「グルーヴ」としての欧陽菲菲の存在感。そしてボーダーレスの時代をいち早くつかんだまさに未来の理想郷作りへ向けての画期的行動。来る21世紀に向けてのヒントはこの辺に隠されているのかもしれない。
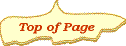
Page maintained by: Katsuhiro Ishizaki . Last updated: 12/14/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||