 | ||
|---|---|---|
| Rage Against The Machine | 疲れちゃいなかった |  |
 | ||
■ Reading Festival - 8/27/00
Last updated: 10/ 8/ 00
★ Battle of Reading I ・・・・ ストリート・ファイティング・マン !!!
 「Calm Like A Bomb」が終わると、バンドの4人が1箇所に集まって何やら打ち合わせが始まった。 ザックがトム・モレロに対して耳打ちし、トムはブラッドに対して何か指示を与えている。 そんな風にしてしばしの時が流れた後、いきなりまったく聴いたことのないフレーズを弾き始めたトム・モレロ。続くザックがヒップホップ的なライムでもってそこに闘争的な詩を乗せていく。「新曲か? 未発表曲か?」などと思いながらみんな聴いている様子で、この時だけは波打つオーディエンスも平穏そのものに見えた。
「Calm Like A Bomb」が終わると、バンドの4人が1箇所に集まって何やら打ち合わせが始まった。 ザックがトム・モレロに対して耳打ちし、トムはブラッドに対して何か指示を与えている。 そんな風にしてしばしの時が流れた後、いきなりまったく聴いたことのないフレーズを弾き始めたトム・モレロ。続くザックがヒップホップ的なライムでもってそこに闘争的な詩を乗せていく。「新曲か? 未発表曲か?」などと思いながらみんな聴いている様子で、この時だけは波打つオーディエンスも平穏そのものに見えた。
ノイズに埋もれて聞き取りにくいザックの声。 しかし最後の方になって聞いたことのあるフレーズが目の前のスピーカーから耳に飛び込んできた。「London town !!」・・・・・・あれ?? ひょっとして・・・・・・。
そして最後の方にザックが連呼したこの言葉がダメを押す。「Street fighting man !! Street fighting man!! Street fighting maaaaaaan !!!」
「あ!! ストーンズのストリート・ファイティング・マンじゃん!!」・・・・・独り呟く日本人。「すげえーーー!! どうなってんだーーーー!!」と叫ぶ間もなく「Street Fighting Man」は終了。すぐに優美なアルペジオフレーズから「Sleep Now In The Fire」に雪崩れ込んでいった。
確かにザックが歌っていたはずの「Street Fighting Man」。でもこの曲をカバーした、なんて話は聞いたことがないし、レイジがストーンズを、ってのも全然イメージ湧かないし、曲調も全く違うし、歌詞も途中まで全然違っていたから、自分としてもちょっと半信半疑の状態。 まあそれでも頭の中で80%ぐらいの確信は得ていたのだが、「ストリート・ファイティング・マン演ったよな??」などと聞ける友人もおらず、独り悶々としながら飛行機に乗って日本に帰ってきた。
フェス後程なくして購入したロッキング・オン10月号。そのHOTNEWS欄にこんなんことが書いてあり、自分の確信は95%ぐらいに上昇する。「この年末にライヴアルバムのリリースを予定しているRATMだが、そのアルバムには何曲かカヴァー曲が収録される可能性があるとのこと。(中略)MC5の"キック・アウト・ザ・ジャムス"、(中略)ローリング・ストーンズの"ストリート・ファイティング・マン"、ディーヴォの"ビューティフル・ワールド"などの候補が挙がっており・・・・」
さらにレイジのオフィシャル・サイトの掲示板などを丹念に見てみると、やはり耳慣れないこのStreet Fighting Manのことがちょっとだけ話題になっていた。よってこの曲が演奏されたという自分の確信はほぼ100%になった。
なおかつ同ロッキング・オン誌には、「まったく新しいレイジの楽曲に色々な人達の歌詞を使っている。(要旨)」ともあり、曲調も歌詞もかなり違って聴こえたのはそのためだったんだ、ってことで目からウロコ。ライヴアルバムに収録されるカバーということだから、このライヴでの演奏がそのままパッケージングされる可能性もなきにしもあらずだな。
「貧しい人間は、ロックンロールバンドで歌うこと以外、どうすりゃいいんだ? 眠ったようなロンドンの街には外で闘う人間のための場所なんかありゃしないんだから。」と歌われる「Street Fighting Man」。いかにもレイジがピックアップして然るべき歌詞。なおかつまさにそんなロンドンにおけるフェスティバルでの演奏。自分たちの楽曲を差し置いてまでプレイされた理由はここにある。
個人的にもストーンズといやあ言わずもがな自分にとって最も大事なバンドだし、「ロンドン」とくればサビの歌詞が口を突いて出るほどこの「Street Fighting Man」は格別なナンバーだ。レイジがストーンズを演奏した!という意外性もさることながら、この曲を、日本ではなく、はるばる飛んできたここロンドンで聞くチャンスを奇跡的に得たことが、レディングフェスに来て良かった!と思えた唯一の瞬間であった。
★ Battle of Reading II ・・・・ 腹の底まで響く重低音
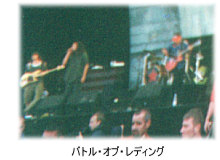 驚くべきことに、フェスのトリはこのレイジではなかったのだ。ステレオフォニックスがこの3日目のトリで、その前がプラシーボ。そしてさらにその前がスリップノットで、つまりレイジはラインナップのちょうど真ん中辺りにエントリーされていたのである。フェスのトリを務めることに嫌悪感を抱くレイジらしいといえばらしいのだが、真っ昼間に見るレイジというのも新鮮でいいなあ、と思ったりもした。
驚くべきことに、フェスのトリはこのレイジではなかったのだ。ステレオフォニックスがこの3日目のトリで、その前がプラシーボ。そしてさらにその前がスリップノットで、つまりレイジはラインナップのちょうど真ん中辺りにエントリーされていたのである。フェスのトリを務めることに嫌悪感を抱くレイジらしいといえばらしいのだが、真っ昼間に見るレイジというのも新鮮でいいなあ、と思ったりもした。
ステージ開始時間は日がまだまだ高い17:40。その前のBlink182が「次はレイジだ!!みんな楽しんでくれ!!でもあと2曲だけ演らしてくれ!」と言ってブーイングされていたことから分かるように、このライヴへのみんなの期待度は思いっきり高まっていた。「Battle Of Reading」と書かれた垂れ幕がステージ後方に掛けられるただけでものすごい歓声が挙がる。レッチリの「Give It Away」がかかっただけで歌ってしまう。そしてそんな中で、自分は始まる前から思いっきりステージ前方に陣取ることにした。なんつったってこの日はレイジを観に来たようなもんだったから。
何気なくバンドが登場。6月の幕張初日では聞けなかった「We're Rage Against The Machine from Los Angeles, California !!」というザックの一声にまず鳥肌。 そして続く1曲目は「Testify」だ。サビの部分で周りが派手にジャンプし始めるのに乗じて、どんどん前の方に突き進んでいく自分。 しかしすごい!! 何が凄いって、ベースとドラムの音が!! なんとも形容しにくいのだが、「ぼふっ!! ばふっ!!」といった感じのバスドラの音に覆い被さるベースライン。 こんなに音圧がものすごいライヴはこれが初めてだ。 でもそれでいて全然耳障りじゃないところが大変素晴らしい。
頭上をクルクル回るテレビカメラに手を振りながら、モッシュの輪の中に自然と溶け込んでいった「Guerrilla Radio」。ここでさらに前方へ進んでいくとあっという間に最前間近。「なんだぁ、レイジも大した事ないじゃん!」と余裕ぶっこいていると、ザックの曲紹介から「Bullet In The Head」へ。そしてここで思い出すあのビデオの映像。 そう、ディスクレビューの名盤紹介でも取り扱った「RATM Video」に収められているレディング'96の映像だ。その中でものすごい盛り上がり&ジャンプを見せ付け、レディングといやあこれでしょ!って感じで自分に強烈なイメージを残していた曲がこの「Bullet In The Head」だった。とうとう自分もそれを体験できるのかぁ〜、と感慨に耽っていたら前方のセキュリティーからコップに入った水が飛んできて頭にバシャ!!・・・・思いっきり水を浴びて周りの失笑を買う。 後ろの方はすごいことになってんのかなあ、などという想像を巡らせながら、竹の子のように湧き出てくるダイバーを事もなげにさばいていく。
「Kick Out The Jams」から「Bulls On Parade」に至る過程は完全にメドレー形式。この頃にはもう完全に超大密集状態に陥っており、あと1メートルぐらいで最前列なのに全く身動きが取れない。でも身動きがとれないからこそ、まったく動く必要もなく、かえってステージがきっちりよく見える(笑)。しかしクツ紐が完全に解けているんだけれど、屈むこともできないから、激しく動くと結構やばいかも。 さらにここにあるように、使い捨てカメラで写真を撮っていたのだが、あまりの窮屈にカメラ壊れる。現像したのを見てみると、殆どの写真にモヤがかかったような状態になっており、さらにピンぼけ。なおかつ写真自体がひしゃげていて、きちんと写っているものがほとんどない。
「Bombtrack」「Sleep Now In The Fire」と、数万人のオーディエンスがさらにヒートアップするにつれ、そんな彼らの最前線にある自分の周りはもう汗と水とで完全にビショビショ状態。上コップに入った水が回ってくるとむさぼりつくように飲むのだが、それを提供してくれているセキュリティもほんと大変そうだ。ダイバーを受け止め、気分の悪い人がいないか監視し、水を与え、倒れている人がいたら助けに飛び込む。ストレスを軽減させるために話し掛けたり、ジョークを言ったり、笑ってみたり・・・・。アーティストや主催者側のことばかり取り沙汰されるデンマークのロスキルドの悲劇だが、何人か亡くなったあの事件を目の前にせざるを得なかったセキュリティに対する風当たりも強くなってるんだろうなあ、などと違った視点からあの事件を捉えることができた。そんな中で彼らは本当によくやってるなあ、といった印象。すばらしい。「Know Your Enemy」では頭上を日本人の女の子ダイバーも飛んできて、目の前のセキュリティーはそれをしっかり受け止めてくれていた。
「Freedom」では途中からの展開が全く変わり、オリジナルにはない歌詞とフレーズが織り込まれている。大胆に変換したグルーヴに呑まれるオーディエンスを見てニヤリと笑うザック。ああ、これで終わりなのかなあ・・・・などと思っていたらそこから曲間なしに「Killing In The Name」へ。トム・モレロがまるでキース・リチャーズみたいにギターを開放で鳴らす。でもまあ合唱に関してはフジロックとか幕張のほうがすごかったかなあ、などという印象も残しなたが、「レイジ、レイジ、レイジ!!!」との掛け声と共に、約1時間のステージはまだ日が高い18:35に終了した。
即座に流れたADFの曲を聴きながら、気がついてみると前身ビシャビシャ。これは汗で、というよりもむしろ、水を浴びすぎてびしょ濡れといった感じか。 当然クツ紐は解けたままだし、カメラはボロボロだし、腕時計のボタンが知らぬ間に押されているし、Tシャツの中に隠していたはずの携帯用タイムテーブルがちぎれてボロボロになって紙1枚になってるし、ペットボトルの水は完全にお湯に変わっているし、といった感じでえらいことになっていた、
★ Battle of Reading III ・・・・ わたしバカよね
このレポートのみが他と異なっているのは、このライヴのみ自分が能動的になって参加できたからだ。 参加できた、というよりは、そうしないと自分は何もせずに、ストレスを溜め込んだままこのフェスティバルを終えてしまいそうだったからだ。
各アーティストのライヴレポートで逐一書いているように、イギリス人と日本人とのライヴにおける楽しみ方の違い、孤独に陥った自分の体調の悪さを理由とした受動的なライヴ観戦などがあって、かなりのストレスを自分自身の中に溜め込んでいた。だが理由はそれだけでなく、あれほど苦労して習得したはずの英語が、長いブランクもあってか、通用しない場面が多かったり、携帯電話会社との予期せぬトラブルに巻き込まれて辟易したり、宿泊先ホテルの従業員のつれない態度に激怒しかけたりと(1泊分余計に宿泊代を請求したくせに、謝りもしなかった。)、フェス以外にもストレスを溜め込む理由は色々あった。そして2日目にベックを見た後、その様々なストレスが最高潮に達し、些細なことにカッときて、実はこの旅行のために購入していたカメラを、ホテルの部屋でぶち壊してしまったりもしていた。
でも一通り怒りも収まってみると、結局俺は自分でなーーんにもしないまま、楽しもうという努力を自ら払わないまま、勝手に不満を溜め込んでいるんだな、ってことに気が付いた。 それにこのまま遠巻きにフェスを眺めるだけでいると、あれほど楽しみにしていたレイジのライヴもつまんないものになっちゃうし、せめてレイジぐらいは楽しみたいなあ、という至極単純な結論を導き出すに至った。 「よっしゃ、前に行ったる!」という気合のもと、この3日目のみ、すべてをホテルに置き去りにし、手ぶらでフェスに臨んだ。でも着いていきなり雨が降り出してどうなることやらと思っちゃったけど・・・。
前で観る、というどうしようもなく単純な行動なのに、実際に前に突っ込んでいってみると、色々なことが見えてきた。 あんなに嫌悪感を抱いていたイギリス人の音楽の聴かれ方が、そこではまったく違うことに気が付いた。 音楽への愛情たっぷりに、目の前のアーティストの一挙手一投足に一喜一憂する、極当たり前の姿がその周囲にはあり、極限の状態なのに他人を思い遣る配慮がそこいらかしこに感じられ、遠くて冷たく感じていたセキュリティの存在も身近になった。そして何よりも、あれほど痛かった腰の痛みが消えた。結局嘘っぱちの痛みだったのだ。凝り固まった筋肉が「もっと動け!」という警告を促していただけなのだ。様々なストレスのいくつかも、この瞬間に消し飛んだような気がした。
結局のところ、自分が何もしないと、なーんにも変わらないという、まあとりあえず当たり前のことに気が付いたこのレイジのライヴ。 イギリスに飛んだ、というだけで行動的になったつもりになっていた自分だが、結局与えられた環境に過敏に反応するだけで、よそ者というレッテルを勝手に自分に貼り付け、その状況をプラスに転じる気力も、周囲の状況に関係なく音楽へ能動的に関わるための当然の努力も、完全に失っていた自分に対して猛省を促すに至った。
結果として、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンは、自分にとってさらに重要なアーティストとなった。