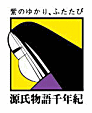
源氏物語(H20/1/11開始) 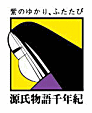
老いて来ると目が覚めるのが早い。まだ暗いのに目が覚めた。ラジオのスイッチを入れる。。
うつらうつら聞くともなしに聞いていると、田辺聖子の「新源氏物語」新潮社1979の朗読であった。
後で調べると、NHKの関西発ラジオ深夜便、源氏物語千年紀朗読特集「田辺聖子・源氏の世界」朗読藤井彩子であった。放送時間は深夜2時になっている。
この本は大変読みやすく分りやすく面白く読めた。源氏の面白さが倍加された。田辺聖子は逐語訳でなく、本質を掴み取り平易な言葉で、しかも原典に忠実に上手く物語を展開している。
私が「源氏物語」と関ったのは三年程前に日下リージョンセンターで「源氏物語」市民講座が在ったのに参加した事から源氏に関心が出て来た。毎月1回2時間の講義である。講師は森田登代子さん。家政学博士、日本文化研究センター研究員、大学講師をされている。受講者は殆どが中年以降の女性である。
空蝉、夕顔、若紫、末摘花、そして紅葉賀。今年から「花宴」に進みそうである。原文を読み解釈して進むので遅々としている。1年間に1巻程度のペースである。
このように月1回でも源氏に関ってくると、もう少し知りたいという欲求がでてくる。そこで源氏に関りのある旧跡やミュージアムを訪れたり、関係のある本を読んだりして、かなり知識が増えてくると、源氏の面白さ、楽しさなど「源氏物語」の素晴らしいと絶賛される理由が納得されてくる。
千年の風霜に堪える人間の本質を示唆し、構成や登場人物、展開や風俗、読み取る所は多々あり大変面白い物語である。
日本が世界に誇る至宝「源氏物語」が書かれて、今年で千年を迎える。
今年は源氏物語千年紀が多くの場で話題を呼ぶであろう。
源氏物語千年紀委員会 http://2008genji.jp/
寛弘5年(1008年)、平安王朝文学の最高傑作「源氏物語」が世に知られた。
| 与謝野晶子の源氏物語 上 光源氏の栄華(桐壺〜行幸) 中 六条院の四季(藤袴〜総角) 下 宇治の姫君たち(早蕨〜夢の浮橋) 序文に上田敏、森鴎外が明治45年1月に口語訳を祝う言葉を送っている。 |
源氏物語を全体として味わい豊満なる美を堪能するには、どうしても現代訳を必要とする。 H20/6/18 |
 |
紅葉賀 源氏の中将と左大臣家の頭将が青海波を舞う。 もの思ふに立ち舞ふべくもあらぬ身の
|
 |
宇治市源氏物語ミュージアムにて
|
| 源氏物語 夕顔 六条御息所の怨霊で 心あてに それかとぞ見る白露の 寄りてこそ それかとも見め 8月15日 中秋の名月 夕顔の家の夜明け前の状況。隣の家から庶民の姿が窺い知れる。 1000年前も現在も庶民の暮らしは大差ないし、話している内容も同じであり納得する。こんな暮らしの情景も描かれているのも素晴らしいと思われるのである。 |
|
 舞台の中心となった宇治 |
宇治十帖モニュメント 宇治川の河畔にある源氏物語の像 |
 |
石山寺の紫式部の像 |
| 末摘花 彼女は身分の高い姫君であるが、今は荒れ果てた邸に淋しく住んでいる。門は錆付き、粗末な食事、寒さに震えながらの困窮さである。 (私案)この時代は冬は現在よりもっと寒い。しかも部屋の中でも間仕切りも無く、隙間風が吹き荒ぶ大変寒い。勿論暖房機器などもない。人々は霜焼けに病んでいたのではないかと推測する。薬も無い。鼻は霜焼けに罹り易い。特に末摘花は鼻が高いのだ。霜焼けに患った鼻が赤く腫れ爛れていても不思議でない。戦後着るものも何も無い時、霜焼けで鼻を赤くしていた人を良く見かけたのである。 このような状態から末摘花の容貌が表現されたのではないかと弁護したいのである。 このような自分の容貌から気分が滅入り劣等感に悩み引っ込み思案、対面恐怖症などに陥り、野暮で気の利かない陳腐な女になってしまったのではないかと思うのであるがどうであろうか。 |
平等院 光源氏のモデルと言われている源融の別荘地。 近くには、宇治川を隔て宇治神社,宇治上神社がある。 田辺聖子
|