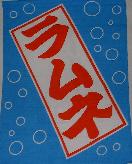清涼飲料水。炭酸ガスを溶解した水に少量の砂糖とレモン香料で調味。
(ラムネを飲むとげっぷが出るところから)月賦の隠語。
昔懐かしいガラス製の瓶入りです。
持ち帰りは出来ません。
ラムネの瓶が手作りで高価な為。瓶代必要
子供はラムネを一生懸命に飲むが、すぐ中に入っている(ビー)玉が、出口をふさぎ、喉に届かないのだ。そこで、お祖父さんがラムネの飲み方について説明。
この二つの凹みを下にして、凹みに(ビー)玉をのせ、出口をふさがないようにして飲むのだよ。
おじいさんと孫との会話。
ラムネはコミュニケーションの道具である。
光景2
スペイン系の女性がラムネを飲んだ。空になったラムネの瓶を振り興味を持った。瓶が欲しいというのであげる。彼女は瓶をマラカスのように、振りながら持ち帰った。
ラムネの瓶は楽器である。
光景3
若いお父さんが自慢。俺はラムネを吹いて開けると。
人差し指では開けられる。小指で開ける人もいるかも。しかし、息を吹いて開けるとはなんと言う肺活量か