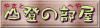昼食を摂った後、島ケ峰への道を少し辿ってみた。
スズタケのヤブこぎは強いられるが踏み跡はしっかりしており、ササさえなければ快適な尾根歩きが楽しめそうである。
ところで、本日の終点とした十字路の川窪側(北側)には、スギの木の元に、ひっそりと小さなお地蔵さんが佇んでいる。

十字路にひっそりと佇む峠の地蔵(彫られた文字は「三界地蔵」?とも読めるのだが、定かではない)。
三方(サンボウ=供物をのせる台)を手にした優しい顔の地蔵に手を合わせ、この日訪れることが叶わなかった「てんぐ岩」への宿題を果たす時に「またお会いしましょう」と心で告げ、峠を後にした。
*全行程の私たちの所要時間(コースタイム)は以下の通り。
【往路】
登山口<15分>陣ケ森<15分>丸山広場<17分>岩場の展望所<32分>戸矢ケ森<11分>川窪分岐三叉路<8分>送電鉄塔<22分>十字路(地蔵)
【復路】
十字路(地蔵)<19分>送電鉄塔<8分>川窪分岐三叉路<10分>戸矢ケ森<25分>岩場の展望所<18分>丸山広場<16分>陣ケ森<10分>登山口
備考
ここで紹介した登山道に水場はありません。
陣ケ森は、土佐町地蔵寺方向から見たその山容が富士山に似ているところから「秀麗山」とも呼ばれていたそうです。
陣ケ森の麓には、特筆すべき1本の天然記念物と由緒ある2つの神社が存在するので、是非訪れてみてください。以下に簡単な紹介をしておきます。
<シャクジョウカタシ(ヤブツバキ)>

まんべんなく花を咲かせたシャクジョウカタシ(ヤブツバキ)。周囲の建物などと比較すればその大きさが知れる。(3月24日撮影)
陣ケ森の南麓、吾北村柿薮(かきやぶ)にある上東(じょうとう)小学校(2001年をもって休校)の横には、日本一の椿(*1)といわれるシャクジョウカタシがある。
その樹形が、修験者などの持つ杖「錫杖(しゃくじょう)」に似ており、椿のことを方言でカタシと言うところから「シャクジョウカタシ」と呼ばれ、平成3年に吾北村の天然記念物に指定され、平成8年には高知県の天然記念物に指定されている。
樹齢は400〜700年、幹周り約3.2m、樹高は13mで、根元は2mほど土に埋もれていると言われる。その枝は直径約14mにわたり傘を広げたように四方へと伸び、山の神の止まり木といわれる「窓木」が数箇所にある。木のそばに立てば、その巨大さと、枝の描く不思議な放物線に誰もが圧倒される。3月の花時の素晴らしさも格別である。
根元には祠があり、これは高橋家の先祖で狩りの名手だった「弥十郎」とも、あるいは山伏に姿を変えた平家の落人とも言われる。
この木は昔から人々に愛され、特に子供たちはこの木に登っては遊び、花時にはその蜜を吸っては楽しんだという。
気の遠くなるほど長い時を隔てて子供たちを育んできたシャクジョウカタシは、この土地の偉大な母親であり、また、その傍にある小学校の隠れた名物先生とも言える。ついこの間まで賑やかだった上東小学校は休校になったが、下流の上八川小学校に通う子供たちを、このカタシはこれからもずっと見守り続けてゆくことだろう。
私たちが訪れたこの日、上東小学校PTAのみなさんは、忙しく翌日の「祭り(*2)」の準備をされていた。忙しい中、その手を止めて私たちにお話をしてくれた一人のお母さんは、「学校はなくなるけれど来年も再来年もお祭りは続けてゆきますから来てくださいね」と力強く語ってくださった。言い表せない寂しさもあるはずなのに、そんなかけらを少しも見せないで屈託のない笑顔は、今を盛りと咲き誇るカタシの花のように清々しいものでした。
(*1)>「巨樹巨木林(第12号/全国巨樹巨木林の会発行)」のリストによれば、単体での大きさは石川県津幡町「倶利伽藍谷の大薮椿」と並び全国トップクラスの大きさである。
(*2)>「祭り」とは、吾北村「カタシの花祭り」のことで、毎年3月の第4日曜日に様々な催しが行われている。
*シャクジョウカタシの紹介を書くにあたり、吾北村教育委員会の片岡さんに大変お世話になりました。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。
<高橋安之丞若宮八幡宮(若宮神社)>

やさしい風貌の狛犬、その向こうには百度石や立派な手水鉢も見える。階段の奥が社殿。
吾北村上八川連行(れんぎょう)にある「高橋安之丞若宮八幡宮」は、この地で村人のために尽力した義民「高橋安之丞」を祀るために建立されたものである。
高橋安之丞は、慶安3年(1650年)頃、上八川田野々(現在の連行とその周辺)に庄屋の長男として生まれた。
少年期からその言動は人々の感心を呼び、20歳で亡き父の跡を継いだ後も、その温厚な性格に慈愛溢れる行動は人々の信頼を厚くした。
積極的に村人を世話し、貧しい村の飢饉対策として新田開発を推進したり、痩せ地でも良く育つ稗(ヒエ)の栽培を奨励したり、楮草(かぢくさ=コウゾ)の改良や茶の栽培で所得向上を計ったりと、その功績は甚大であった。
しかし、そんな安之丞を不幸な出来事が襲う。いつの世にも人を妬む者はいるものである。
貞享4年(1687年)の12月半ば、未曾有の飢饉に襲われた上八川の地区を守るために、年貢の減額を嘆願した安之丞は、同郷の者で川橋三蔵という男に「一揆の首謀者」とでっち上げられてしまう。
三蔵に買収された役人は、弁明も許さず、ついに安之丞は元禄元年(1688年)10月、高知城下で処刑をされてしまうのである。
その後、非業の死を遂げた安之丞については、その首が生家に飛んで帰ってきたという「首飛来」伝説や、安之丞を奸計に陥れた役人の娘が処刑と時を同じくして変死し、また当の役人は狂気の末自害したとか、様々な伝説が残っている。
この若宮神社(俗に若宮様)は、そんな安之丞を慕う人々によって、首塚(*3)のあった場所に建設され、その霊を懇ろに弔り、守護神として祀ったものである。
死後300年を経た現在も県内外からの参拝者が絶えることなく、今も毎年3回(*4)の祭典が行われている。
若宮神社は、その参道の狛犬や台座の彫刻、江戸末期の灯籠なども素晴らしいが、特に神社の拝殿に施されている彫り物は見事で、鳳凰、虎、鶴、亀、、木菟、兎、猿、竜などが驚くほど芸術的に描かれている。
なお、この神社は「縁切りの神様」としても有名である。
(*3)>安之丞の胴体については、生前に熱い恩義を受けた農民「清兵衛」が処刑場で嘆願の末にひきとり、自宅近くに埋葬し社殿を建設して弔った。この神社は高知市長尾山町に若宮神社としてある。
(*4)>祭典は3月2日、7月2日、12月2日に、いずれも午後1時頃より行われている。
<三宝山高峰神社>

右が巨大な手洗石(手水鉢)。左の鳥居を奥に急な石段をしばらく登ると本殿がある。
陣ケ森の北西にある土佐町安吉には、巨大な手洗石(手水鉢)で有名な三宝山高峰神社がある。
この神社は作神信仰(農作業の守護神)の神社として県下に広く(*5)その名を知られている。
神社の入り口には立派な鳥居があり、広場には土俵場がある。そして何より目を奪われるのは鳥居の右手にある大きな手洗石である。
この石は明治10年頃、麓の石原川の河原から引き上げて奉納する計画をたてたが、その道たるや羊腸のような坂道を30町(*6)余り、しかも数千貫(*7)もある石を人力だけで運搬するのは並大抵のことではなかった。そこで、このことを知った多くの崇敬者が毎春の農閑期に集まって奉仕した結果、5年後には山の9合目まで引き上げていたのだが、神仏合祀の紛争で中断を余儀なくされた。
しかし、時を経て昭和3年(1928年)、御大典記念事業として奉献曳石(石引き)が再開され、現在の場所に安置されたものである。
なお、通夜殿には岩を引き上げる際に使われたシュロ縄が今も大切に保管されている。
高峰神社の本殿は正面に仰ぎ見る三宝山の山頂にあり、巨大な手水鉢のそばの鳥居をくぐり、急な石段を5分あまり喘ぎながら登ると注連縄の張られた木の鳥居(2番目の鳥居)に辿り着く。ここには大きくて立派な鷹の灯籠があり狐も彫られている。文政13年寅5月、山田中野村の多仲、キモイリの銘がある。なお、ここまでは裏手から車道も延びてきている。
さて、さらに参道を少しのところにある少々古い鳥居(3番目の鳥居)をくぐると最後の急坂を5分あまりで社殿にたどり着く。拝殿の入り口には鶴と亀の彩色された彫り物が見事で、その造りもおそらく明治時代のものであろう随所におびただしい飾りがある。残念ながら本殿は保護板に覆われて垣間見ることはできない。
山歩きの後に参道の石段は堪えるが、是非訪れてみたい場所である。
(*5)>「高知の登山&ハイキング(山崎清憲著)」によれば、その信仰圏は安芸郡から須崎市方面にまで及んでいるとの記述がある。
(*6)>距離の旧単位。1町は約108mあまり、つまり30町は3.2Km強になる。
(*7)>重さの旧単位。1貫は約3.75Kg