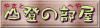樹々とササ原のどこまでも緑一面の風景を軽快に笹平山に向かう。

膝までのササにおおわれた登山道。
なだらかに来て少し下り、最低コルからは照葉樹林の中を登り、やがて広い林と植林との縁を辿る。

かつて林道だったのかと見紛うほど広い道を行く。
山頂が近くなるとなだらかな稜線に幅の広い道が現れるが、この道にはところどころ木々が茂り歩きやすいとは言い難い。
それでもこの道を辿れば方向を見失うこともなく、やがてぽっかりと山頂に飛び出す。
笹平山山頂には2等三角点の標石と小さな山名板がある。
笹平山には子供たちも集団登山をしていたということで、かつては三角点を中心にきれいに刈り払われていたようだが、現在はカヤが茂り、様々な木々があちらこちらで背丈を競い合っている。
おかげで展望もくつろぐスペースもなく、早々に山頂を後にした。

草木に埋もれそうな笹平山山頂の三角点。
だらだらと尾根を辿った縦走路は人によって受け取る印象は違うもので、私たち男3人は一応山頂を踏んで笹平山の確認を終えたが、しかし、同行したY子さんにとっては展望もなく草木に埋もれた三角点は何の魅力も無かったようである。
結局、彼女は三角点まであと十数歩の位置まで来ていながら、山頂を踏むこともなく引き返したのだった。
実は山頂には木陰が無いため、「陽にあたるのが嫌だった・・・」というのがことの真相なのだが、だからといって山頂を踏まないことは理解し難いが、そういう山歩きももちろんあるのである。
さて、往路を引き返し無事に下山した私達は、残った時間を利用して、番所谷の奥にある竜王の滝(大滝)を散策し、平家伝説に彩られた祇園神社に楢(ナラ)の巨木を訪ね、十和村の最奥にある集落を経て林道を県境の峠まで旅した。
その途中には、平家の落人が家宝の巻物を虫干ししたという「絹巻之駄馬」にも立ち寄り、あるいは古屋山アカマツ天然生林保護林を確認してきたのだが、残念ながら当初の目的だったヤイロチョウには結局のところ出会えなかった。
しかし、きっと私達の歩いた山の何処かにヤイロチョウは居たはずで、私達には彼らの姿をとらえることはできなかったが、彼らは私達の姿を遠くから見ていたに違いない。
あの美しい姿に出会うため、今度は求愛のさえずりを聞かせてくれる5月頃、あの「シロペン、クロペン」と啼く声を訪ねて再び北幡の山を歩こうと私は秘かに思うのだった。

大道林道から遠望する笹平山。
*全行程の私たちの所要時間(コースタイム)は以下の通り。
【往路】
森林浴の森入り口の広場(自然観察教育林の看板)<1分>林道脇登山口<15分>第1の分岐<8分>第2の分岐<20分>第3の分岐<12分>第4の分岐(町村界尾根)<31分>土佐地蔵<6分>地蔵山山頂
=計93分
【復路】
地蔵山山頂<5分>土佐地蔵<18分>第4の分岐(町村界尾根)<15分>境653の標石<31分>笹平山山頂<30分>第4の分岐(町村界尾根)<11分>第3の分岐<12分>第2の分岐<7分>第1の分岐<10分>林道脇登山口<1分>森林浴の森入り口の広場
=計140分
*笹平山に行かないで往路をそのまま下山する場合は約65分の所要時間になります。
備考
登山道中に水場はありませんが、第2の分岐を真っ直ぐに行くと谷で補給できます。ただし、登山道コースを大幅に外れるので水はあらかじめ準備しておきましょう。
地蔵山には愛媛県日吉村の父野川上宮成と父野川節安から林道を経由して登るコースもあります。
笹平山には大正町下津井(松川に架かるかつての森林鉄道の旧橋「めがね橋」の北側)から登るコースもありましたが、現在は追い山(狩猟)に使われている程度で、笹平山山頂の近くには林道下藤蔵向畑線の町村境付近から林道が延びてきていますので、ますます道は荒れる一方の様です。
龍王の滝を過ぎてなお大道林道を県境まで行くと、大道藤川線の記念碑が立つ県境の峠に出ます。ここからは幡多地方の雄大な展望を望むことができます。
【龍王の滝と龍王神社】
龍王の滝は番所谷の橋から約1kmほど上流にあり、車道の右手(路肩側)に「龍王の滝」の由来を書いた案内板があります。
龍王の滝はその案内板から階段を下りて橋を渡り3分ほどのところにあります。
この滝は「大滝」とも呼ばれ、3段からなるうちの「三の滝」は落差15mほどあり、美しい渓谷には夏でも涼しい飛沫が漂っています。
この滝の上手には龍王神社があり、神社の対岸からはこの滝の上部にある二つの滝と深淵の「カマ」を覗き見ることができます。龍王神社へは車道に引き返して少し上方に向かえば案内板があります。
龍王の滝には、昔から竜が住んでいたと云われていましたが、ある時、権兵衛という男がいたずらで滝の中に鉄くずを投げ込んだところ、晴天俄にかき曇り、暗雲垂れ込み滝は逆巻き、ついには嵐を呼んで、谷川は大洪水になり大災害が起きて、当の権兵衛も濁流にのまれて水死したとそうです。その後もこの付近の集落には不幸なことが続いたので、そこで人々は龍王神社を建立して龍王様の怒りを静めたといわれています。
なお、この滝の近くでは、大雨の後などに「天空之瀧」という美しい滝をも見ることができるそうです。

「龍王の滝」の「三の滝」。落ち着いた雰囲気の良い場所にある。
【祇園神社の大楢】
龍王の滝から車道を更に北へ向かうと、祇園神社の境内には十和村の天然記念物に指定されている大きなコナラの木があります。
祇園神社は文治元年(1185年)源平屋島の合戦に敗れた平家の落人が伊予の国から予土国境の通称蟹越山(がにごえやま)を越えて入郷居住した当時、平家一族の守護神として祭祀したものと伝えられています。
境内に自生する楢の古木は神木として崇められ、根元周囲5.7m、目通り周囲3.8m、推定樹齢500年といわれ、コナラとしては日本一の大木であろう、と案内板には書かれています。

祇園神社の境内にあるコナラの大木。