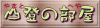さて、山道はいっとき伐採地で途絶えるが、前方に見える山頂までは伐採地と林との縁を辿るように山肌を登る。
尾根筋まで駆け上がると、山腹を伝う山道が確認できる。
少し下ってから雑木林の急坂に挑む。
先ほどまで叩いていた無駄口もたちまち消え失せ、ぜいぜいと喘ぎながらひたすらに坂を登る。

伐採地の上端を辿りながら高度を稼ぐ。
完全にふくらはぎが伸びきった頃、尾根に出て小休止をとる。
しかしお腹も空いてきたことだし、息さえ整えると、休憩は手短に切り上げて一挙に山頂をめざすべく立ち上がった。
振り返ると、小春日和に行当や羽根の岬が輝き、足もとでは赤く熟れたセンリョウの実が年の暮れを知らせてくれている。
そんなすべてが疲れて重たい足を引き上げてくれる。

伐採地を辿る尾根道からはところどころ西山台地方向の眺望も開ける。
ひたすら伐採地の縁をよじ登り、池山さんのやまなみに肩を並べようとする。
妥協を許さない直登を克服すると、ようやく、あの夏の日に探索した見覚えのある尾根の張り出しまで辿り着いた。
すると、あとは、尾根沿いに残る雑木林に入り、なだらかにコルを通過すれば一挙に山頂である。俄然余裕が出てきた。
不思議なもので、あの夏に悪戦苦闘した辛い思い出さえ楽しかった思い出に変わる。
山頂直下のコルでは、以前に喘ぎながら這い上がった踏み跡を確認した。あの強者どもと歩いたひと夏を思い出しながら、薄暗く陰気な植林を見下ろし、勲章のようなため息をつくと、山頂に向かった。

東ノ川を隔てて対峙するやまなみ。
伐採地の最上部から尾根沿いの踏み分け道に入るとほどなくピークに至る。
ひんやりとした風が漂う林には、落ち葉に埋もれた三角点があった。頂は密生した木々に囲まれ眺望は無い。
愛しいものを愛でるように両手でそっと三角点の標石に触れると、二度目の確認を終えて山頂を後にした。

木々におおわれた笠木山山頂。
待ちかねた昼食は伐採地の縁(へり)でとることにして、太平洋を眺めながらお弁当を広げた。
吉良川の町並みの手前には歩いてきたあの広い芋畑も見えている。
海岸線を行当岬まで伝い、やまなみを遡ると、その奥には室戸岬の風車(風力発電)も見える。
にわかに、このすがすがしさに声をあげたくなった。
と、突然、隣でI君が奇声をあげながら柏手を打った。すると目の前で帆翔(はんしょう)するトビが驚いてくるりと輪を描いた。
真似をして私も手を叩くと、またトビが輪を描いた。
二人で顔を見合わせて、心の底から笑った。

昼食をとりながら眺めを楽しむ。中央はるかに運動公園や歩いてきた芋畑が見える。
*私たちのコースタイムは以下の通り。
【往路】
笠木山運動公園<3分>登山口(車道終点)<12分>送電鉄塔<12分>峠(86番の石仏)<46分>三叉路(51番の石仏)<27分>大規模な伐採地の手前<37分>山頂直下のコル(脇の内分岐)<4分>山頂
=141分
【帰路】
山頂<2分>山頂直下のコル(脇の内分岐)<25分>大規模な伐採地の手前<16分>三叉路(51番の石仏)<24分>峠(86番の石仏)<11分>送電鉄塔<9分>登山口(車道終点)<2分>笠木山運動公園
=89分
登山ガイド
【登山口】
今回紹介した登山口は笠木山運動公園の奥にあります。しかし、車道は狭く坂も急なので、吉良川の街並みを散策がてら麓から歩かれることをお奨めします。たとえば「町並み駐車場」あたりからだと土佐漆喰の白壁が美しい街並みを横切って、御田八幡宮に向かいます。神社からは車道または階段を経て笠木山運動公園に登ります。公園から200mほど歩くと車道終点が登山口になります。なお、車の場合は吉良川公民館の前を回り込んで北に向かい、「笠木山運動公園登り口徒歩5分」の道標に従って車道を運動公園まで走ります。駐車スペースは車道左脇にあります。
(その他のコースの登山口については以下の「コース案内」と「備考」をご覧下さい)
【コース案内】
車道終点から山道に入ると、すぐに出会う分岐は右上にとります。まもなく野菜畑を抜けると送電鉄塔のそばで作業道に出ます。
作業道を歩いて広い芋畑を抜けると植林に入り、小さな峠状のコルで村四国の石仏と出会います。ここからは51番まで石仏を辿ります。村四国の参道だけに比較的しっかり整備されています。
51番の石仏と別れると、すぐの分岐で参道を外れ、踏み跡を頼りに二重尾根の様な地形の谷部を登ります。まもなく正面にこんもりとしたピークが近づきます。ここで、ピークの左手を巻いて植林に入り、小さなコルで尾根の東端に向かうと、照葉樹の中に明確な山道が現れます。しかし、参道の分岐以降は道が分かりづらいので、正確な読図と地形の判断が求められます。何度か道無き山を歩いたことのあるベテランの方との同行をお奨めします。なお、少しでも不安に感じたら躊躇せず引き返してください。
さて、山道を歩いて尾根の東山腹を北上すると、やがて正面に大規模な伐採地が現れます。ここで山道は途絶えますが、ひとまず伐採地の縁を登ると、再び明確な山道が現れます。以降は山頂まで伐採地の縁を辿りながら上をめざします。
「脇の内」に下る分岐を通過するとすぐに、伐採地の上から林に入ります。踏み跡をたどるとほどなく山頂です。帰路は往路を引き返します。
なお、回送をされる場合、山頂直下のコルから谷沿いを西へ下れば「脇の内」まで下りることが出来ます。また、伐採地の上部から東に伐採地の縁を辿れば東ノ川に下ることも出来ます。
また、北村から村四国を組み入れて登頂計画を組まれるのも良いでしょう。(その場合は順打ちをお奨めします)
備考
登山道に水場はありません。
コース案内でもふれましたが、51番の石仏と別れてからは道が不明瞭になります。不安を感じたら無理しないで引き返してください。今回のコースの全行程は休憩や昼食も入れると5時間〜6時間を要します。また、ほとんどが東斜面や林の中の歩行になります。日暮れの早い秋以降は特に注意してください。
参考のために代表的なコースを簡単に紹介しておきます。
1)脇の内から谷沿いを遡る場合は、鳥居と小祠を目印に、その左手の谷の右岸から登り始めます。登山道はすぐに南の谷に乗り換え、以後はその谷の右岸沿いにしばらく登ります。やがて標高400m辺りで谷を渡ると左岸を登ります。植林に付けられたコースサインを辿ると山頂直下のコルに出ます。
2)吉良川八十八ケ所を組み入れる場合は、まず北村の松寿寺に行きます。文中でも述べたようにここに1番と88番の札所があります。松寿寺から車道を北に向かうと200mほどで下山道との分岐を通過し、さらに200mほど行くと右手に案内板の立つ参道入口が現れます。車道の左手には室戸線69番の送電鉄塔が立っています。
3)川長の上から伐採地の北縁を登るコースについては作業道の状況や伐採の状態により変化するようなので、現地でお問い合わせください。
笠木山の山名については、村四国開設の願文に「笠置山」とありますが、これについては全国的にも「笠木」と「笠置」が混在しています。
これについては「笠を置いたような山容」を例えた説や、山頂に「笠のような木(松の木か?)」があったなどの説もあります。
一方で、主に山頂に置かれた神社が「笠置神社」だったという場合もあれば、あるいは「笠祗神社」なので「笠祗山」と書き表す例もあります。
今回紹介した笠木山は、さきの願文や三角点名において、「笠置山」と表記される場合もあります。
今回の登山口である吉良川町には意匠に優れた伝統的な美しい町並みがあります。四国では、内子や脇町などとならんで「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されています。最近では土佐東部観光のメインコースに組み込まれているようで、休日ともなるとカップルや団体旅行者などで賑わっています。帰路には是非とも、そんな独特の美しい町並みを散策してみてください。
また、町並みの裏手にある御田八幡宮の境内には、推定樹齢500年ともいわれるクスノキの古木や、高知県指定の天然記念物「ボウラン」があります。ここで奉納される御田祭りは日本三大奇祭のひとつともいわれ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。


吉良川の町並みの奥に御田八幡宮の鳥居が見える。右は初夏に開花するボウランの花。