九州以北の陸上に生息する毒蛇は、クサリヘビ科の日本マムシとナミヘビ科の日本ヤマカガシの二種類である。ともに頭の形は三角形である。
日本マムシ(Agkistrodon.b.blomhoffi)
体長は45〜60cmで、太くて短い。背には黒褐色の銭形の斑紋がある。腹には星のように黒い点々があるが、体色には変化が多い。
山林、田畑、草むらに多く夜行性で活動至適温度は摂氏25ないし28度であり、高湿を好む。夜行性だが曇りの日は昼間も活動する。
胎生(卵胎生)で8月から9月に5〜12匹の仔を出産する。小鳥、ネズミ、トカゲ、蛙、ヘビ等を餌とする。
上顎骨先端近くに通常一対の上顎骨から吊り下がった形で折り畳み式の大きな菅状毒牙を持つ。攻撃時は先端近くにある側孔から毒液を排出する。攻撃できる距離は約50cmほどである。
マムシによる咬傷は年間約3000件あり、月別では7〜9月、時間帯では午後3〜9時に多く、田畑、山林、草むらでの労働中の受傷が多い。
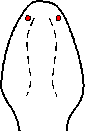 日本マムシの歯跡、赤点が毒液注入部
日本マムシの歯跡、赤点が毒液注入部日本ヤマカガシ(Rhabdophis.t.tigrinus)
体長は60〜120cmで、赤みがかった褐色の体に黒い斑点があり、首筋は黄色いが、体色や斑紋にちがいも多い。
水田、池、川辺など湿ったところに多く棲み、トカゲ、蛙、小魚を好む。
溝状の牙は上顎骨後方に固定されており小さい。ヤマカガシは2つの分泌腺を有し、その一つは上顎骨後方にあるドラベルノイ腺で、咬まれたときに先述の後牙の近くの分泌口から毒素を分泌し、それが後牙による創から吸収されてヤマカガシ咬傷を引き起こす。もう一つは後頚部にある皮脂腺で、強い圧迫により体鱗の間隙から分泌液を吹きだしヒトに結膜炎などの障害を与える。
ヤマカガシによる咬傷は、昭和48年以降十数例であり、8〜9月に多い。つかまえて、もてあそんでいるときに咬まれることが多い。
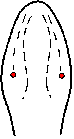 日本ヤマカガシの歯跡、赤点が毒液注入部
日本ヤマカガシの歯跡、赤点が毒液注入部2)蛇毒の毒性とおおまかな症状について
毒液の排出量は毒蛇の種類、大きさ、攻撃回数、受傷状況により異なるが、マムシでは0.025-0.05ml程度といわれている。
毒性は、1)出血毒作用、2)溶血作用、3)血液凝固阻害作用、4)血管壁障害作用、が主なものとされている。
マムシの毒は咬まれた部位の組織や毛細血管の壁を溶かす。咬まれると激痛を感じ、次第に大きく腫れてくる。
毒の回りは遅いが乳幼児や高齢者では死亡することもある。
ヤマカガシの毒は血液の凝固作用を失わせる。咬まれても痛みを感じないこともあるが、数時間後に歯ぐきや古傷からの出血、皮下出血や血尿などの症状があらわれる。
3)主症状、所見について
局所症状と所見
(1)牙痕
通常一対でその幅、数は注入毒量に比例する。毒の注入があれば出血、発赤、浮腫、疼痛を伴う。
(2)疼痛
受傷直後からあり、灼熱感を伴い浮腫の増強とともに激しくなる。時に知覚異常を伴う。ヤマカガシでは疼痛を欠くことがある。
(3)浮腫
疼痛に続いて受傷15〜20分後から起こる。毒量に比例して経過とともに増強し、12〜24時間でピークに達する。
(4)出血、紅斑、皮下斑状出血、水泡形成
赤血球血管外漏出、毛細血管透過性亢進、血管拡張、血漿成分血管外漏出によって起こる。 ヤマカガシでは咬傷部出血の他に歯肉出血、鼻出血、血尿、全身皮下出血班が数時間から2〜3日で出現する。マムシでは所属リンパ節の圧痛、腫脹が認められることがある。
全身症状と所見
頭痛、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、多汗、微熱、複視が受傷24時間以内にみられ、重症化するとショック、意識障害、乏尿、呼吸障害、ヤマカガシでは全身の著名な出血傾向が認められるようになる。
4)治療
以下は専門的な項目ですが、知識として知っておいていただければと考え、記載します。
1)軽症の場合
局所症状、所見はごく軽症で、全身症状なく検査成績正常のときは局所の消毒と必要なら抗生物質を投与し、6-8時間経過観察する。
2)中等症の場合
局所症状、所見は中等度で、全身症状、検査異常はないか、あっても軽度の場合は局所洗浄、消毒、咬傷部小切開、吸引、輸液、抗生物質、セファランチン、破傷風トキソイドを投与し、入院後腫脹の増大があれば抗毒素血清を投与する。
3)重症の場合
局所変化が著名かつ進行性で、全身症状、検査値異常も明白ならばバイタルサインの頻回チェック、抗毒素血清の追加投与、輸血、利尿剤の投与を考慮する。
4)最重症の場合
ショック、意識障害、呼吸障害、急性腎不全、DIC、MOF等の重症例では上記のほかに新鮮血、新鮮凍結血漿、血小板、フィブリノゲン、濃厚赤血球輸注のほか必要に応じて血漿交換、人工透析、人工呼吸なども行う。
参考>合併症と死因について
四肢の変形、拘縮、腎機能障害、血清病が主な合併症である。主要死因は急性腎不全、DIC、肺梗塞、臓器出血(特に脳出血)である。
5)毒ヘビに対する予防
毒ヘビの生息地や活動時期・時間などを考慮し、毒ヘビの居そうな場所には近づかない。それでも登山道などでそれらしい場所を通過する時は充分に注意し、万一毒ヘビを見つけてもあわてないでやり過ごす。(誤って踏むなど、危害を加えたりしなければ襲ってくることは少ない。)
毒ヘビがかま首をもたげた攻撃姿勢の時は、用心して半径1m以内には近づかない。
万一の時のために、必ず通信手段(無線機や携帯電話)は確保しておく。
6)咬傷を受けた場合の応急処置
まず、あわてないことが肝心である。
マムシの場合毒の回りは遅いのですぐに死亡することは考え難い。
ただし咬傷部位が頭部や首筋などでは治療を急ぐ必要がある。
それでも冷静に、携帯電話や無線機などを使用して、救急機関に連絡をとる。
症状に応じて与えられる指示に従うのが一番である。
あらかじめ指示された場所まで歩いて下りなければならない時でもあわてないでゆっくりと歩いて行くようにする。
なお、足などに止血帯を巻く場合は咬傷部位より心臓よりで軽く静脈(青く見える血管)が浮き出る程度に巻き、きつく縛りすぎると逆効果になる。
毒を口により吸い出す方法は、虫歯や歯ぐきからの毒やバイ菌の混入に注意が必要である。
切開して毒を除去する方法は素人には危険であり、ヤマカガシには逆効果の場合もある。
また、咬傷部位を冷やすことは組織の破壊を促すことがわかっているので、冷水などで冷やすことは避ける。
ちなみに、受傷時刻、場所、毒蛇の種類と大きさや応急処置についてなどは、医療機関での重要な問診となるので記憶しておきたい。