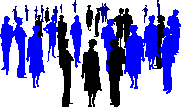
WEBMASTER の 今週の述懐 . . . . .
「市民」の続きの続きです
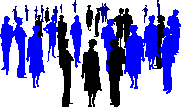
結局、「街並み」をより良く(美しく)するには、皆が相互に市民性を発露して、
何がしか お互いに 調整し合うこと、すなわち
誘導なり 制御なり を導入することが必要なことは 間違いありません。
分かりやすい例 :
マンハッタンの南端に ミノル・ヤマサキの World Trade Center という
極端にのっぽなツインタワーがあります。
これが New York の"Fabric(街並みの基本的な織り成され方)" を
台無しに壊してしまったと言うのが 当地での おおかたの見方であり、
この失敗への反省が それ以後の New York のまちづくりの デザインコード、
アセスメントに 生かされているそうです。
誘導や制御については、 二つの考え方があると思います。
1) 考え方の一つは、設計者や市民 それぞれの 美意識や良識に
街並みを委ねる という 「市民性への全面的信頼」。
・・ これが実現するためには 設計者を育てる建築教育において
「個々の建築の価値・美しさは それを包む都市的コンテクストの中でこそ
初めて社会的意味を獲得できる」 という理念と、
実技的にも 周辺との呼応をデザイン上工夫することの 徹底的な訓練とが
まず必須でしょう。(日本の建築教育では決定的に欠落)
・・ また、市民という視座からの論理的批判精神の育成も このままでは不足です。
社会資本である建築物に対するデザイン批評が
市民的広がりを得られるようにしたいもの。
(京都駅問題は良いきっかけか?)
2) もう一つは、制度によって 何らかの美的統合を担保しようとする方法。
健全な例として 真鶴の「美の基準」条例が すぐ思い浮かびます。
私は 規制行政は 悪であるとは思いません。必要です。
しかし一般的に、制定の背景や 運用のあり方は 議論を要します。
市民的合意に支えられていない場合や 形骸的なデザイン規制に陥るケースが
今後 考えられます (エスプリを理解しない書割景観では困ります)。
・・・
今 日本の現状では 街並みの大半は
当面の利潤追求のための「純・収益道具」建築、 「部屋数確保」建売住宅、
粗利益30%の「下請け任せ」メーカー住宅、 設計者の見えない「場末欲望ビル」、
等々で 埋っています。
上記の二つの考え方 同時双方をもって対処しても 改善の前途はきびしい。
二つ同時に ものすごいエネルギーを必要とします。
そして このエネルギーについては やはり 設計料の問題にも 行き当たらざるを得ません。
ということで この項 来週は お金と 知的生産の関係について。
ではまた。 (^_^) 安達
98/02/15