
伊丹近辺の猪名川渡し
ここでは、中国大返しで通った可能性のある渡しの内、伊丹・尼崎の
「猪名川の渡し」を考えてみる。
【渡渉候補地】
津戸中道(高田−戸ノ内)と西国街道(辻村−下河原)以外を明治時
代の地図と、絵図と、現代地図より探る。
渡渉可能地点の条件は、
1.絵図の道が川を挟んで両側にある、又は渡しの記述が有る。
2.明治の地図で、川を渡っている道、又は橋がある。
上記2点とした。
3.現代の地図にその地点を比定した。
右図参照。
津戸中道(高田−戸ノ内−庄本)以外は徒渉可である。
4.現在の水深を測定し別表に付加した。
(津戸中道のルートが舟渡であることの確証を得る為。)
5.「津門中道」から上流(北)へ「西国街道」までとした。
【結果】は別紙の表に掲げた。
「猪名川の渡し」PDF 「猪名川の渡し」(Excel)
を参照して下さい。
表の説明。
・河川別、年代(絵図、地図)別、渡渉地点名。
・藻川と、猪名川の二川部分だけとした、絵図によっては、
現「駄六川」も猪名川の分流ととして書かれているが、
ここでは無視した。
又、明治より前の時代、藻川と分流後の猪名川は、現在の
旧猪名川に当たると思われるが、その流路の比定が難しい
ため、渡渉地点名は適当に付けた。
・川の両側の村名(町名)を”−”で結び渡渉地としている。
(該当なしは”−”だけ)
・当時の渡渉地点と思われる場所に一番近いと思われる現代
の地点をあげた。
・絵図、地図は
1、明治の地図(明治42測地)
2.天保国絵図(天保 6年(1835)下命、同 9年(1838)完成)
3.元禄国絵図(元禄10年(1697)下命、同15年(1702)完成)
4.慶長国絵図(慶長10年(1605)下命。一部元和三年図)
5.現代の地図(2015年)
を使用した。
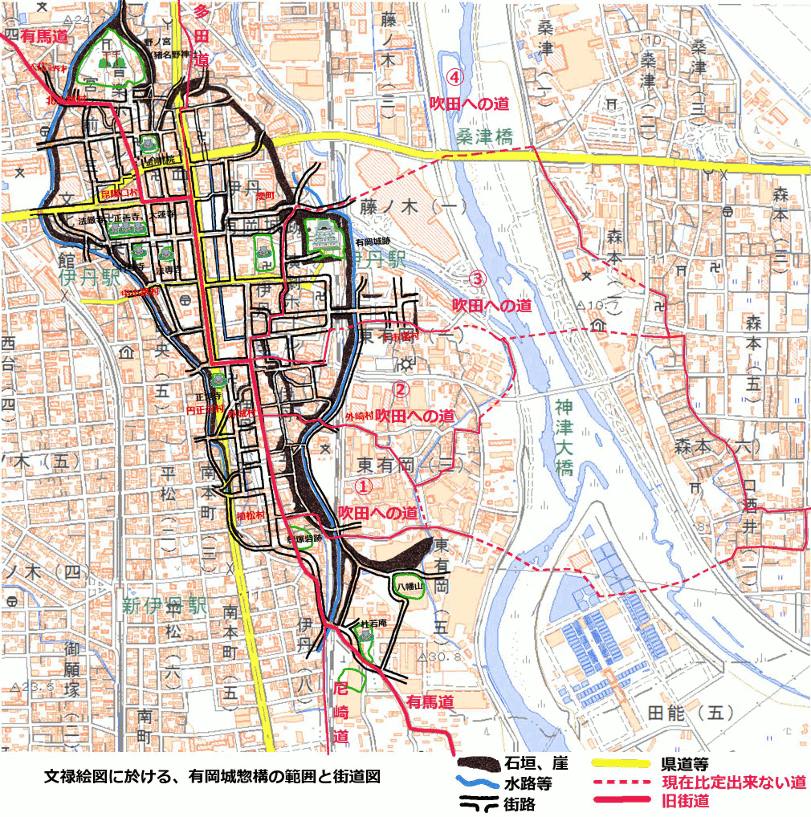 【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】
【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】
1.単に示威行動の為だけなら、距離を短くするか。
2.武器補給等の為なら、城中心部に入らざるを得ないか。
3.村重の反乱後、再建されていたであろう城は惣構だったのか、
城の位置と領域を検討する。
江戸時代(天保)に写した、文禄(1592-1596)絵図を用いた。
【結論】
上の図なら 8、
右の図なら 3「伊丹(下市場)ー森本」が第一候補である。
【参考資料】
国土地理院地図
伊丹古絵図集成
ホームページの先頭へ

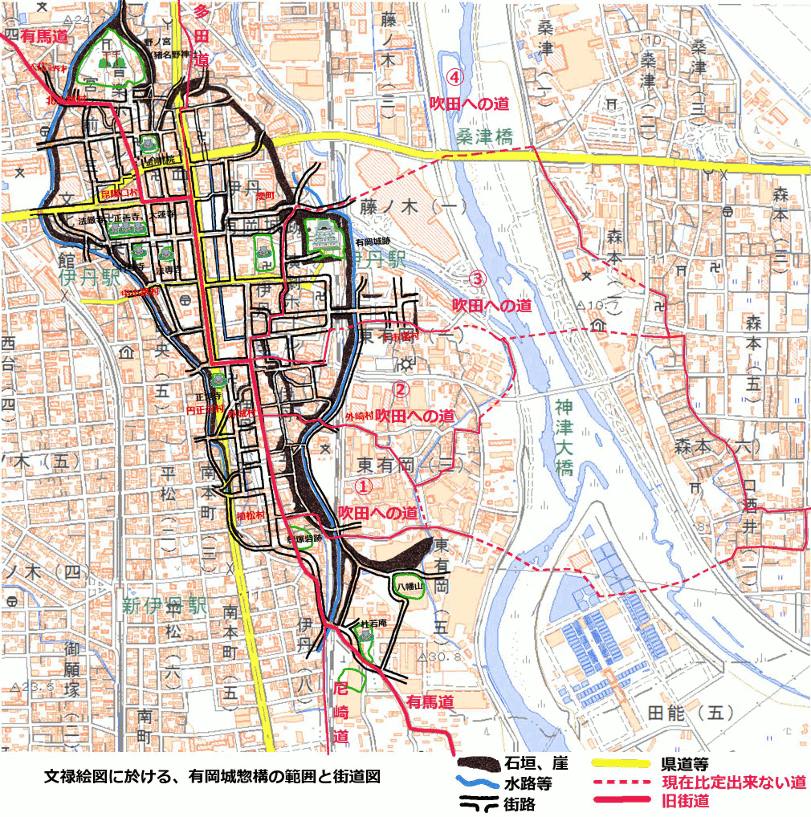 【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】
【「有岡城入城アリテ」をどう解釈するかにより、経路が変わる。】