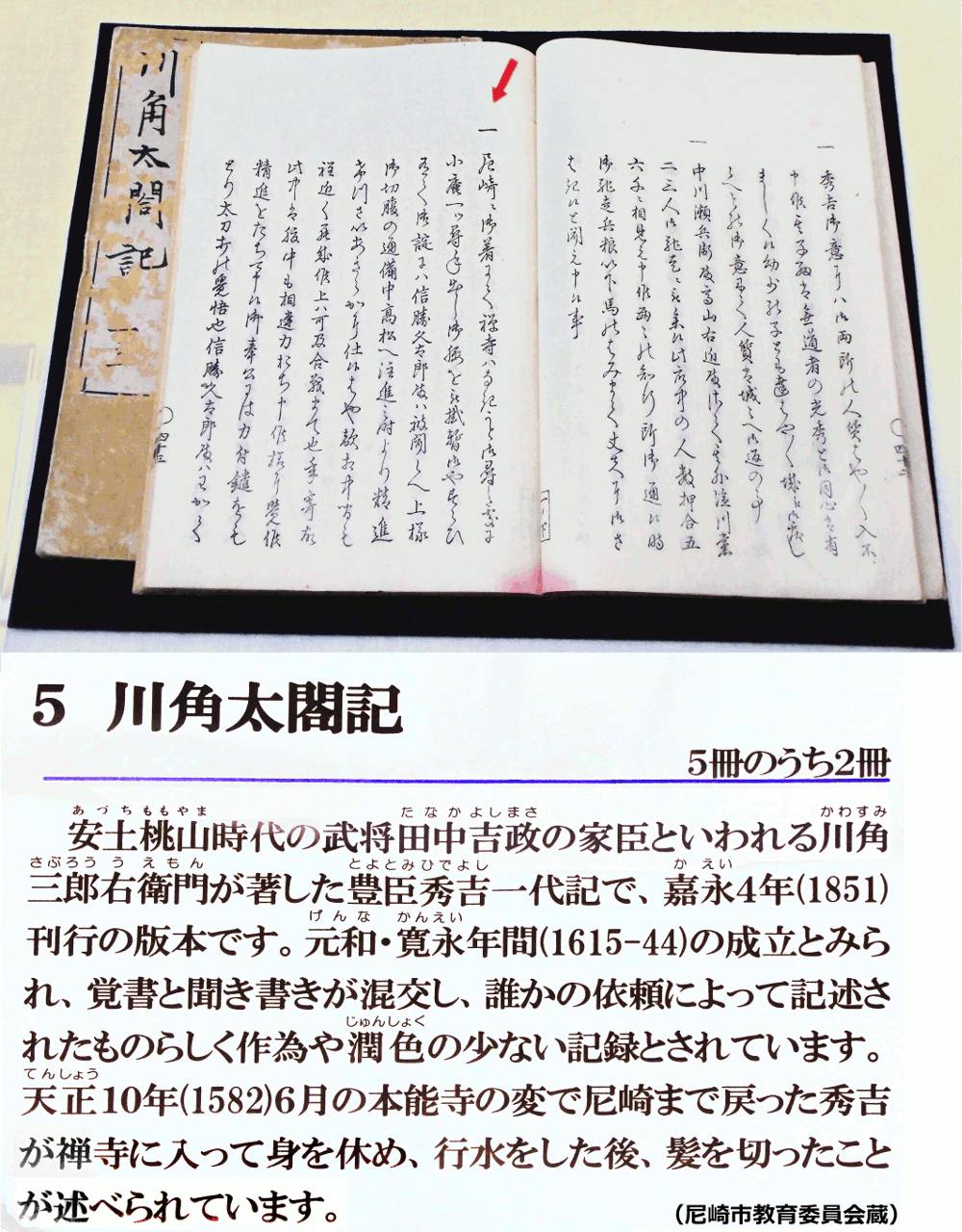武功夜話第二巻
中国大返し初出
『中国大返し』又は『備中大返し』とは誰が言い始めたのか。
『中国大返し』の表現は、後日他人が付けたものである事は間違いないであろう。
「大返し」の表現により、行軍の全体像が歪曲されて伝わっているように思える。
即ち、備中高松城より、摂津富田まで一目散に駆け抜けたと感じてしまうのであ
るがどうも事実は違うようである。
よって、その初出を探ることにより、全体像がゆがめられた原因を探ってみたい。
現在の所、一次資料(手紙、日記等)に、その表現を見つける事は出来ていな
いが、「武功夜話」(前野家文書と呼ばれている古文書群の中心的な家伝資料
とされ、史料価値は論争中)に、『備中返し』の表現がある。
これを見ると話し手の回顧であるため、自慢口調の様に思え、備中国高松城から
を「備中」とし、「退却」と受け取られることを避ける為に「返し」を入れた表現
の様に思える。
その記述する所は、
「第十 天正十年六月十一日、羽柴筑前守尼ヶ崎に着陣」で、喜平治
(前野吉康(前野長康の筋か))存命中に語り、「それがし生涯において辛き
事三度あり、一、金ヶ崎退き口、二つ目は備中返し、三つ目は高麗陣、忘れ難き
難儀の取り合いに候なり。」
とある。
此処の記述では、単に備中からの退却したという事実を述べているだけで、
成句となった、「中国大返し」の感はないが、初めて「備中返し」がみられる。
更に、その文中に
「備中を退くの時」、「首衆此度の変事は申し伝え候も」、「口外仕らぬ様申し諭し」
「御敵は摂津に在り」「急げや急げ」
などの表現があることから、一般の卆などは、事実を知らさないことでもあり、
「退却」、「転戦」にしか受け取っていないであろう。
但し、同じく十巻の見出しには、「羽柴筑前守秀吉、備中大返しの事」と「大」
の字が付けられている所は、これを書いた人が、威勢の良さを出すために付けた
ように感じられる。

中国大返し図
最近のテレビ等で「これが世に言う、『中国大返し』」の様に中国に変えてし
まうと、中国地方全てを全速で走り抜けた印象になってしまう。
確かにその描写の中で姫路までの行程では非常に過酷な様子があるが、
それ以降は通常の出陣状況のように見受けられる。退去に当たっても、
殿軍が明記され、二路に分けて退去し、兵庫にあっては、淡路島への攻撃
軍を出す等、周到な作戦行動を採りながらの進軍となっている。
また、姫路到着(約100㎞山道多)まで2日、富田着(約110㎞ほぼ平坦)
まで3日を要していのを見ても、姫路以後はスピード優先ではないであろう。
確かに姫路までの疲れは尋常でなく、その後の行動に大きく影響はしている
が、「中国大返し」の言葉だけであたかもマラソンのゴール宜しく、山崎ま
で突っ走るイメージを持つのは誤りである。
秀吉や官兵衛の美談として描かれている、姫路城の食糧や財宝を全て、家来
に分配したエピソードも、走り抜けるとしたなら、余分な荷物を持たせるこ
ととなり、矛盾となろう。
本来、「中国大返し」は、姫路(秀吉居城)までの迅速なる撤退と、姫路
から光秀討伐(天下取り)の出兵を示すものです。
言い換えるなら、「備中大返し」と「京都出兵」なのです。
2
【参考】
武功夜話については、愛知県江南市のホームページに詳しく掲載されています。
「武功夜話」を参照。
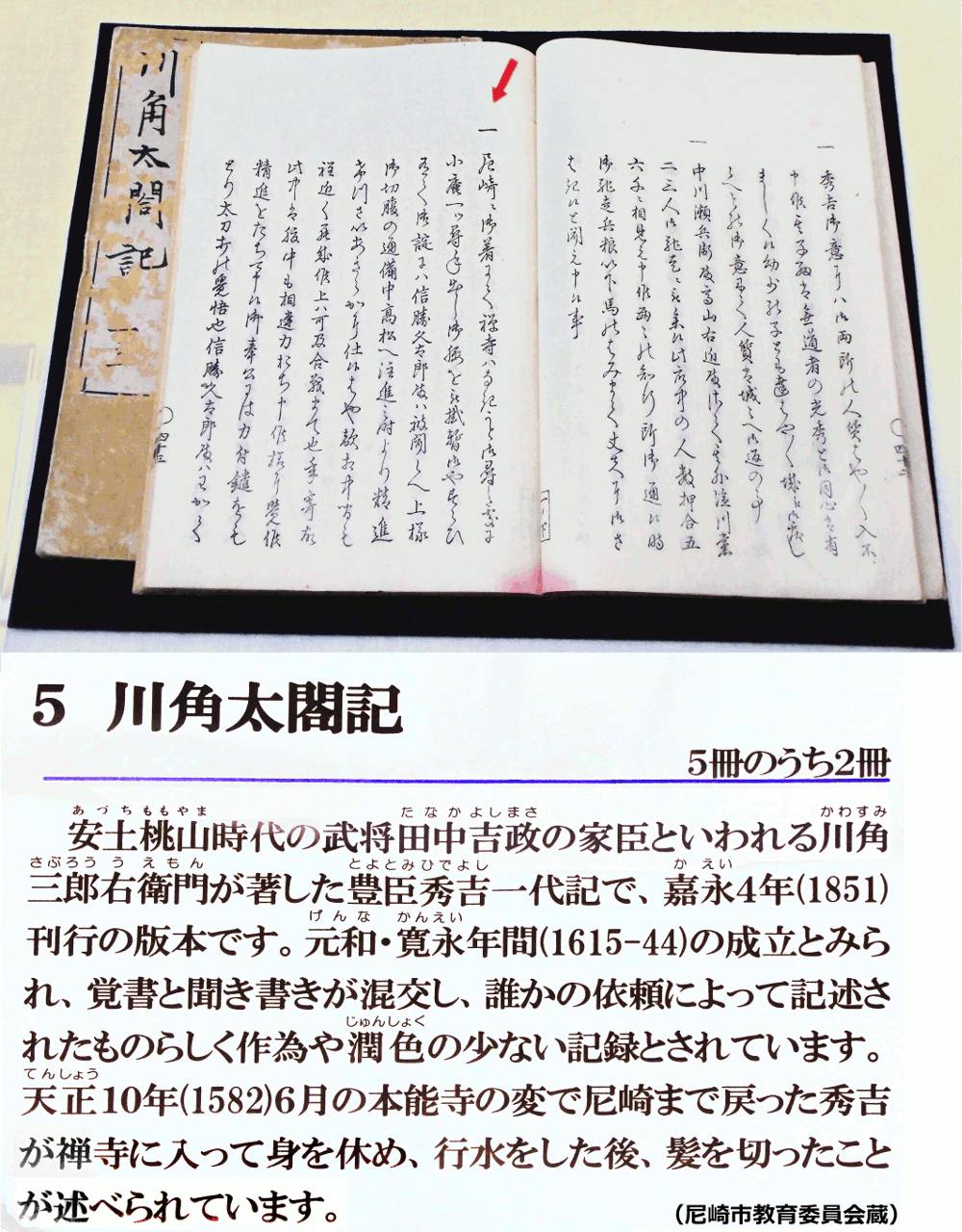
川角太閤記二冊
【その他史料等における表現例】
・「惟任退治記」続群書類従 第20輯 塙保己一編纂245Pでは、
『六月六日未刻。引備中表。至備前國沼城。』と表現されている。
・「川角太閤記」改定史籍集覧第19冊近藤瓶城編17Pでは、
『一右に如申上候四日の夜の丑の刻に御引拂ひ被成備中の國をは
はるかにのひさせ給ひ備前の國江被成御入候處に…』との表現だけでなく
22P、『…護摩堂の僧被申上候其様子は明日の御出陣殊外日柄あしく…』
と言っている様に、姫路からは「出陣」とさえ書いている。
・「豊臣記」小瀬甫庵 では
『同(六月)五日秀吉宇喜多直家拂陳
一日一夜経廿七里打入姫路、軽可息人馬處、光秀語織田七兵衛信澄手合河州旨、
八日酉ノ刻聞姫路
信孝於生害可為武勇瑕瑾
九日出姫路、
十一日至摂州富田、大坂ヘ以使、…』
とあり、「陣払」「打入」等の表現となっている。
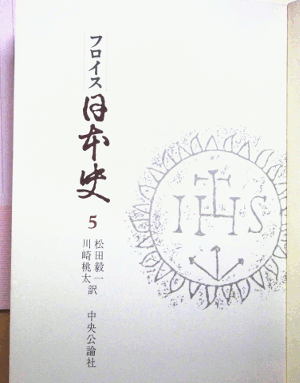
フロイス日本史
・「フロイス日本史」では
『毛利の諸国の征服者である羽柴(秀吉)の陣営では、敵方に先立って信長の死を知ると、
すでに彼らを大いなる窮地に追い込んではいたが、羽柴は有利な立場で彼らと和を講じた。
そしてただちに殿たちは、急遽、自身の居城に帰還し始め、当の羽柴も明智と一戦を交え
に行く準備を完了した。』
とあり、「帰還」「交戦準備」等の表現となっている。
【史料解題】
1.武功夜話 江戸前期成立。 前野家文書(非公開)古文書群の中から、吉田家子孫により写本が発行されている。
2.惟任退治記 天正十年成立。 秀吉の御伽衆大村由己の『天正記』のうち、本能寺の変から信長の葬儀までを記述。
3.川角太閤記 元和(1615~24)年間の成立。 田中吉政旧臣の川角三郎右衛門による秀吉一代記。
全五巻〔改定史料集覧19冊〕
4.豊臣記 寛永三年 (1626)初版。 儒学者小瀬甫庵著、史料的価値は低いとされるが、太閤記本の基底となっている。
〔吉田豊訳、教育社新書、は現代語訳〕
5.フロイス日本史 第3巻は文禄三年(1594)まで執筆。イエズス会(キリスト教)宣教師ルイス・フロイスによる
編年体歴史書。原文はポルトガル語。本能寺の変の時は京都に居らず、伝聞を記述したともある。
「日本史5 五畿内篇Ⅲ」松田毅一訳 中央公論社刊
ホームページの先頭へ