多聞院日記
多聞院日記は、「国立公文書館デジタルアーカイブ」多聞院日記. 第3巻(巻24-巻31)
で参照できる。(下記該当は121コマより。)
ここでは、『続史料大成 第40巻 多聞院日記三』 竹内理三編 臨川書店より挙げる。
誤パンチ、誤変換もあるかもしれないので注意願います。
文の始めに、『一』が書かれているが省略した。『・・・』は文省略を示す。
同じものを繰り返す記号(踊り字、重ね字)等は、同じ文字を続けた。
改行は適当に行った。
天正十年六月一日 今日夜大雨事事敷降、夜明テ五ノ三より止了
順慶今朝結願退出了、大宮番衆へ二石ツ、被遣之云々
流鏑馬定於尺迦院初任一献在之、是へ両種メン十瓜把廿・一荷種々
文観ノ立像ノ文殊八斗ニ買遣之
信長公一昨日二十八日上洛云々大宮番衆ヘス、両種遣之
二日 小折新九郎ヨリ以上十石うツほやへ渡之由也、
順慶へ大門ヨリ峯寺付御礼米以上三十石うツほやへ可遣之通付私ヨリ済了重テ可有算用
順慶今朝京へ上處、上様急度西国へ御出馬トテ既ニ安土へ被帰由歟、依之被帰了
山崎屋東武白瓜廿持見廻ニ来語了
信長於京都生害云々、同城介殿も生害云々、惟任並匕兵衛申合令生害云々、
今暁之事今日四之過ニ聞へ了、盛者必衰之金言、不可驚事也
諸国悉轉反スヘキ歟、世上無常、追日現眼前ゝゝ様躰ハ慥ニハ不知如何成行哉覧ゝゝ
三日 暁より大雨下、京都の儀慥には不聞ヘ、二条殿ヘ城介迯入
當今ヲ人質ニ取間、則時共ニ王モ御生害、新ヰンモ放火了云々
誠歟、浅猿浅猿、○咒合九十七万二千九百返了
教淨峯寺ヨリ昨夕帰、五十石之大略渡之由也、重可尋之
京ヨリ注進之面、信長ハ本能寺ニテ生害、城介ハ二条殿ニテ生害
菅屋久衛門・村井三人・福富平衛門此外小姓衆五六百生害了
日向守ハ先ツ坂本ヘ入大津、松本、セタニ陣取云々細川殿モ生害云々
今日當国衆ハ悉大安寺・辰市・東九条・法花寺辺陣取云々如何可成行哉
四日 筒井ニハ南方衆・井戸一手ノ衆惟任ヘ今日立云々いかがいかが
六下丁聞集一二ノ所广尼長印房ヘ書遣之
釜口の米ノサン用状上丁
五日 昨日山城へ出衆ハヤ引退了ト然ハ三七殿ト被申合歟尤々
西坊見廻ニ鈴持来了
於大坂七兵衛ヲ生害云々、向州ノ聟一段逸物也、三七殿・丹羽ノ五郎左衛門・
鉢屋なとノ沙汰歟、但雑説歟
伊賀は御本所衆ノ城開、則国ハアキタル間各牢人衆入歟云々
木津も筒順ヘ申合則存所ヘ入了、初夜之時分ニ入云々
安土ハ去四日ニ向州ヘ渡了、棹山ヘハ城ニワノ五郎左衛門、山崎源太左衛門入了、
長浜ヘハ斉藤蔵助入了、筒井先日城州ヘ立タル人数今日至江州打出、
向州ト手ヲ合了、順慶は堅以惟任ト一味云々、いかが可成行哉覧
日中後又大雨下了
慶禅子腹切了未死歟云々、題目ハ不知
七日 御忌日ヘハ雖雨止、足下シルキ間不出
新九郎ヨリ替米済了、ヒコ二朗ヨリ十七石ノ替済了
八日 中坊駿河法眼社参之次立寄語了、若神被来語了
六日ヨリ今日マテ於東室同者論在之
九日 過夜大雨下了、以外之洪雨也
今日河州ヘ筒衆可有打廻之由沙汰之處俄ニ延引云々
又郡山城ヘ塩米俄被入云々いかが覚悟相違哉、ふしんふしん、いかが
十日 先日山城ヘ立筒人数昨今打返了、藤吉近日ニ上決定決定ト、依之覚悟替ト聞ヘ了
昨夜十新男子誕生了、尤珍重々々大慶大慶、年来ノ念願之處尤珍重珍重
十四日 又雨下、十新ヘ樽一荷・餅五十、コフ十新三使ニ下了
昨日従向州使ニ藤田伝五順慶ヘ来、
無同心之通返事切レテ昨夜木津迄帰テ又呼返了ト、いかが、心苦敷事也
藤吉ヘハ既順慶無別儀間、誓帋被遣之、村田・今中使云々
昨日十日社家西死去、新権神主拝賀沙汰之、無一収納不便不便、宗禅・順陽・濁穢了、
奥田息太夫新権神主ニ上云々
井戸若狭比間煩、既ニ一昨日九日ニ死了、深隠密云々、実否如何一向ウソ也
今日四過ニ郡山ニテ順慶腹切ス申来、以外仰天ノ處順慶ニテハナシ伝五ニ腹切セ了ト申来、
肝消ス處ソレモウソ也、ナラ中同前ノ沙汰、併天魔ノ所為也、沈思沈思、ナラ中物ヲ隠ス、
向州ノ内衆カクシ物取ヲ一両人殺了云々、沈思沈思可出来ト見タリ、無端無端
備前衛門太上被是取違サン用了、合場座ニ反分買得云々
於三学院一周忌講延識、問陽教、題真如無為仮実云々、
大雨下、乍去雷始鳴、ツユ可上相歟昨日より六月節ニ入了
ナラ中入夜迄物隠事心外也
十二日 葉柴藤吉既至摂州猛勢ニテ上、家康既至安土著陣云々如何可成行哉覧、
惟日衆八幡・山崎ニ在之、淀辺ヘ引退歟云々依之今朝ハナラ中静ル
殊昨日雑談申出、隠物取事井上九郎三郎カ物共沙汰也、則三人令生害弥シツマル
昨日於郡山国中与力相寄血判起請在之、堅固ニ相拘了
金院雇西屋談義田算用則一帋書之了
十三日 於坊餅米以下人夫召寄ツカスヘキ通申付之、
當年安居赤御供赤飯之用意、チチ一石一升、白八斗一升、ウル三斗二升、白二斗三升存之
チマタ彦二郎上、去年ヨリ成身院替米今日可渡之由被申由、則切帋遣之、十五日済了
城州ヰゝノ岡、草内以下山口ヘ宇治田原ヨリ出テ焼之、大雨下
勝龍寺城落居了、則筑州令在京、惟日ハ坂本ヘ入退了云々、実歟
十四日 日中マテ大雨下、打続降雨希代也
教淨寺ヨリ昨夕帰由、ヒセンヘ三石カワシ切帋取之了
善春日中茹汁汲了
槇嶋井若裏帰順慶ヘ渡トテ今朝井戸重郎一手ノ衆従早旦出了
并南方越智楢原万歳以下悉以立了、明日順慶ハ可有出京之由沙汰在之、
勝軍比量古抄二帖長賢房寫来了
十五日 過夜雷鳴一夜大雨降了
去十一日歟ニ木津ヨリ庄村下地被注了、乍去坊領ハ除之云々一帖遣之
向州人数千余十二日ニ損了、坂本ヘワツカ三十計ニテ打帰、
昨日ヨリ筑前大津マテ打越了、今日山ニテ見レハ比叡山ノ東ノ方大焼也ト申、
必定坂本焼城責之ト聞ヘタリ
順慶今朝自身千計ニテ立了、昨今立入数六七千可在之ト云々、
今夕醍醐陣取ト申、餘ニ被見合筑州ヨリ曲事ト申云々、
惣テ天下ハ信長如御朱印毎事可在之云々、尤々
大乗院今日御上洛了、畑事可被仰入之用歟、如何如何
去月廿三日迄雨不下、廿四日ニ降始ヨリ至過夜連雨廿日計下、今日ハ雨止、天気快然
先日合戦ニ惟任討死一定一定云々、則時相終了
十六日 先夜井戸若州槙嶋ヲ離了、荒木清兵衛討入云々、順慶ノ仕合以外之由口遊、
於事実者咲止咲止
木津モ追返了ト、一定歟、沈思沈思
昨夜ヨリ庄安坊ヘ来了、身上被申分由也
新造屋本番之處、賢聖院ヨリ舜実房ニ誂別供来、四斗二升在之相博済了
七月上旬三、丁聞集勧修坊ヘ遣之
順慶仕合曲事ト沙汰故、又ナラ中物ヲ隠、沈思沈思、又日中前ニ雨下
西発志院弟子兒得度、有尋松円、十四才、ヲウシ西師清ノ穢け也
十七日 明日赤御供之用意如別記之
惟任日向守ハ十二日勝龍寺ヨリ迯テ山階ニテ一揆ニタタキ殺レ了、
首モムクロモ京ヘ引了云々、浅猿浅猿、細川ノ兵部太夫カ中間ニテアリシヲ引立之、
中国ノ名誉ニ信長厚恩ニテ被召遣之、忘大恩致曲事、天命此如
知足坊牢人セラレシ、今日歟帰坊云々
高田三川守還住云々
斉藤蔵助生捕テ安土ヱ引云々、天命天命
十八日 赤御供備進了、日記如別帋、二石計ノ入目也、坊之衆各来、日中飯了
備衛上了、合場領二反新買之券文来了、尤尤
寺門ヨリ礼ニ、三長殿・筑州ヘ源舜承仕江州ニテ対面テ帰了
大門様ハ未京ニ御渡、御書被下了、本能寺ニハ日向初テ首共三千程在之云々、
斉藤蔵助十七日ニ京ヲ引テ首切了云々
十九日 加賀来、馬人夫事申定了、専識房来、因一喩ニ談義了
廿日 箸尾ヘ當室御神供米取ニ遣・・・
廿一日 ・・・
近衛殿生害トテ一乗院以外取乱也、一向一向雑説也
・・・
廿五日 ・・・
入夜子之初点歟、大乗院ノハ西坊ヨリ火出、アキ小サシキ并西ノワラヤニ家焼亡了
円専并アキ雑舎ハ不焼、風マイテ吹付如此、消肝了、付火ノ様ノ様ニ申歟、
西ノ坊ノ持仏堂ヨリ焼出了、丸焼過分ノ損亡云々、真言ノ聖教大事之本尊以下悉以可焼歟、
猿猿猿猿、物取二人殺了云々
・・・
七月六日 ・・・
天下ノ様、柴田・羽柴・丹羽五郎左衛門・池田紀井守・ホリ久太郎、
以上五人シテ分取ノ様ニ其沙汰アリ、信長ノ子供ハ何モ詮ニ不立云々、浅猿浅猿
本尊風入了
七日 節供如常、両常往来、雨気由則日中降畢
天下ノ様御本所ト三七ト所論故、両人名代ヲ止テ、御本所ハ伊勢トヲワリ、
三七ハ濃州ノカリ、上野殿ヘ伊賀一円、
柴田ハ長浜一円廿万石所云々、ホリ久太郎ハ城介殿ノ若子ノ御モリ、
依之江州ノ中郡廿万石所、
丹羽五郎左衛門ハ高嶋郡、志賀郡、池田紀伊守ヘハ十七所、大坂取之、
筑前ヘハ山城一円・丹波一円(コレハチクセカ弟ノ小七郎ヘ)・西ノ岡勝龍寺以下河内ニテ東ノ山子キ以上取之、
大旨ハシハカマゝノ様也、則下京六条ヲ城ニ拵云々、
名代ナシニシテ、五人シテ異見申モリタツヘシト云々、
筒井ハ和州一円・宇智郡・宇多郡モ被付云々、筑州一円入魂云々、
爰元先以可静謐歟尤尤、
以上如此雖相定、欲マキレ又種々可存之子息達大勢佐之、何も詮ニ不立之、クルイ可出来歟
・・・
今夜入大雨降下、如當年六月土用中大雨ハ不覚事也、先以満作珍重珍重
・・・
八日 今日日中ニ沐浴八万四千罪云々即各沙汰之、大夕立雨下了
今日城介殿若子三才、羽柴筑前守御伴ニテ在京、諸大名衆礼在之云々、
則大門様モ御上洛了、昨夜大雨夜明テ止、天気快然尤尤
木津羽柴筑前取トテ、奉行浅野弥兵衛ヨリ数出可仕之由折帋来
以上。
【私的な解説。】
多聞院:興福寺の塔頭の一つ。上記部分は「英俊(1534~1596)」の手になる。
夜明けて五ノ三:辰の三刻とするなら午前8時。
聟:婿、ムコ
轉:転
慥:ソウ、タシカ
陳:陣か
四ノ過:卯の一刻過ぎなら、午前5時過ぎ。
咒:呪、ジュ
初夜:戌の刻
迯:逃げる
新ヰンモ:新院も?
歟:ヨ、かヤ、疑問の意
畢:ヒツ、オワル
帘:簾、幕、旗
尤:もっとも
大乗院:奈良興福寺
帋:紙と同じ
汲了(言篇でなくサンズイ篇とした):『大字典』になし、『”K'sBookshelf”漢字林』「言部」 にサ、 ①こじつける
とあるが、こじつけ終わるでは意味をなさない、茹で汁を汲(く)み終った、とした。
○は: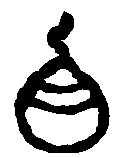 のような記号
のような記号
・Wikipediaに「原本は散逸しているが、江戸中期の写本が興福寺に伝存」とあるので、時制については
考慮を要するかも知れない。
天正十年頃の暦法、宣明暦(862~1685)なら四刻制であるが、貞享暦(1685~1754)なら八刻制と思われる。
「写本」を信じ、読み替えなしで記述されているとして宣明歴を適用。
・6月14日(私説11日)に「昨日より六月節ニ入了」とある、六月節が小暑を示すなら、太陽暦7月6・7日
頃となり、旧暦では天正十年六月七、八日に該当する。依って、11日の方がより近い。
・7月7日に、「六月土用中、大雨ハ不覚」とあり、六月の土用(立夏、立秋の前18日間)が何日かの検討要。
凡そ、太陽暦5月の始めが立夏に、8月7・8日頃が立秋になる。天正10年6月30日が、グレゴリオ暦7月
29日になるので、7月21・22日辺りから土用となるか、7月21日とすると、旧暦六月廿二日となる。
家忠日記には、『廿二日戊申 土用に入候』とある。六月二十二日。
・本能寺の変前後の天気を拾い出したものは、天候PDF 天候(Excel)を参照。
「奈良」の部分が、多聞院日記よりの抽出。
ホームページの先頭へ