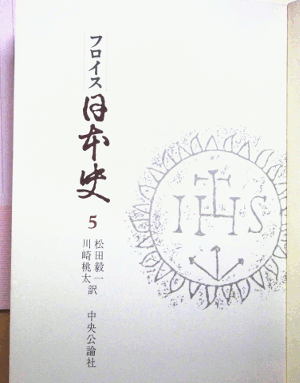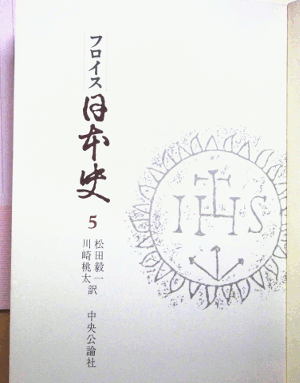
フロイス日本史
「日本史5 五畿内篇Ⅲ」松田毅一訳 中央公論社刊から
本能寺の変に起因する、秀吉の中国大返し(備中大返し)について、
次の観点から一部を掲げる。
1.市中の混乱振り
2.旗色不明
3.一揆の跳梁
4.摂津の状況
5.秀吉の大返し
6.合戦への備え
7.合戦直前の明智等
8.初戦の後
9.勝利の日時
各章の見出し
第56章:明智が謀叛により、信長、ならびに後継者の息子を殺害し、天下に叛起した次第
第57章:この争乱により、司祭、修道士、および安土の神学校が受けた難渋と危険について
第58章:明智の不運と十一日後の死去について
【市中の混乱振り】
天正10年6月2日
57章
「木曜日の朝方、かの近江国出身の一貴人は事の経過を知って明智方に走り彼に
従う証として自邸に放火したが、それは非常に美しい邸で城に接して建っていた。
我等はそれを神学校から望見していたが、何のためか、なぜそうするのかが判ら
なかった。
…ジョアン・フランシスコ師は長白衣を着たまま後から来ていたが、たちまち
追剥どもが彼を襲い〔当時、市中にはこうした輩が横行して、盗みと掠奪のかぎ
りをつくしていたので〕、銀を所持していると見て探索し…
同司祭はそれが聖務日礼書であることを示すためにただちにかけ合うと、まだ袖
から取り出さないうちに彼らはそれを彼の手から奪い、ほかには何も発見できな
かったので彼を置いて立ち去った。…」
都においてさえ信長一人がいなくなるとこの様な状況であるなら、いわんや他
の地でも同様、或るいは、それ以上であったのか。
統治する武将が、在地していればその様な事は無かったのか、気になる点ではある。
例えば、大和には、筒井順慶が出陣前であったと思われるので、奈良の様子等が
分れば参考に出来るだろう。奈良の様子は「多聞院日記」で多少であれば知り得る。
この後58章では、安土、美濃、尾張では殺人強奪に明け暮れるとあるが、57章
の最後では、美濃の大垣は平穏だとしている。
【旗色不明】
57章
「…信長の訃報に接すると、ただちに一人の殿が岐阜の(信長の)長男の邸を
封鎖し、いずれの側につくか態度を明らかにせぬまま城を占領してしまった。…」
【一揆の跳梁】
58章
「明智が安土へ帰りその後津の国河内国へ引き返した。
彼が去った後の安土では、家々の掠奪、強盗、破壊、それに追剥の跳梁以外は
何ものも行われなかった。しかも同地のみならず、堺の市から5,6日の距離にある
美濃や尾張の諸国までが街道や間道において、また街路や町内で、殺人と強奪に
明け暮れる始末であり、それはいとも大いなる荒廃をもたらすために地獄全体が
開放されたかと思われるばかりであった。」
…
「他の異教徒たちの城では、城主が不在の間に、彼らの家臣たちすら、それに農民
(たちも加わって)、家財を盗んだり、その他多くの侮辱を(主君に)加え(危険
に陥っ)た。しかし高槻では、いっさいそのようなことは行われなかった。なぜなら
そこでは人々は皆キリシタンであったから、むしろ(反対に)、彼らは自分の家を
放置して、外部から加えられるかも知れない掠奪や襲撃から身を守るために、自ら
武器を手に取って城に立て籠もり、(自分のことより高槻城を守るという)別な(
意味で、キリシタンとしての)名誉を発揮した。」
掠奪強盗を一揆と同列に見なしてはいけないかも知れないが、各地で再び動乱の
状況に戻った様子が見て取れる。
【摂津の状況】
58章
「明智が信長を殺した頃、津の国の殿たちや重立った武将らは毛利との戦いに出陣
していたから、同国の諸城の占領をすぐに命じなかったのは、明智が非常に盲目で
あったからで、彼の滅亡の発端であった。それらの諸城は、信長の命令によって
ほとんど壊された状態にあり、しかも兵士がいなかったので、五百名あまりの兵を
もって人質を奪い、彼らを入城せしめることは、彼にとって容易な業であったはず
である。しかるに彼がなすことは、すべて好結果から彼を遠ざけ引き離していった。
高槻城の(人々は)皆キリシタンであったので、ジュスト右近殿が、毛利(氏と)
の戦いに出かけて不在であることと、
…
なぜなら明智は勘違いして、右近殿は(中国から)帰って来れば自分の味方になるに
違いないと考えていたからである。…」
摂津三将(高山、中川、池田)の各拠点の内、高槻(高山)は留守になっている
事が分る。三将とも既に中国出陣中であると見える。何処に居たのであろうか。
「変」が無ければ、信長は中国備中へむけ進軍する予定であった、おそらく信長は、
船で淀川を下り、尼崎で上陸(注、武功夜話ではこちら)し西進するか、あるいは
は船を乗り換えて、海路西へ進むと思われるので、軍の主要部は、2,3日先行す
る必要があると思われる。秀吉が、尼崎、富田(高槻)を一日で進んでいることか
ら見て、京都から二日先行としても、尼崎以西に居たであろうと考えられる。
候補地として、尼崎、西宮、兵庫等になるか。今一つ、西国街道を使ったとする
なら伊丹を加えてもよいか。池田も出陣中とするなら、西宮以西となるか。
高山は大坂、池田、中川は住吉にあったとの説もあるが、備中出征軍が、道の便
が悪い大坂方面にいるのは、如何なものか。
注)、「武功夜話」清助扣(ひかえ)に、
『此度の御出馬の御進路、海上をさけ陸路を取り、播州より備前入りの道程、すな
わち摂州尼ヶ崎より播州に越しなされ、三木お泊りこれより姫路へ御成り御お泊り、…
御府内公播州入りは六月七日、右の旨御沙汰の次第、しからば御先手の諸将三日
頃には播州御通過、右道中の…、取次の御使者、猪子兵助申し越し候なり。』
とある。信長が6月7日に三木着とすれば、6日兵庫、5日尼崎、4日京都発の予定
かと考えられる。先手の諸将が4日先行とあるので、6月2日には兵庫に有るべきか。
【秀吉の大返し】
58章
「毛利の諸国の征服者である羽柴(秀吉)の陣営では、敵方に先立って信長の死を知ると、
すでに彼らを大いなる窮地に追い込んではいたが、羽柴は有利な立場で彼らと和を講じた。
そしてただちに殿たちは、急遽、自身の居城に帰還し始め、当の羽柴も明智と一戦を交え
に行く準備を完了した。」
…
「同国の三名の重立った武将は、羽柴が(もはや)さほど遠くない(ところまで戻って来てい
る)との希望のもとに出陣し、軍勢を率い、山崎と称せられる非常に大きく堅固な村落まで進
んだ。彼らが互いに結んだ協約では、…」
取敢えずは、居城への帰還である事。秀吉にあっては、一戦の準備とは微妙な表現である。
宣教師とはいえ一般人とは変わりなく、尼崎の軍議内容など知り得ていないことが分る。
【合戦への備え】
58章
「ジュスト(右近殿)が高槻に到着すると、キリシタンたちは皆蘇生したようになり、
彼らはただちに明智の敵であることを宣言し、大急ぎで城を修築した。この修築を彼は、
信長の息子の三七殿と毛利の征服者である羽柴とともに行ったが、彼らはこの復讐に
ついては団結しており、双方が集め得る最良の軍勢をもって、ともに明智討伐に臨む
覚悟でいた。」
中国大返しが、単に速さだけを求めた訳ではなく、城修築を含め、適切な戦闘体制を
採りつつ進められた事が伺える。
又、わざわざ「明智の敵」と宣言している事も興味深いと言える。(秀吉の他将への
宣伝を目的とする情報戦か、右近が秀吉への従属表明をしなければならなかったのか)
【合戦直前の明智等】
58章
「明智は都から一里の鳥羽と称する地に布陣し、信長の家臣が城主であった勝竜寺と称する、
都から三里離れた非常に重要な一城を占拠していた。彼はその辺りにいて、自分の許に投降し
て来る者たちを待機するとともに、羽柴の出方を見極めようとした。
…
当時彼は八千ないし一万の兵を有していたであろう。そして津の国の者たちが、予期した様に、
自分に投降して来ないのを見ると、彼は若干の城を包囲することを決意して、高槻に接近して行
った。
同国の三名の重立った武将は、羽柴が(もはや)さほど遠くない(ところまで戻って来てい
る)との希望のもとに出陣し、軍勢を率い、山崎と称せられる非常に大きく堅固な村落まで進
んだ。彼らが互いに結んだ協約では、当時までジュスト右近殿の大敵であった(中川)清兵衛
(清秀)殿と呼ばれる彼らの中の一人が、軍勢を率い山の手を進撃することになっていた。そ
して池田(恒興)殿と称する他の一人は、同地方で最大の河川の一つである淀川に沿って進軍
し、ジュストは同じ山崎の村の間に留まることになっていた。ジュストは村に入り、明智がす
でに間近に来ているのを知ると、まだ三里以上も後方にいた羽柴に対し、急信をもって出来う
るかぎり速やかに来着するように(と要請した)。一方、小数でありながら出撃することを欲
し、敵(との一戦)を待てない味方の兵士を彼は抑制していた。
右近殿は羽柴の軍勢が遅延するのを見、自ら赴いて現下の危険を報告しようとしたが、まさ
にその時、明智の軍勢が村の門を叩き始めた。そこで右近殿はこの上待つべきではないと考えた。
彼は勇敢で大度の隊長であり、デウスを信頼し、戦闘においては大胆であったので、約一千名余
の彼の兵とともに門を開き敵を目指して突撃した。…」
明智側の前線の位置が山崎のやや京都よりである事の不自然さと、摂津三将が先陣であった
ことを確認。
【初戦の後】
58章
「この最初の衝突が終わると、ジュストとの間隔を置いて併進して来た二人の殿たちが
到着した。そこで明智方は戦意を喪失し、背を向けて退却し始めたが、敵方がもっとも
勇気を挫かれたのは、信長の息子と羽柴が同所から一里足らずのところに、二万以上の
兵を率いて到着していることを知ったことであった。だがこの軍勢は幾多の旅と長い道
のり、それに強制的に急がせられたので疲労困憊していて、(予想どおりには)到着し
なかった。」
戦意喪失の原因が援軍の到着程度であったのなら、明智の意思が兵士に理解されてない
ことを端的に表している。
【勝利の日時】
58章
「…この勝利は光栄ある童貞聖母の訪問の祝日の正午に行われた。」
天正10年6月13日は、ユリウス暦では1582年7月2日月曜となり、「聖母の
御訪問」の祝日であったらしい、グレゴリオ暦では同年7月12日に相当する。
ホームページの先頭へ