
中国大返しの主な川
中国大返しにおける、川と渡し
中国大返しにおける、主な川については右図
を参照して下さい。
全行程は、詳らかになっていませんが、ほぼ山
陽道、で間違いないでしょう、私見により、西
宮以東は津戸中道、尼崎ー伊丹道、吹田街道、
再び、津戸中道としています。
渡しに関する記述は専ら江戸時代の資料しか
残っていないうえ、平時の旅人や一般の人が使
ったものであり、戦国時代のまして行軍の場合
にどれほど参考になるかは解らないが一覧を示
しておく。 「中国大返し、川と渡し一覧.PDF」 「同(Excel)」
農民に川中に列を成させ、其の肩につかまり、兵士が移動したと言う
ような表記もあるようだが、何れにせよ人の背が立たない所を武器や、
弾薬、弓矢、その他装備を携帯した状態で、泳いで渡ることは不可能と
なるので舟渡とならざるを得ない。
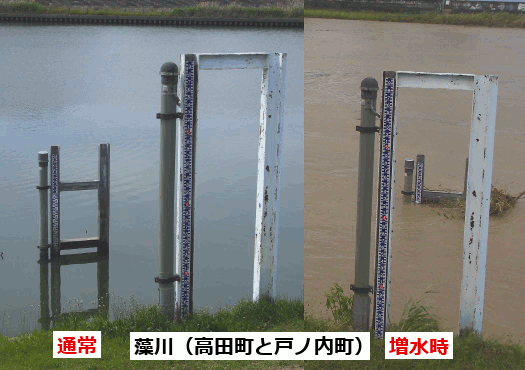 舟渡か、徒歩による渡しかは、行軍の速度に大きく関係する。移動速
舟渡か、徒歩による渡しかは、行軍の速度に大きく関係する。移動速
度だけを考えるなら、舟渡しを避けたいであろう、為に渡しの種別を、
上記の一覧に河川名と共にあげた。
当時の船に関して、信長の作った大きな軍船などの建造技術はあった
ものの、川渡しに用いる最大の船は、「高瀬舟」の一種、平底のもので、
乗員数は最大でも数十名であろう。(一万余人の兵士に対して延べ1千
隻必要とする容量である。) 【参考】高瀬舟の説明へ
今に残る江戸期の渡しの記録では、渡し船は多くても数隻しかなく、
戦国時代にどの程度の数を集めることが出来たかは検討していない(自
軍で所有した分、周辺から徴用した分、四国渡海用の船を流用の為に、
回航したなど)。
尚、川の性質上、梅雨時の大雨の後の流量は渡河方法の決定の為に大
きく影響する。川の状況を推測するため、参考として「藻川(猪名川)」
の大雨後の写真(右図 水位140㎝上昇)を添付しておく。
詳細は『津戸中道と猪名川渡し』藻川の水深を参照。
【出典等】
地図部は「国土地理院ホームページから」参照している。
図中の川幅と水深は、備前国部は、天保絵図、播磨、摂津国部は元禄絵図より参照。
参照先 :国絵図は、
「国立公文書館デジタルアーカイブ」の絵図からや
その下位の地域別の近畿等から。
【参考】
渡し船と同一であったかどうかは不明であるが、
旭川の歴史・文化に「高瀬舟」の1頁に説明があります。
国土交通省岡山河川事務所の
「旭川の歴史・文化(テーマ別)国土交通省 中国地方整備局 」PDF参照。
ホームページの先頭へ


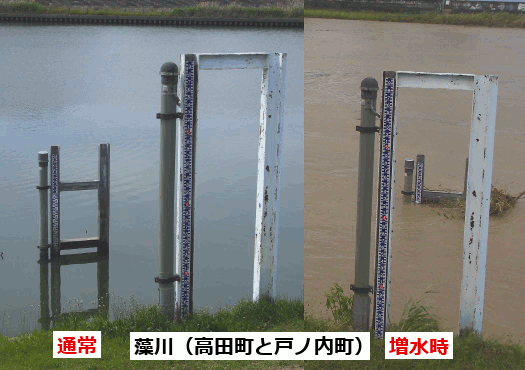 舟渡か、徒歩による渡しかは、行軍の速度に大きく関係する。移動速
舟渡か、徒歩による渡しかは、行軍の速度に大きく関係する。移動速