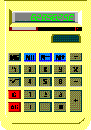
WEBMASTER の 今週の述懐 . . . . .
「お金」シリーズ 3 ・・・ "コンペ "(前段)
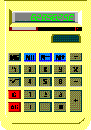
コンペ(設計競技)に我々建築家が参加するのは仕事が欲しいからだけでしょうか?
コンペゆえの 無償 を覚悟で
夢中になって 徹夜を重ねるのは、単なる「契約の勧誘」なのでしょうか?
締切りが近づくにつれ 同時に苦闘しているであろうライバルたちと共有するに至る
あの肉体的限界の中での夢遊病的 高揚感は 結局
参加者多数の 壮大な無駄なのでしょうか?
いや
審査結果が納得の行くものであれ、その逆であれ、
コンペには「建築の謳歌」が一つの約束事として存在しているはずです。
それなのに 最近 施主のみが単独で 審査する 住宅「コンペ」が二つ出現しました。
建築主が自分の気に入った案を選り取り見取りの
要するに 基本設計 大安売りです。
その内の一つはWEB上にあり、そこの掲示板で以下のようなディスカッションを
私は持ちかけたのですが、ある程度の行き来の後、結局 しばらくのブランク中に
消去されてしまいました。 ・・・・ こちら側のみの控しか残っていないので
先方のメンバーの方たちの書き込みは(引用のない部分は)ご想像下さい。
(3月28日記)最近、先方に保存のあることが判明しました。
先方のボードの「現在保存件数」の対象からは外れていて
ほとんど気付きにくい状態だったのです。
先方も意図的に消去したのではないわけです。
現在は気付きやすくしてもらってあります。
こちらの「述懐」にては
論旨を読みやすくする必要上の、私自身の発言順序の入れ替え部分等がありますが
手持ち控から議論の流れがそのまま表現されていることは下記リンクでご確認頂けると思います。
http://www4.big.or.jp/~karasu/housecom/dis/log1.html
1
このサイトの善意は十分理解させて頂いているつもりです。
その善意とご努力には敬意を表します。
しかし、コンペを名乗るからには社会的影響と責任とが生じます。
もとより参加報酬のない公開競技が社会的に正当性を持つのは、
その建物が持つであろう公共性ないし一般性が担保され、
ひろく応募者総体の努力の集積が文化的ストックとなり、
建築(Architecture)の到達点を少しでも高め得る事が想定される場合です。
建築家は相互に切磋琢磨し、負けても十分学び、そのためにこそ、
コンペの審査員はその過半を建築家とし(UIA)、結果は公開されねばならない。
そうでなければ、建築主側の身勝手に終わってしまいます。
施主と設計者の出会いを、ハウスメーカー的「無料設計」の嘘に立脚させる事、
すなわち成約物件で十分コストを回収する工事業者の「営業的」設計と同列に
参加者のスタンスを(結果的に)強いる事、
もっと端的には「プリント代 0円」の延長上にて、仕事を求める事、
これらがこのサイトの目標ではもちろんないはずです。
しかし日本の現状では結果としてそうなる。
建築家は(建築設計者は)襟を正して、筋を通さないと、己の地位を失います。
私だってもっと作品を作りたい。だからこうした企画には筋が通れば参加させて頂きたい。
けれどこのフォーマットはだめです。
とにかく職業倫理への配慮が全く不足していると思います。
みんなで、建主と設計者との出会いの、公正なあり方を議論し煮詰めるために
このサイトに期待したいところです。
がむしゃらに仕事を求めるためのサイトになって欲しくないですし、
仮にそうなると社会的に有害と言わざるを得ません。
2
K>「コンペを名乗るから〜」-コンペではありません。ハウスコンペです。
逃げです。これではディスカッションにもなりません。「住宅無料設計サイト」とされたら?
K>あなたの捉える「建築」では、建築は一歩も前に足を踏み出せません。
あなたがすべての建築家の様々な努力に対しそう言い切れるなら、
それはあなたの「建築」に対するコンセプションの問題です。
「設計者は間違いなく建築を愛してます」と、あなたが言うときの「建築」にも同列の
アーキテクト意識はあるはずです。
あなたのパースペクティヴがどのように優位だと言おうとしているのか判りません。
建築設計競技が建築家同士の狭い世界を体言していると言いたいのなら、市民への開示が現状で
最もマシなのがコンペであること、ドイツや北欧の市民的関心を知って欲しいこと、
「建築家同士の狭い世界」の結果も歴史の中で、かなりの率で市民的定着を得ること、
いま市民参加のまちづくりが建築家にとってもホットなテーマであること、
等々を、別な場で議論したいものです。
ここでは住宅がポイントとなりましょう。
上述のような公開コンペに「私的住まい」はなじまない、これなら判る。
K>それが住宅ともなるとなおさらです。
K>住宅は施主に属します。「建築主側の身勝手」に終わって大いに結構です。
住まい方は施主の身勝手で当たり前です。
ただし街並みは公共のものです。
そして設計報酬を正しく支払うのは、施主の社会的義務です。
(無料の設計契約は違法ではありませんが別問題です。)
施主も設計者も等しくハード・ソフト両面にわたる公共的責任があるはずです。
もとより住宅設計は経営的に儲かるものではありません。
まぎれもなく建築家は住宅への「愛情」で仕事をしています。
そうした日本の設計環境をさらに圧迫することで、結局損をするのは市民一般です。
K>ハウスコンペは、施主と設計者の出会いを、非ハウスメーカー的「無料設計」
の本当に立脚させます。設計者のボランティア精神にのみ支えられています。
仕事が欲しいボランティア精神というところですか。
もし否定される自信のある方は、設計・監理すべてをボランティアでやる気に違いありません。
K>あなたみたいな方は雑誌に載ることを目標にしこしこ作品づくりに励んで下さい。
そうすることで「建築(Architecture)の到達点」はきっと高まるでしょう。
このディスカッションにとっては場外乱闘気味です。
あなたはご自身の作家性を全否定できるのですか?
私は住宅と言えども創ることの顕名性を大切にしたい。
私の中でそれを否定したら欺瞞になる。
よい作品を作ることと、雑誌に載ることとは同義ではありません。念のため。
K>「建築主側の身勝手」を否定するには、行政から見直さなければ道はありません。
不動産の私有を認めないような。
論点がずれています。ずれた後の論旨も内容不明。
K>ハウスメーカー的と中傷させる訳には行きません。
民法上の「契約の勧誘」に該当し、まさしくハウスメーカー的です。
その自覚がないならもっと事態は深刻だ。
繰り返すようですがこのサイトを作られた際の善意には敬意を表します。
3
追伸
もし施主と設計者の出会いに資することをWEBに期待するなら、
ひとつの提案として、
1. アクセスしてきた施主に
参加希望設計事務所がそれぞれポートフォリオや住宅観を提示し、
2.
施主は考えの合いそうな設計者に面接をする。
3.
施主がどうしても案を見たい場合は、実費清算で各案を注文し比較する(WEB外で)。
これが妥当な線では?
「アイディアはただで手に入れて当たり前」的な、日本の恥ずべき土壌を皆で改善しませんか?
「不安だから案をまず見たい(設計者に出させる)、気に入ったら先に進める、気に
入らなかったら金は払わなくて良い」と言う、主としてハウスメーカーによって刷り込まれた
目茶苦茶な観念、設計行為の軽視を、私たちはどこかで是正しなくてはなりません。
4
K>「...改善しませんか?」- 確かにそうだと思いますけど、名もなき設計者の
未知の案に対してなかなかお金は払ってくれないと思います。
K>実績のない20代の設計者でも案を出すのは自由というのがこちらの思想
実績のない(主として20代)設計者にもチャンスが欲しいというのは良くわかります。
1.
しかし実績に代わる
能力の提示方法を、ハウスメーカー的「自分の案で営業」、
即ち施主の条件に対し骨子案を、無償で、しかも皆がオープンな場で
提供することに求めるしかないと考えるのは、早計だと思います。
2.
施主側も着手金程度は参加謝礼総額として用意するべきでしょう。
さもなくばコンペでなく一種の営業合戦になります。
ひとりあたまの「スケッチ程度」に見合う額を確保するために、
参加人数制限も考えられます。
3.
住宅設計は奥が深く、現場も甘いものではありません。実績を求められても当然です。
設計者の独立時期はその人の自己責任で決めたことで、
実績がないのは社会のせいではありません。
一方、WEBを通じて社会に「アイディア=無料」を振りまくのは
社会(特に建築界)に対し少し酷ではないですか?
なぜ最初からお金を払ってくれないだろうと諦めるのでしょう?
見る目のない(スケッチ代も払わない)依頼者なら相手にしなければ良いではないですか。
いま20代の方々には、先輩たち以上に志を高く持って頂きたい。逆ではさみしい。
K>イメージは、スケッチ程度なのです。設計者にもあまり負担にならないような。
なおのこと、施主にもあまり負担にならないわけですから、有償とするべきでしょう。
K>設計条件に応じた案を募集し、”どのような家が建つのか”ある程度つかめた段階で、
(トップページより)
こうした口上が、ハウスメーカーとスタンスが同じという判断を余儀なくします。
施主コンペの実例群からいくつか。
a.「いわきの家コンペ」は参考になると思います。
審査員は建築家・施主・他。
江口氏の日経発言も要チェック。
b.
施主のみが審査員という他の住宅競技にも建築家がアドヴァイザーに居ます。
友人がそのアドヴァイザーだったとき誘われて一回だけ応募してみましたが
参加者の多くがシステムに不満を抱いたようでした。(友人のせいではありません)
私も5案くらいに絞るのは、建築家審査員の役割だと感じました。
その友人も今では「やはり審査員に建築家を加えるべき」と言っています。
K>住宅というテーマにあなたのいう建築家を審査員とするようなコンペは
絶対に応用できない
昨日書いたように、公開コンペに「私的すまい」はなじみにくいのは事実ですが、
絶対というのはちょっと......
。もう少し吟味されたら?
K>現状は本当に設計者のボランティア精神に支えられているんです。
Kさんのボランティア精神は信じます。
でも「案で営業」をボランティアの美名でくるむのは、いただけないな。
続きます。 (^_^) 安達
98/03/08