神戸市東灘区御影本町2丁目5 東西の道から北に道が分岐する四辻の北西部に南を正面に建つ
(国道43号線北側、東御影交差点と浜中交差点の中間)
山型角柱 116x30x19㎝(頂高10㎝)
N34.711401 E135.258678
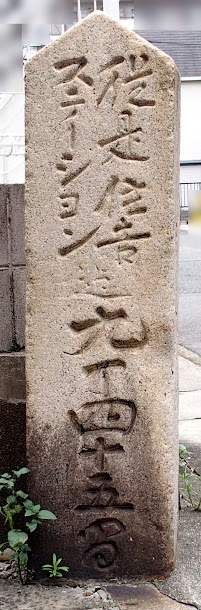



南面
┌─―――――――――――――――――┐
│従是住吉 │
│ 迄九丁四十五間 │
│ステーション │
└――――――――――――――――――┘
(迄の旁の「乞」は「占」となっている)
東面
┌─―――――――――――――――――┐
│ 嘉納治良平 │
│ 周旋人 │
│ 宮田為介 │
└――――――――――――――――――┘
北面
┌─―――――――――――――――――┐
│(なし) │
└――――――――――――――――――┘
西面
┌─―――――――――――――――――┐
│明治十四年六月建之 │
└――――――――――――――――――┘
(明治十四年は西暦1881年である。)
(『神戸の道標』山下道雄、神戸新聞、1985年刊では東灘区№14)
(Wiki住吉駅に「1874年(明治7年)6月1日開設」とあり、明治14年建設と矛盾は無い。)
(この地点から9丁45間=1060m真っすぐに北に進むと現JR東海道線の北辺りとなり、やや東の、現住吉駅
までだと1.3㎞となり距離が一致しない。間数まで表現している事を考えると数mの誤差程度で考えねばならず、
この不一致は看過できない。住吉ステーションが現JRの住吉駅であるとすると、移設されたものと思われる。浜街
道(現43号)沿いでピタリの距離を示すのは、ここから東350mの東灘区住吉南町5丁目1-1
N34.711195 E135.262505
辺りの四辻北西部で「住吉南町4の西側道標」の北側になる。
下記に有る解説板の「西国街道」をキーに当時の西国街道を見ると、東灘区御影本町2丁目17-2の南東角
N34.714318 E135.257438
辺りとし、阪神御影駅の東を北に進み、旧西國街道で東に向かい、住吉東町に入る手前を北折すれば一致する。
此方は現在地より北へ350mの地点となり、距離的な優位性は見られないが、移設に当って、「明治の頃の西国街道
なら、浜街道にあったものだろう」として此処に移されたと穿った見方をすれば、こちらの可能性が高いか。
因みに、阪神御影駅は明治38年(1905)4月開業らしく当道標建設時には駅は無かったと思われる。)
(「周旋人」の表現は「三田市東本庄」明治30年や「尼崎市東園田町4」大正5年がある。施主であろうか。)
(西側にある解説板)
住吉ステーションの碑
明治七年に大阪~神戸間に鉄道が建設され、
その間に神崎・西宮・住吉・三ノ宮の駅が設けられた。
この碑は、西国街道を通る旅人に住吉駅を教える
ために、明治十四年六月に建てられたもので、表面に
「従是住吉ステーション迄九丁四十五間」とある。
東灘歴史掘り起こし隊
東灘区役所
(明治43年測図の地図では、西国街道は現阪神電車の通るここより北の道となり、現道標のある道は御影村内を通
る細道として描かれているが、旧西国街道浜街道であろうと思う。よって解説板の表現は的を得ていない。
現在地から東に浜街道を採れば、上記「住吉南町4の西側道標」を過ぎ、松原交差点で明治の西国街道と合流後
「魚崎西町3の道標」へと続く。)
 |
 |
 |
| 【1.道標を北に望む |
【2.道標を南に望む |
【3.道標を東に望む |
| 奥(北)阪神御影駅へ |
左右は現43号 |
奥(東)西宮へ |
| 左右は西国浜街道】 |
右(西)神戸へ】 |
左、住吉駅へ1.3km】 |
 |
 |
 |
| 【4.道標南面拡大 |
【5.道標南面拡大 |
【6.道標東面拡大 |
| 「従是住吉…」のうち |
「九丁四十五間」 |
「周旋人」 |
| 「迄」の彫が浅い】 |
「間」=1.8m】 |
新しい表現か】 |
 |
| 【7.道標西に建つ解説板 |
| 東西の道は江戸期の浜街道 |
| 明治の西国街道ではない】 |
 |
| 【8.神戸市東部の道標】 |
文字ずれ時はブラウザの幅や「Ctrl」と「+」、「-」キーで倍率変更等して下さい。
↑先頭へ