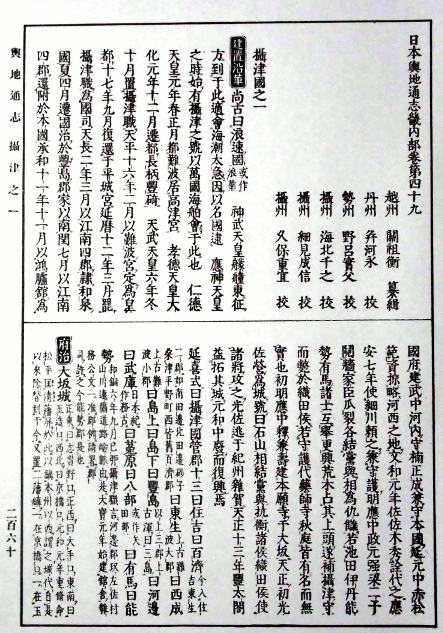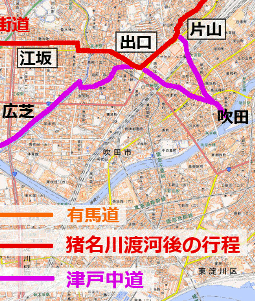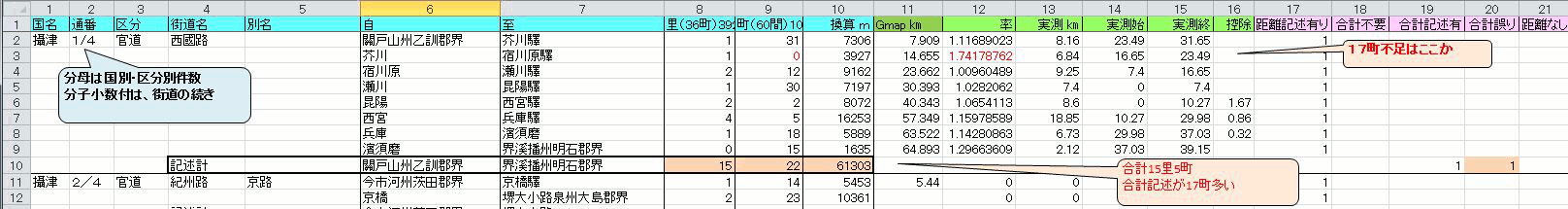五畿内志について。
1.【収刊本】
2.【五畿内とは】
3.【記述に関して】
4.【街道に関する記述】
【収刊本】
刊本として、
『大日本地誌大系34・泉州志 第一巻』 雄山閣 蘆田伊人 昭和51年12月15日発行
があるが、それより、一部分を掲げると
一 本巻には、『五畿内志六十一巻』、及『泉州志六巻』を収めたり。
一 五畿内志とは、日本與地通誌畿内部の略称にして享保(1716~1736)中關祖衡、
並河永等の編纂に係れるものなり。
…幕府の許可を得て、畿内の各処を巡歴し、拮据六年
享保十九年二月(1734年3月)畿内部六十一巻を完成して、之を幕府に進献せり。
體例一に大明一統志(注1)に倣ひ、
…凡そ畿内の地誌中編纂の統一され、而かも精細を盡せるものとしては、
本書を以て嚆矢と為すべし。
…永字は宗永後尚永と改め…元文三年三月歿す。歳七十一。
とある。
【参考】
国立国会図書館ウェブサイトの近代デジタルライブラリの、
『日本古典全集第三期14 五畿内志、下巻』 正宗敦夫 編纂 昭和4年版(摂津志は71コマより)
で見る事が出来る。
同じく、
『大日本地誌大系18 ・五畿内志泉州志』 雄山閣 蘆田伊人 昭和4年版(摂津志は138コマより)
を見ることが出来る。
【補足】
時に参考としたのではないかとされる、
『摂陽群談』は、岡田溪志が伝承や古文献を参照に元禄十一年(1698年)から編纂し、同十四年(1701年)に完成した
とあり、28年程前に遡る。こちらには、街道に関する記述はない。
巻第二の川邊郡の各村の記述が終わった後に、
「以上十二郡也、凡村附は、山川・郷河・道路の隔て、如も遠近有て、隣里を数量る事巡ならず。
西の国境に計て、亦東に走る。南北も亦同じ。假へば山頭より猥に礫を抛て、如拾之。是故に村里の次第、不能詳。」
のように、書く気が無いとおもわれる。
又、巻九、城郭の部に、
「有岡古城 同郡池田村にあり。所傳、池田勝入信輝在城、息三左衛門尉輝政兵庫に在城す。
池田筑後守充正城跡、各残其威儀。池田古城とも云へり。」
「伊丹古城 同郡伊丹にあり。所傳荒木摂津守、構之古城と云へり。」
とある様に、記述に誤りも見受けられる。
注)有岡古城=伊丹町が正しい。
【参考】
『摂陽群談』有岡古城は、国立国会図書館ウェブサイトの近代デジタルライブラリの、
「大日本地誌大系、第九冊」コマ96を、里程は21コマを、参照、
又、伊丹市ホームページの「有岡城」にも詳しい。
【五畿内とは】
1.山城(京都府)
2.大和(奈良県)
3.河内(大阪府)
4.和泉(大阪府)
5.摂津(兵庫県)
の五国を言う。
【記述に関して】
最初に「図版」、巻名、纂輯者、校正者、国名。
1.建置沿革(創設とうつりかわり)
2.府治(役所施設)
3.疆域(くにざかい)
4.路程(みちのり)
5.官道(今の国道か?)
6.間道(わきみち?)
7.航路(船の道)
8.形勝(地勢)
9.風俗(世のならわし)
10.祥異(めでたいことと異変)
11.郡名(国の下にある)
12.郷名(郡の下、村落を合わせたもの)
13.村里(町や村)
14.山川(池、岡、井、堤も含む)
15.關梁(駅、橋、渡し、津、等)
16.製造(炭、草履、等)
17.土産(野菜、竹、雉、蛤、等)
18.神廟(主に神社)
に分けて記述され、必要により
城池、文苑、列女、僧英、氏族、陵墓、佛刹、古蹟、その他、
等も書かれている。
【街道に関する記述】
「疆域」の中に、「官道」と「間道」に分けて書かれており、
○印の次に街道の名称が書かれ、「自」「至」、距離(里、町)、
場合により、「経由地」が小さな字で書かれている。
但し、漢文による表記のため、理解に苦しむことままあり。
【例】(右図参照、○の中に数字があるのは筆者の書き込み。)
『○三国嶺丹播摂三州交界仍名路通丹州小津村至大川瀬二十九町』
(仍は、よっての意味)
とあり、
小津村(丹波)ー大川瀬(摂津)が29町なのか、摂州の境界ー大川瀬なのか解りにくい。
おそらく意味は、
「三国嶺は、名前の如く、丹波、播州、摂津の三州の交わる地点で、
丹波の小津村に通じており、州境から、大川瀬村まで29町である。」
とすると、
後者(摂州の境界ー大川瀬)であろう。
尚、1里=3.904㎞ 1町=107.5m 相当で、29町=3117.5m。
又、36町=1里となる。
【距離に関して】
各地点間の距離は、作者が実測したもので無く、何か別の資料より転記したものと想像する。
理由として、
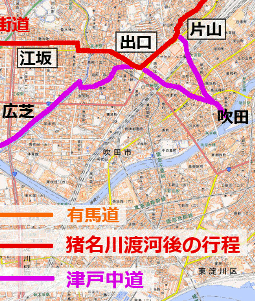
津戸中道吹田部分
1.津戸中道の記述が大きく二つに分けて書かれており、この道(西宮から芥川へ至る)を、
明治の地図に当てはめて見ると、出口村から吹田(南高浜町、吹田の渡し地点)を通過し、
片山村へ出ると、遠回り(行った道を引き返すような感じ)になり、吹田村を通る必要は感
じられない。
しかし、吹田から亀岡街道が出ていて、距離が分かり、西宮から吹田への距離も分かるが、
出口ー片山間が分らないとした時は、一度、吹田に行、更に吹田から片山へとしなければ、
合計が書けなくなる。
よって、二つに分けて記述し、合計も求めたと思われる。
尚、津戸中道を、吹田市出口町ー吹田市片山町を直行と比定し、その距離を現在の道路で
実測すると、吹田経由の場合より、約2km短くなり、摂津志九里二十八町からすると、誤差
が大きくなりすぎるのも根拠とする。(他街道と比較した場合)
2.行程中に大きな川の舟渡しが含まれる場合、川幅が距離に含まれていない様である。
五畿内志作成時に実測したのなら、凡そであっても距離に加算するか、渡しだけの記述が
あってもよさそうである。
当時の技術で川幅を計るのは可能であったようで、実際、元禄絵図には、川幅が書かれている。
これを、五畿内志に書かなかったのは、オリジナルの資料が手元になかったものと想像する。
因みに、渡渉(歩いて渡る)と思われる部分は、川幅も距離に含んでいるようだ。
これは、記述の正確性を見る為に、実測値と比較して得た結論である。
詳しくは、西国街道検証を参照。
3.巻頭に、「幕府の許可を得て、畿内の各処を巡歴し」とあり、六年を掛けたとあるが、
実測を行った場合には、とてもこの期間内に終わるとは思えない。
確かに、この書にしか出てこない「津戸中道」等は、現地を訪ねない限り蒐集出来ないと
思うが、巡歴は測量でなく、文字通り”めぐりあるき”し、手元の資料の検証を行ったも
のと思う。
では、何を資料(書き写しの原本)としたのか、「道帳」であろうか。
正保国絵図作成の折に、郷帳と共に作成された様で、他国の部分であるがその書き様は、
国境から、最初の村、更に次の村のように各村間の距離が詳細に書かれている。
許可を得ると共に、写しの作成も許可されたのではないか。
奥州南部領の道帳では、距離記述の仕方が、必ず隣りの村までで書かれており、経由地を
間に挟むような書き方はされていない。道帳の書式も統一されていたはずで、もしこれを
参照したのなら、「五畿内志」の書き方は、それをサマリーした様になっている。
道帳については、「津戸中道」【参考4】」を参照。
【距離記述の誤りについて】
詳細は別項「津戸中道、5.距離記述の検証」を参照されたいが
要点のみ書き出すと
1.五畿内志には、
全道数が、 235件(別名含まず、街道に続く道は件数に含む。)
街道名称が、 213件、
距離の記述が、 352件、
合計が、 45件、
合計の不一致が、 8件
ある。
合計が不一致の内訳をみると、
a.明細記述に誤りがあるもの、3件
(合計に足りない分を明細に、足すと実測距離に近似するもの)
b.合計に誤りがあるもの、 2件。
c.誤差の範囲にあるもの、3件。
(合計が1町多いが2件、山間部(長距離)で誤差が3%が1件)
となっている。
実測距離は、五畿内志記述距離に比べ、平均+9%の誤差となった。
(記述(m法に換算)より、実測の方が長いとの結果となった。)
詳細は、「五畿内志街道一覧」の項参照
(吹き出しに、誤りの内容等が書き込んである。)
2.この誤りの内容を検討すると
上記cに関しては、防ぎ様がないと思われるが、
a.b.に関しては、各州別に校正者が居り、六年の歳月を掛けたにしては、
多すぎるし、単純な誤りの様にも思える。いかに電卓の無い時代とはいえ、
算盤はあったであろう。
この様なミスは単純に書き写す場合に多く発生すると思われる為、前述の
転記説の一要因とした。
但し注意しなければならないのは、現存する「五畿内志」もオリジナルでは
無いであろう点である。
オリジナルでは正しく書かれていたものが、筆写の過程でこれらの誤記が生じた
ものなら、伝播の過程で誤りが取込まれてしまったとすべきかも知れない。
何れにしても、『距離を読み解く場合には、一部の値に修正を加える必要が
ある。』と結論する。
例】西国路、明細記述の「芥川-宿川原駅」1里は1里17町とすべき。
前述『五畿内志、下巻』の74コマ、503頁左
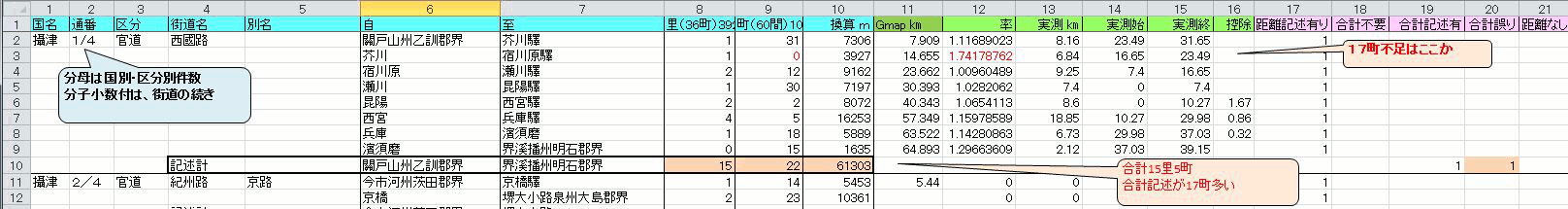
注1.大明一統志(だいみんいっとうし)
中国、明朝の全域と朝貢国について記述した地理書、全90巻、天順5年(1461年完成)
李賢らの奉勅撰(天順帝(英宗):明朝第8代皇帝)。
その書名、体裁など『元一統志』に倣っている。
巻頭序文に次いで図が配置され、本文は京師、南京、中都より十三布政司、
そして朝貢国の順でその地誌が記述されるが、記事は往々誤りあり。
「世界大百科事典」「ブリタニカ国際大百科事典」等より。
ホームページの先頭へ