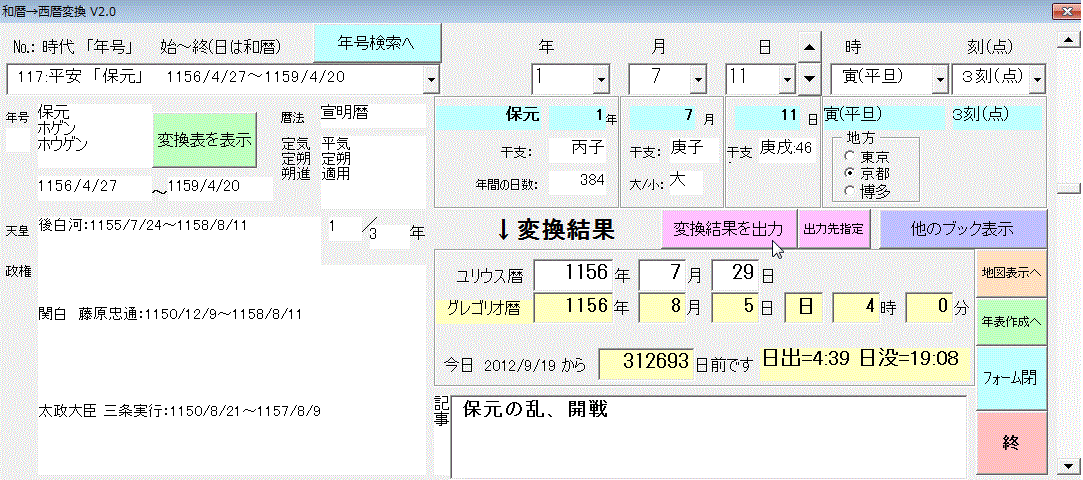本能寺の変、家康の伊賀越え、秀吉の中国大返し、に関して
この三点を、時系列的に記述した本はあまり無いように思います。これを一つの時間軸と、事象発生地点を地図上にプロットすることで、何か見えてくるかと試みました。
●結論から書いてみます。
1.伊賀越えは、後世、チョット大げさに作ったもの?
2.穴山梅雪は、農民に殺された、に疑問?
3.中国大返しは、秀吉本人の都合?
などが見えてきました。
尚、各出来事は、一覧にまとめています。
地図への表示は、数時間単位にしたかったのですが、表示制限の為複数に分れていたり、1日の記述が無かったりしています。
1.伊賀越え、
Q1.家康一行を討てと、誰が指示したのか?
答、1.光秀なら、いつ指示したのか、又指示を受けたものが、それを受け入れる事が可能であったか?
更に、打ち取る準備が可能であったか?
例えば、光秀配下の本城惣右衛門覚書には、軍事行動に当たって、家康討伐と勘違いした状況があった。
よって、光秀側一揆なら、襲撃の可能性ありと見なせる。
2.光秀方以外の信長方(家康敵対方)が、独自で討とうとしたのか?
例えば、フロイスの「日本史」の中に、「光秀の兵士たちは、変の行動は、家康を殺す為であろうと考えた」とある様に
光秀以外の信長方にあっても、「家康を殺す」下地が出来ていたのか。
3.指示を受けたのではなく、「信長方」に対しては、全て襲撃する状況(一揆を起こす)にあった為か?
変の発生を聞くだけで、信長反勢力方は、好機と捉え、手当り次第攻撃を加える状況であったのか?
4.光秀にとっては、今後の対抗勢力となることがハッキリしていれば、家康を討ち取るように指示するであろう。
味方に付けようとしなかったのか?
Q2.支配地域と人物の系統。
1.伊賀地域
北畠(織田)中将信雄、天正9年(変の前年)伊賀の柘植、佐那具等に「服部党」を討ち、信長より三郡の領地を受ける。(武功夜話巻九)
この人は、「変の直後、近江国甲賀郡土山まで進軍したものの、戦わないまま撤退した」り、
「10月に、東国で家康と後北条氏らが武田遺領を争った、天正壬午の乱で、双方の和睦を仲介した」ように、家康を打ち取る積極的な意思は、
なかったとみてよさそう。
2.大和地域を支配していた人物は?
筒井順慶で、信長軍にあっては、外様であった。天正8年佐久間信盛(信長の家臣団の筆頭格)の追放後、大和全域を支配。
変の直後には、「洞が峠を決め込む」の諺の元に成った様だが、辰市近隣まで派兵して陣を敷いた。
3.山城地域を支配していた人物は?
村井貞勝で、織田家の政務担当で、変により死亡。(光秀と見なす。)
4.河内
北河内、野間長前、池田教正、多羅尾常陸介(三好義継を(直前まで敵対)を裏切った家臣。)
南河内、三好康長(7年前の降将)
5.近江
織田信長、変により死亡。(光秀と見なす。)
6.伊勢
北畠(織田)中将信雄、
7.大坂
神戸信孝と丹羽長秀が四国出征準備中
Q3.
Q4.変後に、光秀に協力した人物とその支配地域は?
1.近江山本山(湖北)の阿閉貞征が長浜城
2.若狭の京極高次も長浜城
3.若狭の武田元明が佐和山
4.淡路の管氏が洲本
5.亡命中の土橋重治が雑賀
(鈴木重秀が6月3日夜に雑賀より織田信張の和泉岸和田へ脱出)
6.筒井順慶
Q5.穴山梅雪は誰に討取られたのか?
答、1.3月1日に武田方総崩れを見て寝返ったばかり。家忠日記より
家忠は、深溝(ふこうず)三ヶ根駅の北に居城していた。岡崎まで6㎞
6/3京の酒井忠次から、家康帰国後西国出陣を、伝えてきた
同酉の刻変の発生が大野(愛知県常滑)から入った。(水野氏からか)
6/4岡崎と緒川から、変は事実であり、家康が堺にいたことを知り、岡崎に向う。
岡崎で家康の消息を知り、大浜へ迎えにいった。
2.家康の気持ちで考えてみよう。
1.本能寺の変の知らせを受けて。(発生だけでなく、信長が死亡した情報を知っていたとする。)
1.光秀に味方する方向で、光秀の元に行く。
最初に考え付いたが、行けば殺される可能性が高いと部下に説得される。
確かに、TOPが代わっただけと考えるなら、この方法しか無いが、冷や飯食わされるならまだしも、殺される可能性は高い。
又、ここで旗色を決めるには、時期尚早であるのは素人目にも明らかである。(他の有力武将も同様な決定が多かった。)
2.取敢えず、自国に帰り今後を考える。
3.この近辺で、身柄を安全における様な状態にする。
2.方針決定後。
3.移動速度について。
「一般的に、重要情報の伝達は、有能で健脚な家臣が使者に選ばれ、…江戸時代とは違い街道・橋などの交通手段が完備されていない当時、その上敵地を通過しなければならない場合や悪天候などの自然条件も考慮すれば、…遠隔地間では、健脚の使者でも、一日五十キロメートルをコンスタントに進むことなど不可能だったと思われる。」※1とあるが、本能寺の変発生の知らせを毛利へ知らせる使者が、秀吉に捕えられたのが2日後であったことをみると、一般的な移動距離を当てはめることは間違いである。当時とはいえ、戦争にあっては、情報収集伝達が重要であったのは変わりない。
※1:「証言 本能寺の変」藤田達生
※2:乱の始まりが6月2日 未明、情報を掴んだのが6月3日夜から4日未明、(最大2日=48時間)で、距離で210㎞(京都沓掛から備中高松:高速道路経由)とすると、100㎞/日となる。
保元物語新訳 吉村重徳 大同館書店(青字「…」部分)から、日時に関する記述(赤字)を見つけ、
抜き出して、当ツールを使用した結果を表にまとめてみた。
尚、《…》は段落見出しを示す。

巻之一《鳥羽院崩御の事》
はじめに、年号のわかる記述を探すと、
「明くる四月二七日改元あって保元とぞ申しける。
七月二日終に一の院隠れさせ給ひぬ。」
とあり、保元であることがわかる。
《新院御謀反の事》
「保元元年七月三日下野守義朝に仰せて、…」
この辺りから、事が起こり始め、
《新院御所各門固軍評定の事》
左府(頼長)の問いに、為朝が答えて
「『…或は城を攻めて敵を亡すにも、皆利を得ること夜討に如くこと侍らず。…』
『未だ天の明けざらん前に勝負を決せん條何の疑か候ふべき』」
《主上三條殿行幸附官軍勢ぞろへの事》
天皇が信西入道に問わせ、義朝申しけるは、
「『…即時に敵を従え、立所に利を得る事、夜討に過ぎたる事候はず。…』」
と答え、これにより、
「十一日寅の刻、官軍既に院の御所へ押し寄す。」
とあるように、夜討を先に仕掛けるのかがポイントになったようです。
しかし、この後の記述で「本当に夜討であったのか?」と疑問が生じた。
巻之二《義朝白河殿夜討の事》
 院側の頼賢と、天皇方の瀧口俊綱との対決の記述で
院側の頼賢と、天皇方の瀧口俊綱との対決の記述で
「川越に、矢二つ放つ。夜中なれば誰とは知らず、…」とある、
が又、天皇方清盛の郎等景綱と院側(鎮西八郎)為朝とが名乗り合いの後、為朝の射た矢が
景綱の子二人を死傷させたともある。
この様を見て、清盛は別の門へ向かおうとする時、これまた郎等の伊行が腑甲斐なく思い
『夜明けて後に傍輩の、八郎のいで矢目見んといはんには、何とかその時答ふべき。』
とも書かれているのを見ると、物語とはいへ、夜明け前であったと思われる。
しかしこの後、為朝と、伊行の対戦の記述には、『鎮西八郎此にあり』と名乗り、伊行に射掛けさせた後、
二の矢を番えている所を為朝が射落とすと、目視可能と思える光景も描かれている。
尚、本文中には、松明やかがり火を焚く等の記述は見当たらない。
《白河殿を攻め落す事》
「さる程に夜も漸く明け行くに、…」とあれば、薄明の頃か。
義朝の使者を内裏へまいらせ「『夜中に勝負を決せんと、揉みに揉うで攻め候へども、…
今は火を懸けざらん外は…』」とあるのは、やはり夜中である事を現している。
《朝敵の宿所焼き払う事》
「さる程に七月十一日寅の刻に合戦始り、辰の時に白河殿破れて、…」
「未の刻に義朝清盛内裏へ帰り参ってこの由を奏聞す。」
「…申の刻に宇治橋の守護の為に周防判官季実を差し遣はさる。」
とあり、初めて時間が分る記述が出てくるのだが、寅の刻に始まった合戦で辰の時に終わる間に、
名乗り合いや、為朝の矢を射る場面が矛盾しないか?等も調べてみたいと思った。
《関白殿本官に帰復の事》
「同じき十一日夜に入って関白殿、本の如く氏の長者にならせ給ふ。」
「子の刻ばかりに及んで武士の勧賞行わる。」
下の表を見ると、夜討ちといえども、日の出も近い頃のようで、特に「見てきたような嘘を言い」でもなさそうである。
又、本の解説のように「寅の刻」=4:00としたなら、一層よく見えそうである。
保元元年 和暦→西暦変換 表
| 和暦 月 日 時刻 | 西暦 年/月/日 時刻 | 出来事/事象 等 |
|---|
| 四月二十七日 | 1156/5/25 | 改元 |
| 七月 二日 | 1156/7/27 | 一の院隠れ |
| 七月 十一日 寅の刻 | 1156/8/ 5 3:00 | 合戦始り(本の注釈では4:00) |
| 七月 十一日 夜中なれば | 1156/8/ 5 | 為朝の矢で景綱の子二人が死傷 |
| 七月 十一日 夜明けて後 | 1156/8/ 5 | 伊行も為朝に射落とされる(仮定なので日出前) |
| 七月 十一日 日出 | 1156/8/ 5 4:39 | 日出 |
| 七月 十一日 夜も漸く明 | 1156/8/ 5 | 三條院に火を懸け |
| 七月 十一日 辰の刻 | 1156/8/ 5 7:00 | 白河殿破れる(本の注釈では8:00) |
| 七月 十一日 未の刻 | 1156/8/ 5 13:00 | 義朝内裏へ帰着 |
| 七月 十一日 申の刻 | 1156/8/ 5 15:00 | 季実を宇治橋守護 |
| 七月 十一日 日の入り | 1156/8/ 5 19:08 | 日没 |
| 七月 十一日 夜に入って | 1156/8/ 5 | 関白忠通本復 |
| 七月 十一日 子の刻 | 1156/8/ 5 23:00 | 武士の勧賞、清盛は播磨守に |
保元元年(1年)7月11日、寅の三刻 を変換中の図。
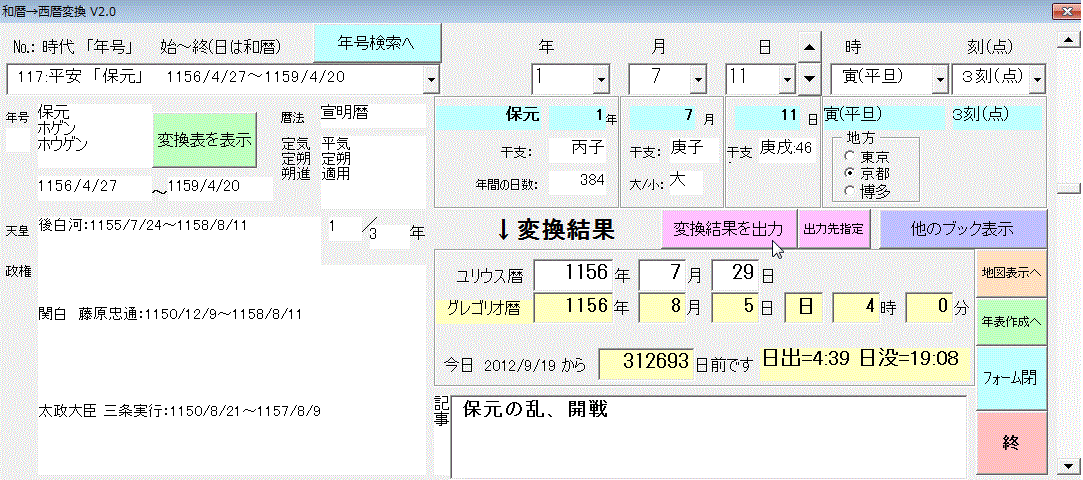
当ツールでは、子の刻の始まりを23:00としています。
よって、よく言われる「草木も眠る丑三つ時」が2:00に一致します。
●関連する場所を地図に表示してみました。
天皇方、上皇側でマーカの色を分けるとか、
「清盛」の位置を、時系列的に作成する等し
表示させると面白いかもしれません。

図をクリックするか、又はここ をクリックすると、別フレームに拡大表示されます。

 院側の頼賢と、天皇方の瀧口俊綱との対決の記述で
院側の頼賢と、天皇方の瀧口俊綱との対決の記述で