 |
てつまるくんの今日のひとこと |
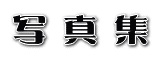 |
|||||
|
|
|||||||
| 帝塚山古墳のこと 2003/07/30 住吉区帝塚山西2丁目 |
二段築成の墳丘をもつ前方後円墳で、築造当初の姿をほぼ伝えている、市内唯一の古墳である。 復元される古墳の大きさは、墳丘長約120m、後円部直径57m、高さ約10m、前方部幅50m、高さ約8mである。(「新修・大阪市史」)。幅約20〜30mの周濠の痕跡が認められるが、完周はしていなかったと推定されている。 石室・石棺などの内部構造は不明であるが、円筒埴輪列や墳丘を覆っていた葺石(覆い重ねられた石)などが確認され、出土の埴輪片の特色から4世紀末〜5世紀初めに造営されたと考えられている。 なおこの付近には、かって大小の古墳が点在していた。−−以上門前案内板より−− |
||||||
写真左から
|
 |
 |
 |
||||
|
|
|||||||
| 日本綿業倶楽部のこと 2003/07/25 中央区備後町2丁目 |
文化庁の登録有形文化財を1つ見つけました。 中央公会堂から南に栴檀木橋を渡り、さらに適塾跡を横目に真っ直ぐ南に下ると左側に煉瓦造りの重量感のある建築物に出くわします。それが日本綿業倶楽部ビルです。 大阪の建築家・渡辺節氏により建てられたそうです。各部屋全ての様式が異なると言う贅沢な設計らしいが時間の関係等で拝見出来ませんでした。 予約すれば内部見学が出来るそうですよ。 (但し、第4土曜の午後のみ・無料) |
写真左から
|
|||||
 |
 |
 |
 |
||||
|
|
|||||||
| 露天神社のこと 2003/07/20 北区曽根崎2丁目 |
菅原道真公が太宰府に流される時にここで詠んだ和歌にちなんで付けられた露天神社が正式な名ですが、お初天神の方がよく知られているようです。1703年(元禄16年)この天神の森で平野屋の手代・徳兵衛と遊女・お初が心中をし、これを近松門左衛門が「曾根崎心中」として発表して以来このように呼ばれるようになったそうです。現在のこの周辺は最もにぎやかな繁華街で、ここに集まる若いカップル達にも縁結びの神様として人気の有る所のようです。時々イベントとして境内で骨董品市が開かれてるようですよ! | 写真左から
|
|||||
 |
 |
 |
 |
||||
|
|
|||||||
| 愛珠幼稚園のこと 2003/07/15 中央区今橋3丁目 |
日本で最も歴史の長い幼稚園で明治13年(1880年)の開園。現在の建物は明治34年の物らしく、どっしりとした御殿風の木造建築に、重厚な冠木門がさらに風格を添えています。 門前には、江戸時代に銅座が有ったらしく記念碑が建っています。銅座は明和3年(1766年)から明治維新まで、精錬と売買を統括していたそうです。 緒方洪庵の適塾跡とは背中合わせの位置に有ります。 |
 |
|||||
|
|
|||||||
| 緒方洪庵適塾跡のこと 2003/07/10 中央区北浜3丁目 |
この建物は蘭学者・緒方洪庵が弘化2年(1845年)に住居として買い受けて瓦町から移り住み、文久2年(1862年)に幕府の典医師として江戸に迎えられるまでの17年間に渡って、私塾(適塾と呼ばれた)を開いていた所です。洪庵はここで諸国から集まった門人たちに蘭学を教えて、幕末から明治にかけて日本の近代化に貢献した多くの人材を育てました。門人には福沢諭吉や大村益次郎など3000人も居るそうです。一般250円。月曜及び祝日の翌日休館。 |
写真左から
|
|||||
 |
 |
 |
 |
||||
|
|
|||||||
| 木村長門守重成のこと 2003/07/05 |
木村重成は、江戸初期の武将で豊臣秀頼の臣。 大坂冬の陣(鴫野にて初陣)に善戦し、和議の際、家康血判受取の使者をしたという事です。鴫野古戦場は現在の城東小学校付近。運動場の片隅に碑は建っています。翌年の夏の陣に豊臣方長宗我部盛親と共に徳川方藤堂高虎・松平直孝隊と激突。重成は戦死しました。(八尾市幸町・〜1615年) 若江南は重成の陣の有った所で、今は重成像が建っています。又、戦死地付近は現在公園になっていてその北の端に墓所が有ります。 この二つの地点間は約10分程です。 |
写真左から
|
|||||
 |
 |
 |
 |
||||
|
|
|||||||
| 【バックナンバ−】 ★2003/10★2003/9★2003/8★2003/6★2003/5★2003/4★2003/3★2003/2★2003/1★2002/12★2002/11★2002/10★ トップに戻る |
|||||||