 |
てつまるくんの今日のひとこと |
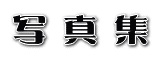 |
||||||
|
|
||||||||
| 陶器神社のこと 2003/10/25 中央区久太郎町4丁目 |
南御堂の西側に坐摩(いかすり)神社が有ります。この神社は神功皇后が安産を祈願した後に応神天皇が生まれた事から、安産・旅行の安全・家内安泰などの守護神として「ざまさん」と親しまれています。 この境内の一角に陶器神社は有ります。西側の高速道路を挟んで陶器問屋が軒を並べている「とうきの町」の守り神・火防の神社として信仰されています。この境内には、時の話題を題材にして陶器人形のパネルが展示されています。 問屋街の中で陶器人形の実物を見つけました。 |
写真左より
|
||||||
 |
 |
 |
 |
|||||
|
|
||||||||
| 大正橋のこと 2003/10/20 大正区三軒家東1丁目 |
大正時代、渡し以外に川を渡る手段が無かった為、大正4年に支間長90.6m、幅員19mの当時としては最も長いアーチ橋が架設された。大正時代の幕開けを告げる物として「大正橋」と命名された。さらに大正区の名称はこの橋にちなんで付けられたそうです。戦後、泉尾今里線の拡張整備に伴い、昭和46年3月に撤去され、同49年3月に我が国最初の合成箱桁橋(橋長80m、幅員41m)として架設された。尚、橋詰には「伊予の青石(紫雲石)」の原石が設置され、南側欄干は5線紙に見立てられ、ベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」が約17小節デザイン化されています。 | 写真左より
|
||||||
 |
 |
 |
 |
|||||
|
|
||||||||
| 浪速記念碑のこと 2003/10/15 浪速区幸町3丁目 |
大正橋の東詰めに記念碑は建っている。 嘉永7年(1854年)に大地震が浪速の町を襲い、安治川、木津川の両川口に大津波が押し寄せ大被害を被った。その時の教訓を供養塔の裏に彫り込んで代々伝える事にした。 元号が変わり安政2年(1855年)にこの碑は建てられた。1.4m程の泥水と大型の舟等が押し上げられかなりの被害状況だった様です。それ以後も何度か地震や津波が有った様です。 尚、この碑の見出しは「大地震両川口津波記」です。 |
写真左より
|
||||||
 |
 |
 |
 |
|||||
|
|
||||||||
| 旧毛馬基標のこと 2003/10/10 北区長柄中3丁目 (都島区毛馬町3丁目) |
 |
尚、写真の15.50と記載の単位は「尺」です。 |
||||||
| 毛馬閘門の敷地内に設置されています。この標石は明治から昭和にかけ、大阪港の建設や淀川改修工事等の高さの基準として使用され「毛馬基標」と呼ばれていました。大阪港の潮位観測により決められた工事基準面「0メートル(m)」を基として、明治19年に天保山の旧砲台跡に設けられたのが最初で、そこの高さは工事基準面「+2.045m」と定義されました。明治40年、毛馬閘門と同時にここにも設置されました。高さは工事基準面「+4.697m」でした。 しかし現在は使用されていなく、元の設置場所から東北東約20mの位置に記念碑として保存されています。 ちなみに現在は、昭和41年設置された茨木市にある国土土地院の基準水準点が使用されているそうです。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 法善寺横丁のこと 2003/10/05 中央区難波1丁目 |
先般の中座の類焼から免れた水掛不動さんは寛永14年(1637年)に創建され、商売繁盛、恋愛成就などを祈願して掛けられた水で苔がびっしり。どこが目やらお鼻やら。 西を向いて建っているので「西向不動明王」とも呼ばれています。 又この狭い敷地の中に金比羅堂も有ります。 織田作之助の「夫婦善哉」に執筆され有名になった横丁の一角に善哉屋が有ります。 デジカメを持った観光客や地元浪花っ子達の参拝でいつも線香の煙が絶える事が無い様ですよ! |
 |
||||||
 |
 |
 |
||||||
|
|
||||||||
| ★バックナンバ−★ ★2003/9★2003/8★2003/7★2003/6★2003/5★2003/4★2003/3★2003/2★2003/1★2002/12★2002/11★2002/10★ トップに戻る |
||||||||